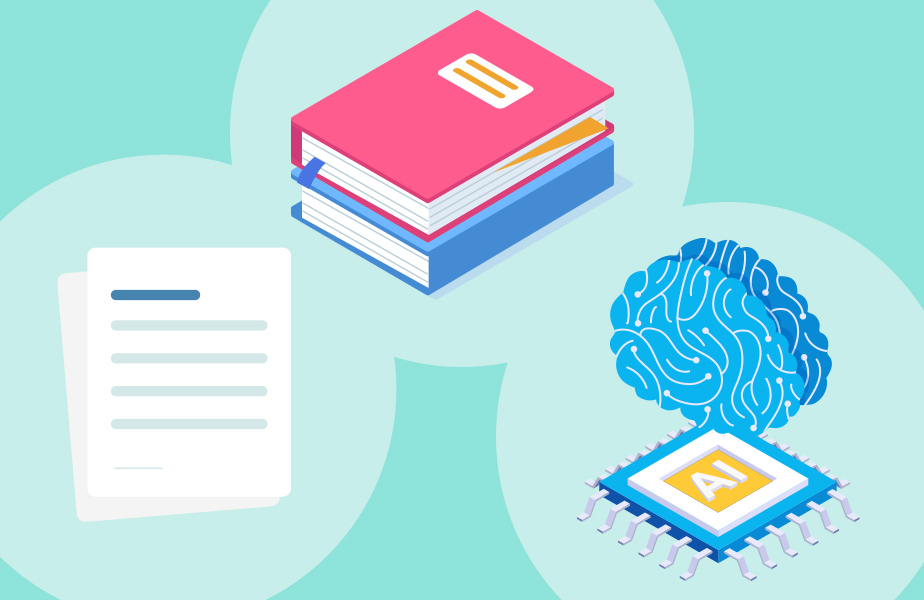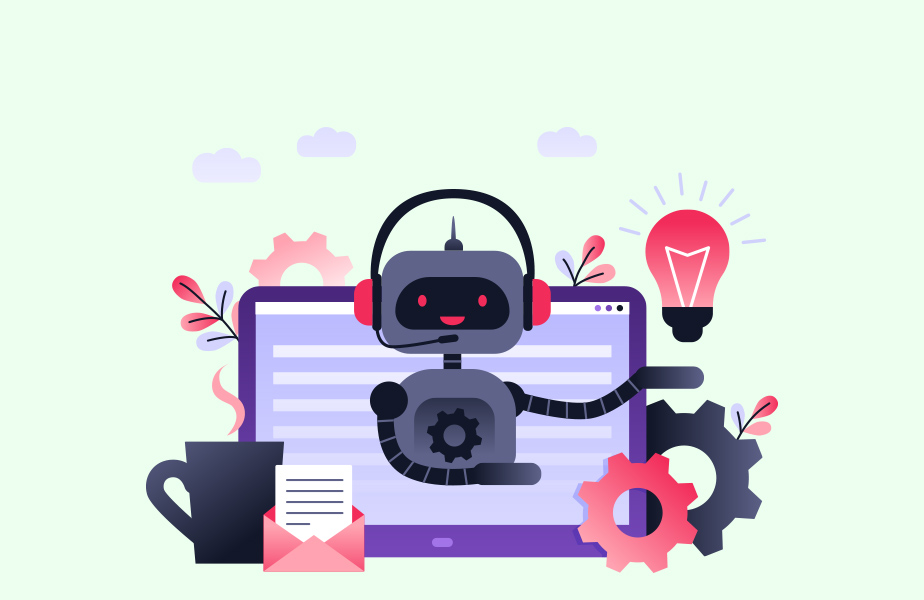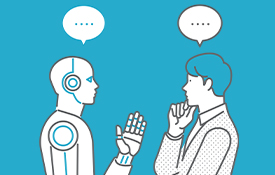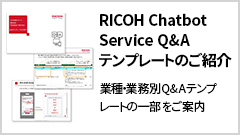目的別おすすめ情報共有アプリ15選|導入メリット・デメリットや選び方、最新のトレンド情報など詳しく解説

情報共有アプリを導入する企業は、年々増加傾向にあります。情報共有アプリを導入すれば、作業の効率化が図れるため、導入を検討している担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、情報共有アプリのメリットや選び方、おすすめの情報共有アプリ15種を紹介します。自社に適した情報共有アプリを選定する際の参考にしてください。
情報共有アプリとは、1か所に集約された情報を共有することができるアプリのことです。多くの種類やサービスがあり、情報の共有以外に高度な検索やチャット機能、Web会議機能、タスク管理機能などが搭載されているものもあります。
多くの情報共有アプリは、使い勝手がよいように工夫されているため、パソコンの初心者であっても比較的簡単に使えることも特徴です。
情報共有アプリと一言で言っても、その目的や機能によって様々な種類が存在します。自社の課題を解決するには、それぞれの特徴を理解し、最適なツールを比較検討することが重要です。ここでは代表的な4つの種類について解説します。
ビジネスチャット型
日常的なコミュニケーションの活性化に最適なのがビジネスチャット型です。テキストメッセージを中心に、スピーディなやり取りを実現します。個人間の連絡はもちろん、社外のパートナーを招待して連携することもできます。多くのツールでは、画像やドキュメントファイルの共有も簡単に行えるため、メールよりも迅速な情報伝達が可能です。社内wiki/ナレッジベース型
業務マニュアルや議事録、日報といった、企業内に蓄積すべき「ストック情報」の管理を得意とします。検索性に優れており、新入社員向けの業務ガイドや、過去のプロジェクトのノウハウ集として活用することで、業務の属人化を防ぎます。個人の知識や経験を組織全体の資産として蓄積していくための土台となるツールです。オンラインストレージ型
クラウド上で大容量のファイルを一元管理し、安全に共有するためのツールです。動画や高解像度の画像、設計データといった、メールでは送信が難しいファイルも容易に共有できます。また、Excelファイルなどを複数人で同時に編集できる機能を持つサービスもあり、バージョン管理の手間を大幅に削減します。アクセス権限を詳細に設定できるため、セキュリティを担保しながら効率的なファイル共有を実現します。プロジェクト管理型
特定の仕事やプロジェクトにおける「タスク」と「進捗」の可視化に特化しています。誰が・いつまでに・何をすべきかを明確にし、チーム全体の進捗状況をリアルタイムで共有できます。ガントチャートやカンバンボードといった機能で、複雑なプロジェクトも視覚的に管理し、遅延や対応漏れを防ぎます。

企業が、情報共有アプリを導入するには目的があります。ここでは、その目的について解説します。
業務効率化を図るため
情報共有アプリ導入の主な目的は、業務の効率化です。情報共有アプリによって、従業員が必要な情報にアクセスしやすい環境を整えることで、情報の収集や確認にかかる時間を削減できます。個人・企業で取り組める業務効率化のアイデア【16選】役立つツールも紹介
従業員間での情報共有漏れを無くすため
情報共有アプリを導入すれば、従業員間での情報共有漏れをなくすことも可能です。バックオフィスなどで属人化しやすいナレッジを共有すれば、誰もが同じ作業を行えるようになります。社内プロジェクトなどの情報共有にも不可欠なツールです。部門間でのスムーズな連携のため
社内の部門間での情報は縦割りになりやすく、スムーズな情報共有が難しくなりがちです。情報共有アプリを導入することによって、リアルタイムにオープンな情報共有が可能となります。認識齟齬を防ぐことができ、他部門との連携もスムーズになるでしょう。情報共有アプリを導入すれば多くのメリットがあります。ここでは、代表的なメリットについて解説します。
効率的な情報共有が可能になる
情報共有アプリのメリットの1つは、効率的な情報共有です。メールや社内回覧板などでは、特定のメンバー間のみの情報共有となりがちです。情報共有アプリを導入すれば、利用している全ての従業員へ一括での情報共有が可能となります。社内コミュニケーションの円滑化を図れる
情報共有アプリのチャット機能やメッセージ機能を使えば、従業員間で気楽にやりとりができるため、コミュニケーションの円滑化も図れます。従業員の誰もが同じ情報を共有することにより、効率的な業務が可能となり社内コミュニケーションの活性化にもつながります。社内情報の一元管理ができる
情報共有アプリの導入により、これまでメールや紙ベース、オフィスツールなど、さまざまな形態で保管していた情報を一元管理できます。一元管理されている情報をベースにすることにより、必要な情報にすぐアクセスできる環境を構築できます。
情報共有アプリは業務効率化に大きく貢献しますが、導入前にデメリットや注意点を理解しておかないと、期待した効果が得られない可能性があります。ここでは、導入時に考慮すべき主なデメリットを3つ挙げ、その対策について解説します。
導入・運用コストの発生
多くの高機能なアプリは、初期費用や月額の利用料が発生します。特に社員数が多い企業では、ライセンス費用が大きな負担となる可能性があります。まずは無料プランやトライアル期間を活用して複数のツールを比較し、自社の課題解決に必要な機能を見極め、費用対効果を慎重に検討することが重要です。利用する機能や人数を絞ってスモールスタートするのも一つの方法です。情報過多による生産性の低下
アプリ導入によって情報のやり取りが活発になる一方で、通知が多すぎると重要な情報が埋もれてしまい、かえって仕事の集中を妨げる「情報オーバーロード」に陥る危険性があります。これを防ぐためには、導入時に明確な運用ガイドを設けることが不可欠です。「緊急性の高い連絡のみメンションをつける」「会議の議事録は特定のフォルダに格納する」といったルールを定め、全社で共有することが定着の鍵となります。セキュリティリスクへの対策
クラウド型のアプリを利用するということは、企業の重要な情報を外部のサーバーに預けることを意味します。特に社外のメンバーとファイル共有を行う際は、情報漏洩のリスクも考慮しなければなりません。そのため、ツールの選定段階で、どのようなセキュリティ対策が講じられているか詳細を確認する必要があります。アクセス制限、IPアドレス制限、二段階認証などの機能が備わっているか、自社のセキュリティポリシーに適合するかを厳しくチェックしましょう。Excelに記載された個人情報や機密情報の画像などを安易に共有しないよう、社員への啓発も同時に行う必要があります。

情報共有アプリが職場でどのように活用されているか、ケース別に紹介します、自社への導入がイメージしやすくなります。
活用例【1】社内マニュアルの整備
社内マニュアルの整備には、ドキュメント作成やドキュメントの共有機能を搭載した情報共有アプリを導入しましょう。情報共有アプリなら、修正した社内マニュアルもリアルタイムで共有、更新できます。まずは、簡易なマニュアル作成から始めるとよいでしょう。活用例【2】業務連絡が多い職場での見落とし防止
業務連絡が多い職場環境では、業務連絡の見落とし防止として情報共有アプリが導入されています。情報をリアルタイムで更新できる、掲示板機能を搭載した情報共有アプリがおすすめです。従業員に掲示板をチェックする習慣を定着させれば、見落としを防止できます。活用例【3】スケジュールの可視化と共有
従業員のスケジュール共有のために、情報共有アプリが導入されているケースもあります。スケジュール登録機能を搭載した情報共有アプリの導入により、従業員のスケジュールが把握できます。共通のスケジュールも立てやすくなるでしょう。情報共有アプリを導入するにあたって、確認しておきたいポイントについて解説します。
情報共有アプリを導入する目的
情報共有アプリを導入することになった課題点の洗い出しや目的を明確にし、従業員と共有することが大切です。目的に適した機能を持つ情報共有アプリを導入すれば、効率よく情報共有アプリを活用できます。情報共有アプリの使用に関するルール
情報共有アプリの使用において、権限やルールを作ることが重要です。従業員の誰もが、社内の機密情報にアクセスできるような環境下であれば、情報漏えいリスクが発生します。情報共有アプリの運用担当者を決めるなど、ルールを作成して運用しましょう。情報共有アプリを選ぶ際にもポイントがあります。ここでは、主なポイントを5つ解説します。
自社の導入目的にあっているか
情報には大きくわけて、ストック情報とフロー情報があります。ストック情報とは、主にマニュアルのように蓄積して活用する情報のことです。反対に、フロー情報とはメールや会話の要なコミュニケーションなど、その場で活用されることを目的とした情報です。情報共有アプリを選ぶ際は、自社の目的と適しているかどうかを確認しましょう。ストック情報とフロー情報が一元管理できるかどうかも大切なポイントです。情報共有アプリの特徴や人数、利用料、プランなども確認する必要があります。
セキュリティ面は問題ないか
情報共有アプリでは、社外秘の情報を取り扱うことが増えるため、情報漏洩リスクや不正アクセスを防止する必要があります。セキュリティ認証など堅固なセキュリティ機能を有しているアプリを選ぶことが大切です。マルチデバイス対応や動作環境の確認
情報共有アプリは、多様なデバイスに対応しているものを選ぶことが大事です。従業員が使用するパソコンやスマートフォン、タブレットなど、どのデバイスでも利用できなければ、かえって業務に支障をきたす恐れがあります。自社が使用しているOSに対応しているかなどの動作環境も確認しましょう。誰でも無理なく使えるか
従業員全てが、ITに長けているわけではないため、従業員の誰もが無理なく使える情報共有アプリを選ぶことが大切です。利用方法を習得するだけで、膨大な時間がかかるものは避けましょう。直感的に操作できるものがおすすめです。サポート体制は整っているか
アプリ提供事業者のサポート体制が整っているかどうかも、重要なポイントです。トラブルの発生に対して迅速に対応してもらえなければ、損失につながる恐れもあります。サポートサービスが有料の場合もあるため、確認が必要です。タスク・スケジュール管理におすすめの情報共有アプリを3つ紹介します。
LINEWORKS
LINEWORKSは、LINEと繋がる唯一の情報共有アプリです。チャット機能だけではなくカレンダー機能やフォルダ管理などができます。LINEと同じ使い方でチャットができるため、普段感覚で操作できることがおすすめのポイントです。kintone
Kintoneは、企業のニーズに合わせたビジネスアプリを作成できる情報共有アプリです。エクセルのように、情報をまとめて管理できます。IOSとAndroidに対応したモバイルアプリも提供していることがおすすめのポイントです。サイボウズoffice
サイボウズ Office(オフィス)は、情報共有するための各種機能やメッセージ機能を備えた情報共有アプリです。ワークフローなどの基本機能だけでなく、ユーザーページで個人の情報が一元化でき、全ユーザーへの共通メッセージなども表示できます。スマートフォン、タブレット端末など、さまざまなデバイスから利用できることも大きな特徴です。
社内SNSとして使える情報共有アプリを2つ紹介します。
Microsoft Teams
Microsoft Teamsは、マイクロソフトが提供するビジネス向けの情報共有アプリです。資料を共有する機能や、チャットや通話やビデオ会議なども実施でき、リモートワークにおける社内情報の共有にも活用できます。Office 365と連携する機能を持つことも、おすすめポイントでしょう。Talknote
Talknoteは、社内コミュニケーションを円滑化させられる情報共有アプリです。親しみやすいデザインで、「スタンプ」や「いいね」を気軽に残すことができます。おすすめポイントは、既読未読の管理やタスク管理などが充実していることです。円滑なコミュニケーションにおすすめの情報共有アプリを2つ紹介します。
Chatwork
Chatworkは、ビジネス向けの情報共有アプリです。チャット感覚でコミュニケーションができて、スタンプ機能や返信機能などが充実しています。既読機能がないため、メッセージを自分のタイミングで確認できます。Slack
Slackは、ビジネス向けの情報共有アプリです。カスタマイズ性が高く、オリジナルの絵文字を作れたり、botを利用できたりします。他のサービスと連携させられる点も特徴です。ファイルやナレッジ共有に特化した情報共有アプリを3つ紹介します。
Dropbox
Dropboxは、さまざまなファイルを一箇所で管理できて、共有もできる情報共有アプリです。従業員間で共有しやすい環境を提供しています。おすすめのポイントは、クラウド上で全てを保存できるため、いつでもどこでも情報共有ができることです。Stock
Stockは、情報を簡単に残せる情報共有アプリです。情報共有が簡単なため、情報共有ストレスが解消されます。余計な機能がなくシンプルなアプリで、誰でも簡単に情報を残せます。RICOH Chatbot Service
RICOH Chatbot Serviceは、AIを使いチャットボットが自動で応答可能なツールです。経理、人事、総務、情報システムなど幅広い部署において、社内のマニュアルや社内規定についてなどを気軽に聞けて即時に回答を入手できます。24時間対応可能なことも、特にリモートワークの際に便利でしょう。ドキュメント作成・管理ができる情報共有アプリを3つ紹介します。
esa
esaは、自律的なチーム向けの情報共有アプリです。可愛いデザインで、書き込み途中で公開できる機能があり、情報を育てるという視点で構築されています。おすすめのポイントは、記事の外部公開とスライドショーです。flouu
flouuは、豊富なテンプレートが用意されており、簡単にドキュメントが作れる情報共有アプリです。ドキュメントは複数の従業員で同時編集できます。チャット機能を使い、会話感覚でドキュメント編集ができることが特徴です。Qiita:Team
Qiita:Teamは、ブログ感覚でドキュメントを簡単に作成できる情報共有アプリです。テンプレートの使用により、フォーマットが統一できるため議事録や日報を統一できます。ドキュメント管理のしやすさがおすすめです。掲示板機能を搭載した情報共有アプリを2つ紹介します。
desknet’sNEO
desknet’sNEOは、多くの機能を持つ情報共有アプリです。直感的な操作で27の機能を使用することができ、掲示板機能だけでなく、スケジュールやプロジェクト管理、オリジナルのアプリ開発まで可能で、さまざまな業務に対応できます。スマートフォンにも対応しており、カスタマイズのしやすさがおすすめのポイントです。R-GROUP
R-GROUPは、人数制限なしに無料で利用できる情報共有アプリです。マルチデバイス対応なため、在宅ワークなどにも活用できます。20カ国以上の言語に対応しています。Chat&Messenger
Chat&Messengerは、ビジネスチャット機能が搭載されている情報共有アプリです。音声通話機能も搭載されているため、在宅勤務やリモートワークなどにも活用できます。掲示板機能やタスク管理機能が充実しています。チャットボットとは企業のWebサイトなどに組み込むことで、Web上でユーザーからの質問に自動回答を行うツールです。チャットボットは主にWebサイト、社内ポータル、アプリなどに設置することで、問い合わせ対応の自動化を実現することが可能になります。
ここではアプリにチャットボットを導入する方法を2つご紹介します。
①アプリと外部チャットボットを連携させる
ベンダーで開発されているチャットボットと導入したいアプリを連携させる方法です。開発費用は比較的安価で済むケースが多く、多くの企業ではこちらの方法が採用されています。
②自社で開発したチャットボットをアプリ内に組み込む
こちらはチャットボットを一から自社で開発し、それをネイティブアプリ(AppStoreやGooglePlayからダウンロードできるアプリ)に組み込む方法です。自社で開発を行うため費用は高くなり、開発にあたりノウハウが必要となります。
チャットボット(Chatbot)とは?初心者にもわかりやすく解説
情報共有アプリは、テクノロジーの進化とともに日々発展を続けています。最新のトレンドを把握することで、将来を見据えたツール選びが可能になります。ここでは、特に注目すべき2つのトレンドについて解説します。
AI(人工知能)機能の搭載
近年の最も大きなトレンドがAIの活用です。会議の動画や音声データを自動で文字起こしし、要約を作成する機能や、蓄積されたデータの中から必要な情報をAIが探し出してくれる検索アシスト機能などが登場しています。これにより、議事録作成といった仕事の手間が大幅に削減され、ナレッジの活用がさらに促進されます。今後は、過去のやり取りを分析して最適な回答案を提示するなど、より高度な活用が期待されています。多様なツールとの連携強化(ハブ化)
一つのアプリで全ての業務を完結させるのではなく、各分野で優れた機能を持つ複数のアプリをシームレスに連携させる「ハブ化」が進んでいます。例えば、ビジネスチャットを起点に、カレンダー、Web会議システム、オンラインストレージなどを連携させ、情報を集約します。Excelやスプレッドシートの更新通知をチャットに飛ばしたり、クラウドストレージのファイルを直接共有したりすることで、アプリ間を移動する手間を省き、業務フローを円滑にします。情報共有アプリは、多くの企業で導入され業務効率の向上に役立っています。情報共有機能だけではなく特徴的な機能を備えたものも多いため、自社に適したアプリを導入しましょう。
情報を共有するだけでなく、適切に収集・分析していくことも重要です。例えば、チャットボットを導入すれば、顧客のニーズを把握するためのデータ収集に役立ちます。チャットボットの導入を検討するなら、ぜひ「RICOH Chatbot Service」をご検討ください。記事内で紹介したLINEやMicrosoftTeamsなど数多くのアプリ上でも動作し、さまざまなナレッジの共有が可能です。
資料ダウンロードはこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。
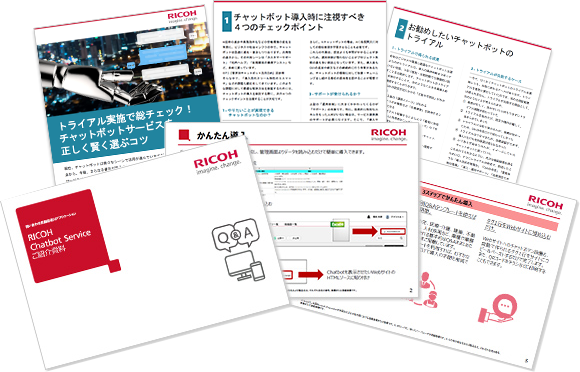
以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!