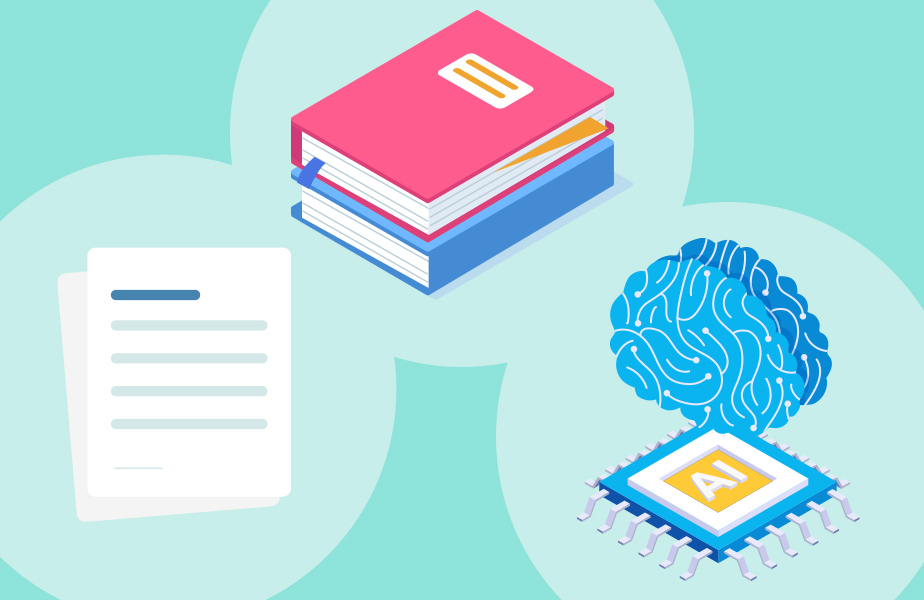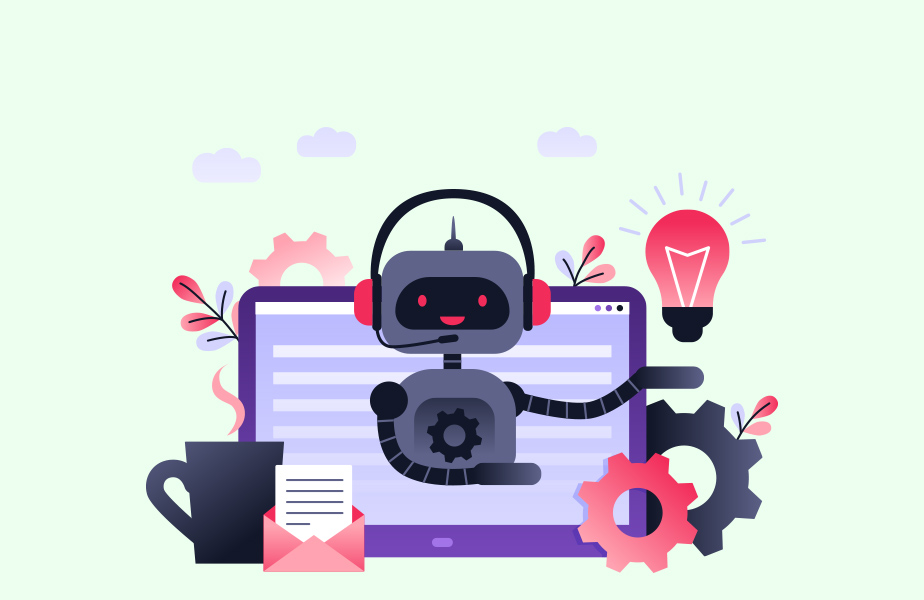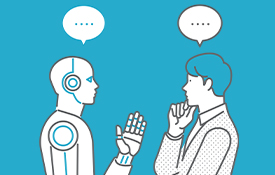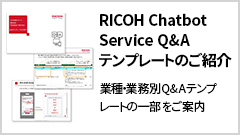業務効率化とは?
背景から成功のポイント、AI活用トレンドまで徹底解説

「業務効率化」という⾔葉をよく聞くようになりました。実際、無駄と思える作業や残業をなくすために、業務の効率化を検討する企業が増えています。しかし、⼀⼝に業務効率化といっても⼀体何をすればいいのか、何から始めればよいのかわからない⽅も多いでしょう。
この記事では、業務を効率化するメリットや具体的な⽅法、さらには効率化を進める上での注意点も紹介します。ぜひ参考にしてください。
業務効率化とは、業務上無駄であることや無理な要素を取り除き、時間的、費⽤的なコストを削減することです。具体的には、実現不可能なスケジュールや不要な業務の削減、適切な⼈材配置などを通じて業務効率の最適化を図ります。
時間や資⾦、そして⼈材は有限です。業務効率化を推し進めることで、限られた資源を余すところなく活⽤できるようになります。それは会社にとっても個⼈にとっても⾮常に有益です。

現代のビジネス環境において、業務効率化は単なるコスト削減策ではなく、企業の持続的な成長を左右する重要な経営課題となっています。その背景には、社会構造や働き方の大きな変化があります。
最も深刻な要因は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少です。限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、既存の業務プロセスを抜本的に改善し、生産性を向上させる取り組みが不可欠となりました。この動きを加速させているのが、国が推進する「働き方改革」です。長時間労働の是正や多様な働き方の実現が求められる中で、企業は従業員が限られた時間内で最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整える必要に迫られています。無駄な業務を削減し、従業員が付加価値の高いコア業務へ集中できる環境を構築することが、企業の競争力、ひいては従業員満足度の向上にも直結します。
さらに、AIやクラウドといった最新IT技術の進化は、DX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に後押ししています。これは、単にアナログ業務をデジタルに置き換えるだけでなく、データ活用を基盤としてビジネスモデルそのものを変革する動きです。このDX推進の第一歩として、非効率な業務を効率化することは避けて通れません。このような背景から、現代における業務改善の目的は、変化に対応し、新たな価値を創造するための経営基盤を構築することにあるのです。守りの施策ではなく、企業の未来を創るための戦略的な取り組みとして、その重要性はますます高まっています。
業務効率化と同⼀視されやすい概念の⼀つに、「⽣産性向上」があります。しかし、その意味は異なります。
⽣産性向上とは、「最⼩限の資源で最⼤限の成果を上げること」であり、⽬的です。⼀⽅、業務効率化は業務上の無駄を省いて時間や費⽤などを節約することであり、⽬的ではなく⼿段といえます。つまり、⽣産性向上という⽬的を達成するための⼿段の⼀つが「業務効率化」なのです。
次で詳しく紹介しますが、業務効率化には⽣産性の向上以外にも多くのメリットがあります。
企業における業務効率化は、経営者側だけではなく従業員にとってもメリットがあります。それぞれのメリットを具体的に⾒ていきましょう。
【経営者側】コストを削減できる
業務効率化の最⼤のメリットは、さまざまなコストの削減です。たとえば、無駄な業務をなくして残業や休⽇出勤が減ると、その分⼈件費を抑えられます。また、会議資料のペーパーレス化を⾏えば、準備にかかる時間や労⼒のほか、紙代やインク代なども削減できます。
【経営者側】利益が上がる
業務効率化を進めると、利益率の向上が期待できます。必要な⼈件費や消耗品費などを抑えられれば、その分利益は純増するでしょう。削減したコストを別の業務に充てることで、さらなる利益を上げることも可能です。
【従業員側】個⼈の負担が軽減する
業務効率化によって業務の無理や無駄がなくなると、個々の従業員の負担も減ります。その結果、従業員の気持ちに余裕が⽣まれ、業務のパフォーマンスが向上します。また、精神的、⾝体的な負担が減ることで、従業員の健康維持につながる効果も期待できます。
【従業員側】仕事の満⾜度とモチベーションが上がる
残業や休⽇出勤が減ると、仕事以外の時間を確保できます。プライベートの時間やスキルアップの機会が増えるのは、ワークライフバランスの構築において⾮常に重要な要素です。結果として、仕事へのモチベーションや満⾜度が上がり、⽇々の業務に打ち込めるようになります。
業務効率化を実現する⽅法は、⼀つではありません。次に紹介する⽅法から、まずは取り⼊れやすいものを検討してみましょう。
ツールやシステムを導⼊する
業務効率化のポイントは、従業員の能⼒に関係なく、誰でも標準以上の成果を上げられるようにすることです。これを実現する⽅法として、ツールやシステムの導⼊を検討しましょう。
たとえば、勤怠管理や販売管理などは誰が⾏っても同じ成果を出さなくてはなりません。このような管理業務にツールやシステムを導⼊すると、作業が標準化され、個々の能⼒による業務への影響が⼩さくなります。ツールやシステムの使い⽅さえマスターすれば、誰でも同じ業務を遂⾏することが可能になるため、業務の安定にもつながります。
⾃動化ツールやシステムを採⽤する
決まった⼿順をこなすだけの業務は、⾃動化することによって削減できます。エクセルを利⽤した業務の場合、マクロを活⽤すると同じ操作をワンクリックで実⾏可能になります。また、⼊⼒した値や⾦額のチェックなどを⾃動化するRPAを導⼊すれば、単純業務だけではなく⼈的ミスの削減も可能です。
定型的な業務だけではなく、⼈的な判断の補助にAI技術を⽤いる動きも広まりつつあります。ただし、AI技術の取扱いは専⾨的な知識やスキルが必要になるので、導⼊するには知⾒を持つ⼈材の確保が必要になります。
ワークフローを効率化する
ワークフロー上から時間や場所といった制限を取り払うことも、業務の効率化につながります。たとえば、リモートワークを導⼊すればオフィス以外でも作業ができるようになり、通勤時間や費⽤が削減できます。
タブレットなどを活⽤して⽂書を電⼦化し、ペーパーレス化を進めるのも効果的です。ネットワーク上で会議を⾏えるようになれば、会議⾃体を省略し、紙の書類にまつわるコストを削減できます。
社内外からの問い合わせが多い場合は、ヘルプデスクのBOT化、いわゆるチャットボットの導⼊も検討してみましょう。チャットボットとは、BOTによる⾃動対応のことです。あらかじめ想定問答を設定しておくと、担当者が不在であっても⾃動で回答してくれます。
無駄な時間をなくす
業務における無駄な時間の削減は、業務効率化の基本といえます。
例えば、定例化したものや情報共有だけを⽬的としたような会議は、無駄な時間の⼀例です。会議にかかる労⼒が、会社全体の⼈件費の増⼤や作業リソースの逼迫を招くこともあります。ツールやシステムを導⼊することで、会議を開かなくても常にリアルタイムで情報共有を⾏うことが可能です。
⽇々の⽇報作成も、無駄な時間を⽣み出しているといえます。作成は報告事項がある場合に留めるなどして、作業そのものの省⼒化を検討するべきでしょう。
⼈員を再配置する
会社によっては、これ以上業務を減らすのが難しいというケースもあるでしょう。このような場合でも、⼈員を再配置することによって業務効率化を図れることがあります。
適材適所といわれるように、個々の従業員の能⼒に応じて適切な業務を割り当てると、業務効率の向上が期待できます。また、超過勤務の時間数から繁忙期と閑散期の部署を分析し、弾⼒的に⼈員を配置するのも⼀つの⽅法です。
アウトソーシングを利⽤する
アウトソーシングは、業務の⼀部を社外に委託することです。たとえば、給与計算などの定型的な業務処理を外部に委託すれば、従業員の労働時間に余裕が⽣まれ、より⽣産性の⾼い業務に専念することができます。
また、専⾨的な業務を外部に委託することも検討してみましょう。専⾨家や業者へコンサルティングを依頼した場合、社内で専⾨家の雇⽤や育成にかかるコストを減らせる場合があります。ただし、本当にコスト削減となるかどうか、あらゆる⾯からよく精査してからにしましょう。

業務の効率化は個⼈単位でも実⾏できます。次に紹介する内容を⽇々の業務に取り⼊れてみてください。
業務に優先順位をつける
業務に優先順位をつけることは、業務効率化の基本です。業務は優先度の⾼いものから順番に処理しましょう。順位をつけるときのポイントは、時間のかかる業務や調整を必要とする業務を優先することです。こうした業務をこなす合間に、簡単な業務も並⾏して処理していくと効率化できます。
業務のマニュアルを作成する
誰でも⼀定の業務成果を出せるような「業務マニュアル」の作成も、業務効率化の具体策です。マニュアルは、業務⼿順だけではなく、関連するルールや規則なども紐付けることが⼤事です。業務内容を体系的に理解できる質の⾼いマニュアルを作成しましょう。
業務にデータベースを活⽤する
過去の業務内容を、データベース化しておくのも有効です。顧客情報や在庫管理などは、データベース化すべき基本的な情報といえます。さらに、顧客からの問い合わせや回答などをデータベース化しておけば、類似の質問があった場合にも同じように対応できます。
権限を⼀⼈に集約しない
特定の担当者に承認権限を集約すると、作業が増加したときに承認が進まず、時間がかかったり対応が滞るリスクがあります。できるだけ承認権限は複数の担当者に分散させましょう。
しかし、責任の所在が明確になるよう、権限は同じ職位の⼈に付与するといったような配慮は必要です。
【関連コラム】個人・企業で取り組める業務効率化のアイデア【16選】役立つツールも紹介
やみくもに策を講じても、業務効率化はうまくいきません。これから紹介するポイントを押さえた上で具体的な施策を検討するようにしましょう。
社内体制を整備する
社内の業務状況にそぐわない⽅法を持ち込むと、かえって現場が混乱するリスクがあります。まずは業務効率化を無理なく進められるように、社内体制を整備しましょう。既存の業務フローとも照らし合わせて、どこを整備すればよいか確認しながら進めることが⼤切です。
全てのアイデアを同時に実⾏しない
全てのアイデアを同時に実⾏すると、どれも中途半端に終わってしまうことがあります。複数のアイデアがある場合は、確実に達成できるものから実⾏しましょう。達成可能なアイデアかどうかを⾒極めるには、実⾏する担当者の能⼒なども考慮する必要があります。
まとめられる業務はまとめる
似たような業務は、作業が重複している可能性があります。複数の担当者が同じような業務をしている場合は、⽚⽅に集約してみましょう。回数の多い作業も整理対象となりやすい業務です。何度も⾏われている会議や報告を⼀回にまとめれば、その分だけ時間や労⼒を削減できます。
ミスは必ずフィードバックする
⼈がやる以上ミスは必ず起きますが、フォローや解決にはそれなりの労⼒が必要です。起きたミスは必ずフィードバックして、⼆度と発⽣しないように務めましょう。フィードバックの際に別部署でも同じようなミスがないかを確認し、社内全体でくり返させないようにすることが重要です。

ツールの導入やプロセスの見直しといった業務改善を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、組織全体としての取り組みが不可欠です。本ブロックでは業務効率化への取り組みのポイントを紹介します。
●目的の明確化と共有「何のために業務効率化を行うのか」という目的が組織全体で共有されていなければ、従業員の協力は得られず、改善活動は形骸化してしまいます。経営層が明確なビジョンを示し、業務の効率化を図る意義を丁寧に説明することが重要です。
●変化を受け入れる環境の整備従業員が新しいツールやプロセスを積極的に受け入れ、活用できる環境を整備することも欠かせません。十分なトレーニングの機会を提供したり、導入初期の混乱をサポートする体制を整えたりすることで、変化に対する心理的な抵抗を和らげることができます。
●全部署を巻き込んだ改善プロセスの構築一部の部署だけで取り組みを進めるのではなく、部署横断で課題を洗い出し、解決策を検討するプロセスも効果的です。これにより、組織全体の視点から最適な業務改善を図ることが可能になります。
●主体性を尊重する組織文化の醸成最終的に、継続的な業務効率化を実現するためには、従業員一人ひとりが「やらされる」のではなく、主体的にビジネスの課題解決に取り組む文化を育てることが不可欠です。現場からの小さな改善提案を積極的に評価・採用する制度を作るなど、ボトムアップでの取り組みを奨励することが、変化に強い持続可能な組織へと繋がります。

近年のAI技術の進化は、DXの取り組みを加速させ、業務効率化に新たな可能性をもたらしています。本ブロックでは、AIを活用した業務効率化の最新トレンドを紹介します。
●AIによる高度なデータ分析膨大なビジネスデータの中から、AIが人では見つけられないパターンや関連性を発見します。これにより、高精度な需要予測や市場トレンドの分析が可能となり、データに基づいた客観的で迅速な経営判断を支援します。在庫の最適化や効果的なマーケティング戦略の立案など、具体的な課題解決に大きく貢献します。
●自然言語処理技術の活用人間の言葉をAIが理解・処理する技術です。顧客からの問い合わせに24時間365日対応するAIチャットボットや、会議の音声を自動でテキスト化し議事録を作成するツールなどが実用化されています。これにより、従業員の対応工数を大幅に削減し、より重要な対人業務や戦略的な思考を要するプロセスにリソースを振り分ける環境が整います。
前述の業務効率化を実現する方法のブロックにて、問い合わせ対応においてチャットボットの導入を紹介いたしましたが、本ブロックではチャットボットの概要や、メリット・デメリット、できることを簡単に紹介いたします。
チャットボットとは
チャットボットとはWebサイトやアプリなどに組み込むことで、Web上でユーザーからの質問に自動回答を行うツールです。【関連コラム】チャットボット(Chatbot)とは?│初心者にもわかりやすく解説
チャットボットの導入メリット・デメリットとは
メリット・問い合わせ対応のコスト削減・業務負荷低減につながる・業務効率化、生産性向上が期待できる
・24時間365日問い合わせ対応が可能になる など デメリット・Q&Aデータの準備・メンテナンスなど手間がかかる
・すべての質問に対応することができない
・個別対応の質問が多い場合は不向き など
チャットボットでできること
・24時間365日の問い合わせ対応・業務効率化、業務負荷の軽減
・社内、社外の問い合わせ数削減 など
【関連コラム】チャットボットの導入事例19選!業界別の事例や導入手順・費用も解説
業務効率化を実施すれば、時間や費⽤といったコストが削減できます。利益のアップはもちろんのこと、従業員の満⾜度やモチベーションの向上も期待できるでしょう。
しかし、業務効率化の実現は簡単ではありません。どれだけ素晴らしいアイデアがあっても、社内の業務フローとマッチングしなければ逆に無駄を⽣むことになります。まずは社内体制を整備し、実⾏可能かつ優先度の高いものから順番に検討しましょう。定型的な業務の効率化、自動化を検討されるようでしたら、「チャットボット導入」をおすすめします。なお、RICOH Chatbot Serviceは、低コスト、専門知識不要で始められるAチャットボットです。導入時、導入後も専任メンバーがしっかりサポートするため、自社のチャットボット運用業務の効率化も図れます。
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。
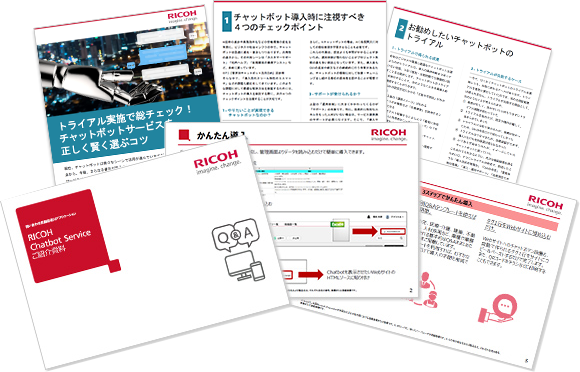
以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!