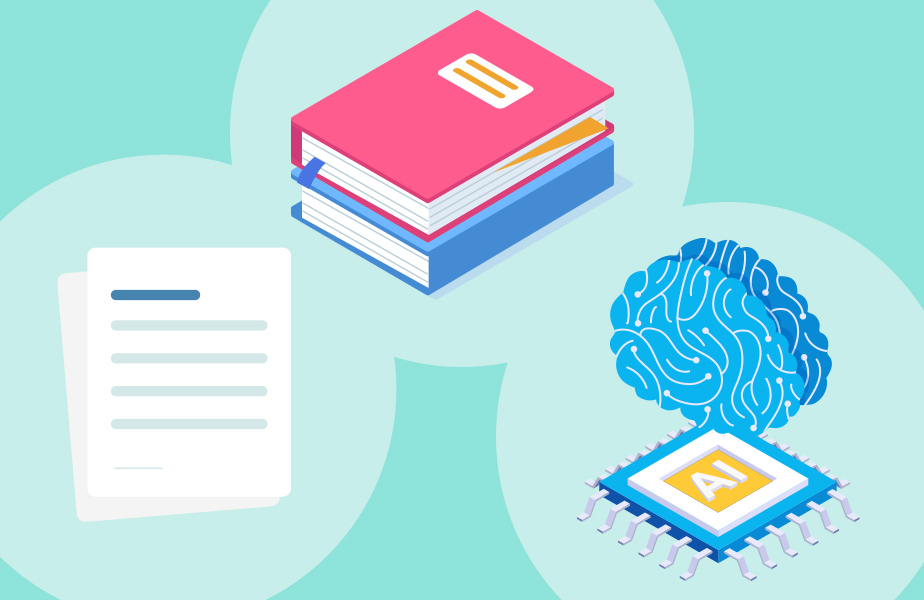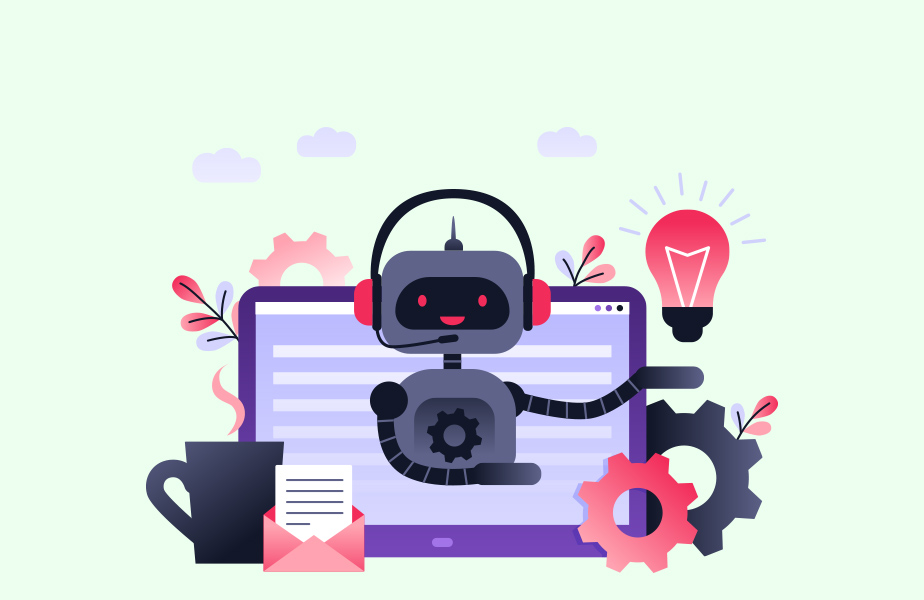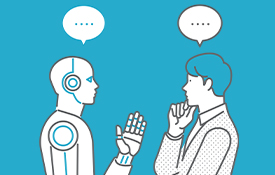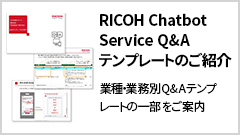チャットボットの仕組みとは
- ハイブリッド型チャットボットなどを紹介

最近、チャットボットを設置している企業サイトを多く目にするようになりました。現在チャットボットの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。そこで、導入前にチャットボットの仕組みを知っておくと役立ちます。特に手軽に導入できるルールベース型はおすすめです。その理由も合わせてご紹介します。
●チャットボットとは
チャットボットとは、サイトやアプリなどに設置してユーザーと自動的に会話(チャット)を行うことができるプログラムのことです。チャットボットを自社のサイトに組み込むことで、ユーザー側は気軽に質問や相談が出来るようになり、企業側は問い合わせ対応業務が削減できるとして、近年、様々な企業で導入が進んでいます。
【関連コラム】チャットボット(Chatbot)とは?│初心者にもわかりやすく解説チャットボットの使い方-種類や仕組み、活用例をご紹介
●チャットボットの基本機能
チャットボットの機能には主に以下のようなものがあります。・自然文による応答機能
・選択肢を示す機能
・有人対応へ切り替える機能
・アンケート機能
・外部システム連携機能
各機能の詳しい解説は以下のコラムでご確認いただけます。
【関連記事】チャットボットの基本機能 - 有人対応やアンケート機能など

チャットボットの導入は、単なる問い合わせ対応の自動化に留まらず、企業に多様なメリットをもたらします。その実際の効果を理解することで、自社の課題解決に繋がる戦略的な活用が可能です。以下でチャットボットを導入した際のメリットを一部ご紹介します。
●24時間365日対応による顧客満足度の向上企業の営業時間外や休日に発生する問い合わせに対応できないことは、機会損失や顧客満足度の低下に直結します。チャットボットを導入すれば、時間を問わず24時間いつでも顧客からの質問に即時回答できる体制が整います。待ち時間なく疑問を解消できるという体験は、満足度を大きく向上させる要因となります。これにより、深夜帯にサービスを利用するユーザーや、時差のある海外からの問い合わせにも対応可能となり、幅広いニーズに応えることができます。
●潜在ニーズの可視化とサービス改善チャットボットに蓄積された顧客との対話ログは、貴重なデータの宝庫です。これらのデータを分析することで、電話やメールでは拾いきれなかったユーザーの実際の悩みや要望、つまり潜在的なニーズを可視化できます。どのような質問が多いのか、どのページで離脱しているのかといった詳細な分析は、FAQの改善、新サービスの開発、WebサイトのUI/UX改善など、具体的なアクションに繋がります。

チャットボットは、ユーザーから質問文を受け取ると、「キーワード分析」「データベース検索」「回答文作成」という3つの手順によって、ユーザーへ回答文を返します。
(1)キーワード分析
上の図のように、まずユーザーがPCやスマートフォンのブラウザやアプリなどに表示されるチャットボットのフォームに質問などをテキスト入力します。するとチャットボット側は、その入力された質問文に含まれる重要なキーワードを抽出する「キーワード分析」を行います。
AI型のチャットボットは、この分析にAI(人工知能)を使って抽出するため、よりユーザーの質問の主旨に近いキーワードを抽出することができます。
(2)データベース検索
次に、チャットボットに備わるデータベースにアクセスして、抽出されたキーワードに紐付く適切な回答を検索する「データベース検索」を行います。データベースにより豊富なキーワードと回答が用意されていれば、より精度の高い回答をユーザーに返すことができます。
データベース上にあるキーワードと合致すれば、すでに登録してあったキーワードに紐付く回答を引っ張ってきます。
(3)回答文作成
適切な回答をデータベースから拾ってきたら、次は「回答文作成」を行います。
あらかじめデータベースに回答文を用意しているものをそのままユーザーに返す場合と、AIが単語をいくつか組み合わせて自然な文章に直す場合とがあります。
回答文が完成したら、すぐにユーザー側のチャットボットに表示させます。すると、ユーザーは質問への回答を閲覧することができます。
・シナリオ型チャットボット
シナリオ型チャットボットとは、チャットボットのユーザーがたどるシナリオをあらかじめ設定しておき、選択肢をいくつか用意し、それをユーザーが選んで進んでいくチャットボットです。ユーザーに文字入力の手間をかけず、質問分岐を適切に設定することで手軽に利用できるメリットがあります。
【関連記事】シナリオ型・機械学習型チャットボットの違い・メリットは?~シナリオ作成の基本ステップも解説!
・辞書型チャットボット
辞書型チャットボットとは、事前にキーワードとなる単語と、そこから考えられる回答を組み合わせた複数の単語をあらかじめ辞書として登録しておくチャットボットの仕組みです。そのキーワードが入力されたときに適した回答を返すことができます。ユーザーが知りたい内容を単語や文章で入力した中に、該当するキーワードが一語でも含まれていれば回答を返すことで会話が成り立ちます。そのため、うまく質問と回答を設定できれば、人と直接会話をしているようなスムーズな対応ができるメリットがあります。
【関連記事】チャットボットの辞書型の成功事例をご紹介
・シナリオ型と辞書型のハイブリッド型チャットボット
シナリオ型と辞書型の両方の機能を併せ持つハイブリッド型チャットボットもあります。ケースに応じて選択肢を提示することもできますし、辞書から回答を返すこともできます。よりユーザーにとって“使える”チャットボットサービスとしてハイブリッド型チャットボットが利用されるケースが増えています。
ハイブリッド型チャットボットで問い合わせ業務の削減や顧客満足度の向上を実現
AI型チャットボットとは、機械学習型ともいわれるもので、AIを搭載したチャットボットのことです。あらかじめ大量の人間の会話を学習し、ユーザーから入力された文脈を解釈して回答するチャットボットの仕組みです。
例えば「Aという単語の後にはBと回答するパターンが多い」ということをAIが学習します。するとユーザーが「A」と言ったときは「B」と返せるようになります。辞書型と異なるのは、学習して文脈を解釈した上で回答を返す点です。事前に大量の学習とともに、チャットボットが利用されるほど精度が上がっていく特徴があります。いかに学習をさせるかというところにかかっているともいえます。
AIチャットボットの作り方とは?基礎知識から導入後のポイントまでを解説

チャットボットは、種類に応じて様々な仕組みで動いていることがわかりました。それぞれの仕組みには、導入・運用に関する注意点があります。チャットボットの種類ごとにそれぞれの仕組み上の注意点をご紹介します。
●ルールベース型のチャットボットの仕組み上の注意点
・事前にシナリオや辞書の設定が必要 ルールベース型のチャットボットは、使い始める前に、必ずシナリオや辞書の設定が必要です。先述の通り、ルールベース型のチャットボットは、必ずシナリオや辞書に基づいて会話を返す仕組みだからです。手間がかかりますが、効率的にチャットボットを設定するには、過去にお問い合わせのあった質疑応答データを集める、営業担当者やカスタマー対応担当者によくある質問を聞くなどしてQ&Aを収集することがポイントです。そこから必要なシナリオや辞書を設定していきます。また、チャットボットサービスによっては、業種別Q&Aテンプレートを用意しているところもあります。その場合、それを編集することで、一からQ&Aを作るのと比較して時間短縮につながります。
・設定したシナリオ・辞書以外の回答ができない ルールベース型のチャットボットは、AI非搭載型であるため、その仕組み上、自ら返答を返すということはできません。あくまで登録されているデータを自動的に返します。
そのため、チャットボット選定時にはあらかじめ使用用途を絞っておくのがおすすめです。例えばよくある質問といったパターン化された質疑応答であれば、ルールベース型のチャットボットが向いています。一方で、臨機応変に会話を楽しんでもらうような用途の場合、ルールベース型のチャットボットは向いていません。このように、適した用途で利用することがポイントです。
また、回答できなかった問い、つまりあらかじめ設定していなかった問いも出てくるでしょう。ユーザーが困らないよう、有人チャットや有人オペレーターの電話に取り次ぐ仕組み作りを行っておくことも必要です。
●AI型のチャットボットの仕組み上の注意点
・大量の学習データの準備とメンテナンスが必要 AI型のチャットボットについては、事前に学習データを用いて学習させる必要があります。特にお客様に対して提供するチャットボットとして機能させるためには、事前学習データは膨大である必要があります。また、AI型のチャットボットはその都度、メンテナンスを行う必要があります。一度覚えさせたらそれで終わりではないのです。チャットボットの回答精度を上げていくためには、そのメンテナンスの工数や仕組みも検討しておく必要があります。
・導入コストが多くかかる傾向がある AI型のチャットボットの懸念点として、導入コストの問題があります。チャットボットの仕組みや運用がシンプルなルールベース型のほうが一般的に安価に導入できるため、必要でなければAI型である必要はないでしょう。またメンテナンスも知見のある人材にしか行えないとなると、さらに運用コストがかかってきます。ただしAI型のチャットボットはコストをかけた分だけ、柔軟な回答を返すことができるため、目的に見合った投資であれば利用の価値はあるでしょう。
チャットボットの種類の中で、より手軽に導入できるのがルールベース型です。そこで、ここではルールベース型のチャットボットの魅力をご紹介します。
既存のFAQをインストールするだけで利用ができる
AI型のチャットボットは精度向上の可能性が高いものの、事前に膨大な学習データが必要になる上に、利用がされなければ成長していかないという点があります。また、ある程度学習させて運用を開始したとしても、質問に対する回答が正しいかを定期的にチューニングする必要があります。 それに対して、ルールベース型のチャットボットは、あらかじめ作成したFAQをインストールすればすぐに利用開始でき、随時、FAQを追加していくことでチャットボットを成長させていくことができ、導入やメンテナンスが行いやすい仕組みになっています。FAQは、チャットボットサービスが用意したテンプレートを利用すればより簡単かつスピーディーにスタートできます。導入コストが安い
価格面からすれば、ルールベース型のチャットボットはAI型と比較してより安価に導入できます。コストを抑えたい場合にもおすすめです。ユーザーにとっての使い勝手が良い
ルールベース型のチャットボットは、ユーザーにとって使い勝手が良いのも特徴です。AI型は学習の途上では精度が落ちることがあるため、使い勝手が下がることもあります。ルールベース型はあらかじめ決まった内容しか回答しないため、十分に作り込んでおくことで精度を高められます。
チャットボットの種類の中では、正確性(ルールベース型)と柔軟性(AI型)を両立できるハイブリッド型も存在します。そこで、ここではAIを使用したハイブリッド型のチャットボットの魅力をご紹介します。
●幅広い問い合わせに対応できるハイブリッド型の最大の魅力は、ルールベース型の「正確性」とAI型の「柔軟性」を兼ね備えている点です。「定型的な質問にはシナリオに沿って確実に回答し、シナリオにない複雑な質問や曖昧な表現にはAIが意図を汲み取って回答する」といった使い分けが可能です。この方法により、簡単な質問への迅速な対応と、イレギュラーな問い合わせへの対応力を両立させ、多様化する顧客のニーズに幅広く応えることができます。実際の運用では、多くの問い合わせを自動化しつつ、重要な場面では有人対応に切り替えるといった連携もスムーズです。
●データを活用した高度なマーケティング展開の手助けになるハイブリッド型チャットボットは、単なる問い合わせ対応ツールに留まらず、高度なマーケティングツールとしても機能します。ルールベースの部分で正確な顧客情報を聞き出し、AIがその詳細なデータや対話履歴を分析して、個々の顧客が持つ潜在的なニーズを掘り起こします。その分析結果を基に、最適な商品やキャンペーン情報をチャット上で提案するなど、One to Oneマーケティングを展開することも可能です。これにより、24時間稼働する自動営業担当として、新たなビジネスチャンスの創出にも貢献します。
ここでは、業務効率化と顧客体験の向上をさらに加速させるチャットボットの最新トレンドをご紹介します。
●パーソナライズを実現するハイブリッド型の進化本コラムでも紹介したハイブリッド型チャットボットは、現在も進化を続けており、ルールベースの正確性と生成AIの柔軟な対話能力を高度に融合させています。実際には、基本的な問い合わせにはルールベースで迅速かつ正確に回答し、より詳細な説明や個別具体的な相談に対しては、生成AIが顧客の過去の対話履歴や購買データを参照しながら、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた回答を生成します。このような活用により、顧客エンゲージメントの向上が期待されています。
●音声や画像も扱うマルチモーダル対応これからのチャットボットは、テキストだけのコミュニケーションに留まりません。スマートスピーカーの普及に伴い、音声での対話が可能なボイスボットのニーズが高まっています。また、顧客がスマートフォンのカメラで撮影した製品の画像を送ると、それに関連する情報やトラブルシューティングを提示するなど、テキスト、音声、画像を組み合わせた「マルチモーダル」な対話が新たなトレンドです。これにより、24時間対応のサポート窓口がさらに直感的で使いやすいものへと進化していくでしょう。

チャットボットの仕組みを知ることで、チャットボット導入時のサービス選定に役立てることができます。どのような種類のチャットボットを選ぶかによって、成果が変わってくるためです。
大切なのは、それぞれのチャットボットの仕組みや特徴を理解して自社に合ったチャットボットを選ぶことです。
例えば、次のような場合にはどのタイプが良いかの例をご紹介します。
1)できるだけ費用を抑えて、チャットボットをFAQのような役割にしたい
従来、電話やメールで受けていたよくある質問への回答をチャットボットに代替したいというケースです。いわゆるFAQのようにユーザーが気軽に自分の悩みを解決できるようにします。
この場合、比較的安価に幅広い質問に対応できるルールベース型の「辞書型」がおすすめです。辞書型はシナリオ型と比べてフリー入力のため、人間同士の会話感覚で質問ができます。また、幅広い質問に対応でき、即座に回答にたどり着くのもメリットです。さらに、管理者にとっても、Q&Aの一覧のみ準備すれば良いので、手間と時間がかからず、AI型と比べて費用対効果が出やすいメリットもあります。
2)人間に近い会話でユーザーを楽しませたい
ユーザーとキャラクターを対話させることで、ユーザーを楽しませるというエンターテインメント性を主目的としてチャットボットの導入を考える場合、「AI型」が向いているでしょう。ある程度、コストをかける大々的なキャンペーンであったりすればなおさら良いかもしれません。
AI型は、対話ログを機械学習するため、切り返しなどが人間に近く、学習した分だけ会話の幅が広がるため、キャラクターとして愛着が出てきます。コストや時間がかかりますが、精度が高められれば導入効果を出すことができるでしょう。
あくまでこれは例であり、同じ目的や課題を持っていても、最適なチャットボットのタイプは変わってくることがありますので、自社の要件や目的を明確にして、チャットボットの仕組みや特徴とマッチするものを選びましょう。
チャットボットの導入事例19選!業界別の事例や導入手順・費用も解説
リコーのチャットボットサービス「RICOH Chatbot Service」は、ルールベース型の、シナリオ型と辞書型を兼ね備えたハイブリッド型のチャットボットで、ユーザーにとって使い勝手の良いレスポンスで満足度を高められます。リコーの独自調査の結果、利用者の約70%が回答に満足したと評価しています。
また導入が簡単である手軽さも特長です。自動で作られるタグをコピー&ペーストするだけでWebサイトに設置できます。シナリオ設定は事前に設定されており、FAQデータを読み込むだけで、すぐに開始できます。業種別のQ&Aパッケージのご用意もあるため、自社事業やサービスに合わせたチャットボットを簡単に作ることが可能です。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
RICOH Chatbot Serviceの紹介資料はこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。
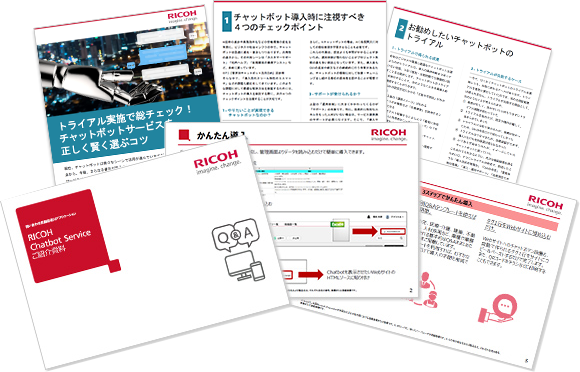
以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!