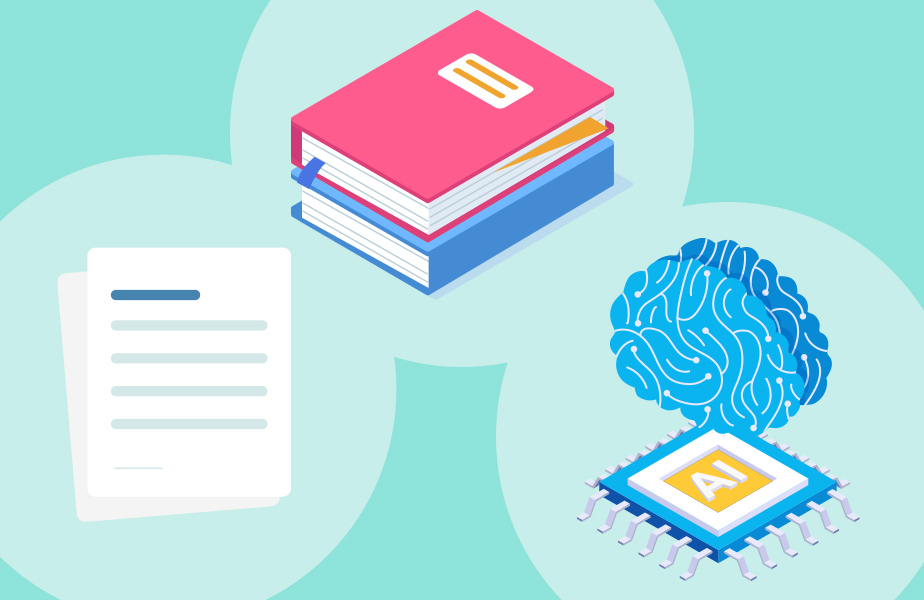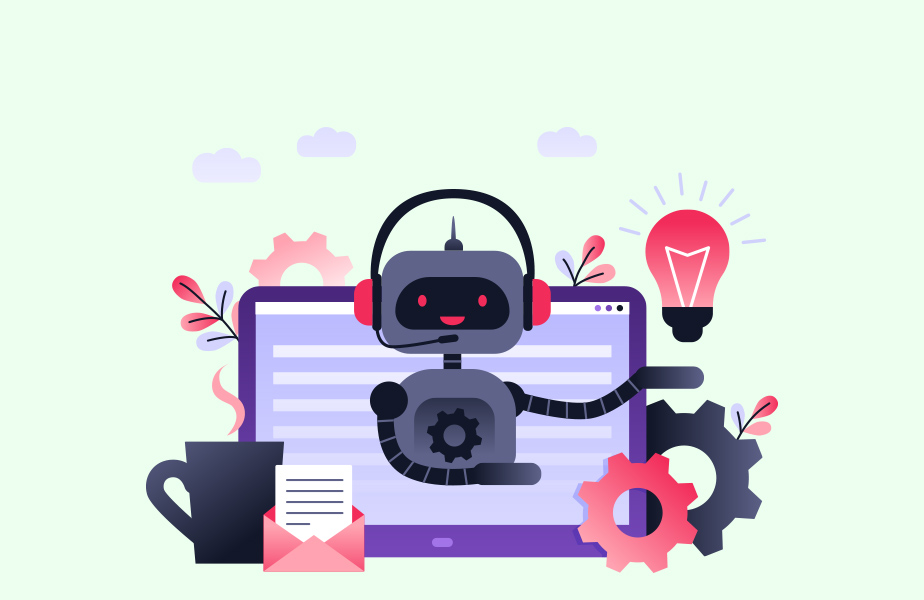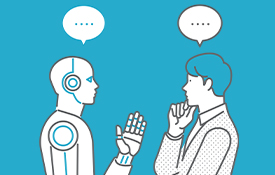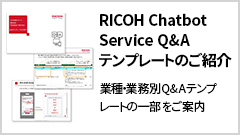テレワークのコミュニケーション課題を解決する最適なツールとは

コロナ禍によってテレワーク化が進みましたが、課題はまだまだ多くあります。新しい制度を構築しなければならないルール面の課題や、利用するツール、「集中できない」などの環境面の課題もあります。こうした中でも、特にコミュニケーション課題を解決することが最重要と考えられます。
今回は、テレワーク環境の整備のポイントやコミュニケーション課題を解決する方法を、業務の生産性向上も期待できる「チャット」に焦点を当ててご紹介します。
現在、進められているテレワークをはじめとした新しい働き方を実現するためには、「ルール・ツール・プレイス」の3つの整備を行うことが重要になります。
●ルールルールとは、テレワークそのものの制度や業務上におけるルールのほか、評価や成果に関する考え方はどうするか、勤怠・時間管理の具体的な方法など、新しい働き方で求められるさまざまな取り決めのことです。まずは何よりも先に必要なものです。初めからきっちりルールを厳格に定めてそれを守るというよりも、実際に実施してみて、よかったら継続する、よくなかったらやめるなど、トライ&エラーで修正してルールを作っていくというケースが多いようです。
●ツールツールとは、業務が従来と同じようにできるよう、高品質なビジネスコミュニケーションが可能で、安全に業務システムや必要な情報にアクセスできる環境に必要なツールのことを指します。クラウドツールを利用することで、ツールにおいてもトライ&エラーが可能です。
●プレイスプレイスとは、オフィスやサテライトオフィスなどの企業側が整えるべき環境のことです。インターネットや電源があり、安心して仕事ができる環境、会って話せる場所など、業務に合わせて従業員が選択できるようなプレイスの整備が求められています。

ルール、ツール、プレイスの整備の中で、特に重要になってくるのが「コミュニケーション」課題をいかに解決するかというところです。
内閣府のアンケート調査結果(※)によると、テレワークのデメリットとして「社内での気軽な相談・報告が困難」(38.4%)、「取引先等とのやりとりが困難」(31.6%)、「画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレス」(28.2%)がトップ3となっており、どれもコミュニケーションに関する課題です。
このことから、コミュニケーション課題を直接解決するツールが最も重要になってくると考えられます。
※出典:内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)
「第2回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」2020年12月24日
テレワークの最も大きな課題は「コミュニケーション」だとご紹介しました。以下ではより具体的な例を用いてどのような課題が生じているのか解説します。
業務の連携ミスや認識の齟齬
オフィスにいれば「少しよろしいですか?」と気軽にできた確認相談の機会が、テレワークでは減少します。相手の状況が見えないため、「忙しいかもしれない」と遠慮してしまい、結果的に自己判断で業務を進めてしまうケースは少なくありません。テキストベースでのやり取りでは、細やかなニュアンスや温度感が伝わりにくく、指示の意図を誤って解釈してしまうこともあります。こうした小さな認識のずれが積み重なり、後になって大きな手戻りや連携ミスにつながるなど業務効率の低下を招いてしまいます。
上司・部下間の信頼関係の希薄化
テレワーク環境では、上司が部下の働きぶりを直接見ることができません。そのため、業務の進捗状況が把握しにくく、適切な評価やサポートが難しくなるという課題があります。一方、部下側も自分の頑張りが上司に伝わっているのか不安に感じたり、キャリアに関する相談の機会が減ったりすることで、会社への帰属意識や仕事に対するモチベーションが低下しがちです。定期的な面談などの工夫がなければ、信頼関係が希薄になり、チームとしての一体感が失われる恐れがあります。
偶発的な会話から生まれるアイデアの喪失
オフィスでの何気ない雑談や、休憩中の会話から新しいアイデアや問題解決のヒントが生まれることは珍しくありません。このような偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)の機会がテレワークでは激減します。目的が明確なWeb会議やチャットだけでは、こうした創造的な会話は生まれにくく、組織全体のイノベーションが停滞する原因にもなり得ます。

ツールによってコミュニケーション課題を解決するために、特にビジネスチャットやチャットボットが多くの企業で導入されています。テレワークでは、どのように活用されているのか確認していきましょう。
●ビジネスチャットビジネスチャットは、社員同士の気軽なコミュニケーションを実現します。オフィス勤務だったときに隣の席にいる社員との雑談や、社内を移動中にふと対面した社員と始まる気軽なコミュニケーション等の代替として使われているケースが多いといわれます。このことから、テレワークの最大のデメリットを克服するのが、ビジネスチャットといえます。
●チャットボットチャットボットとは、「チャット(対話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、人が行っていた回答作業をシステムやAI(人工知能)が自動的に行うプログラムのことです。
チャットボットがテレワークで活用されている背景は、新しく導入されたルールやツールについて、気軽に正確な情報を取得できるところにあるといわれます。
従来のオフィスでは、知るべき制度やITツールについて不明点が出たら、近くの人に聞いたり、担当部門に内線電話で問い合わせたりと気軽に人に聞くことができましたが、テレワークではそれができません。自分で情報を探そうとしても情報が散在しており、情報を探すのに時間がかかるなどの問題もあります。
また、問い合わせを受ける側も、テレワーク関連の制度やツールが増え、問い合わせ対応業務の負担が増えたというケースもあります。
これらのことから、余計な情報探索・問い合わせ業務が増え、業務生産性の低下を招いてしまいました。こうした課題をチャットボットが解決します。ふとした疑問を人に聞くのではなく、チャットボットに質問し、問い合わせることで、自分で探すよりも効率的に情報を取得することが可能になります。
これらのことから、新しい環境下では、「チャット」がスタンダードなツールになっていくでしょう。
チャットボット(Chatbot)とは?│初心者にもわかりやすく解説

テレワークにおけるコミュニケーション不足は、少しの工夫で改善できます。ツールを導入するだけでなく、社員一人ひとりの意識やチームとしてのルール作りが、円滑なコミュニケーションの鍵を握ります。
テキストコミュニケーションの表現を豊かにする工夫
文字だけのコミュニケーションでは、感情が伝わりにくく、冷たい印象を相手に与えてしまうことがあります。これを防ぐ工夫として、感謝やねぎらいの言葉を意識的に文章に加えることが有効です。例えば、「承知しました」だけでなく「迅速なご対応ありがとうございます!」と一言添えるだけで、会話の雰囲気が格段に良くなります。また、絵文字やリアクション機能を使用することもポジティブな関係構築につながります。会社として推奨する使い方を共有するのもいいでしょう。
「状況の見える化」で連携をスムーズに
相手がどのような状況にあるか分からないことは、テレワークにおけるコミュニケーションの大きな障壁です。スケジュール共有ツールやチャットのステータス機能を活用し、自身の状況をこまめに共有する工夫をしましょう。こういった「見える化」は不要な待ち時間や心理的な遠慮を減らすことができるため、チーム全体の業務効率向上に大きなメリットをもたらします。
意図的に雑談の機会を設ける工夫
業務に必要な会話だけでなく、雑談やインフォーマルなコミュニケーションの機会を意図的につくることも重要な工夫です。例えば、チームの定例会議の冒頭5分を雑談タイムにしたり、チャットツール上で「雑談チャンネル」を作成したりする方法があります。上司が率先してプライベートな話題を振るなど、気軽に会話できる雰囲気作りも大切です。

チャットボットは、テレワーク等の新しい働き方において、ただコミュニケーション課題を解決するだけでなく、業務生産性の向上も期待できます。
実は、社内からの問い合わせの50%ほどは「よくある質問」といわれています。そのため、よくある質問だけをチャットボット化すれば、問い合わせ対応の半分は削減できるということです。これにより、業務生産性は向上するといえます。具体的には、コア業務のスピードアップと非コア業務の削減につながります。
各社員は知りたい情報をチャットボットによりスピーディに入手できるようになるため、各自のコア業務に集中できます。
●非コア業務の削減チャットボットにより、問い合わせる側は余計な情報探索作業が減りますし、問い合わせを受ける側は、問い合わせ対応が減ります。非コア業務については削減が可能です。
これらのことから、チャットボットは新しい働き方において、生産性向上にも寄与する有効なツールといえます。
個人・企業で取り組める業務効率化のアイデア【16選】役立つツールも紹介
近年進化が著しいAIチャットボットは、社内コミュニケーションの効率化において大きなメリットをもたらしています。
定型的な問い合わせ対応からの解放
テレワーク環境では、総務や人事、情報システム部門への定型的な問い合わせが各所から寄せられ、担当部署の業務を圧迫しがちです。AIチャットボットを導入すれば、従業員からのよくある質問に24時間365日自動で応答できます。これにより、問い合わせる側は上司や担当者の状況を気にすることなく即座に自己解決でき、対応する側は本来注力すべきコア業務に集中できるという、双方にとって大きなメリットが生まれます。
ナレッジ共有の促進と業務の属人化防止
「あの件はAさんにしか分からない」といった業務の属人化は、テレワークにおいて連携を阻害する大きな要因です。AIチャットボットは、社内に散在するマニュアルやノウハウ、過去のQ&Aといった知識を集約し、一元的なナレッジベースとして機能します。必要な情報を誰でも簡単に見つけられる環境を整備することで、情報格差をなくし、特定の社員への依存から脱却できます。会社全体の知識レベルを底上げし、円滑な情報共有を実現します。
能動的なサポートによる生産性とモチベーションの向上
今後のAIチャットボットは、単に質問を待つだけでなく、個々の従業員の状況や役割に応じて、必要な情報を先回りして提供するような、より能動的なパートナーへと進化していくでしょう。例えば、新入社員に対しては入社手続きをナビゲートし、営業担当者には関連資料を自動で提示するなど、個人の生産性を高めるサポートが期待されます。こうした支援は、テレワークにおける孤独感の軽減や、仕事へのモチベーション向上にも寄与する可能性を秘めています。

テレワークをはじめとした新しい働き方は、企業に大きな変化をもたらしました。制度や場所ほか、ツール選びまで、より有効な選択が迫られています。自社にとって最適なルール、ツール、プレイスを整備し、社員にとって満足度の高い環境を整えていくことが重要です。その中でも、ツールにおいてはコミュニケーション課題を解決するビジネスチャットやチャットボットが有効であり、生産性を高める効果も期待できるでしょう。
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。
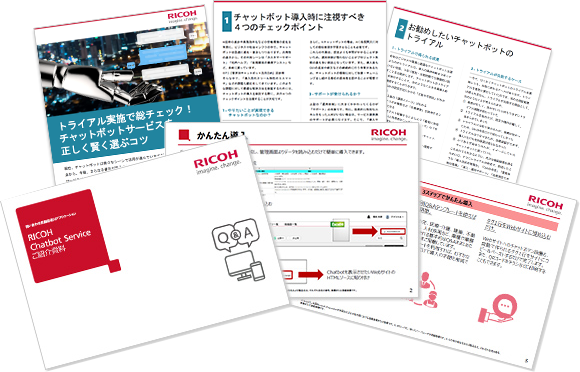
以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!