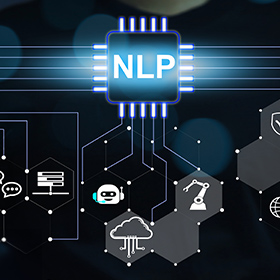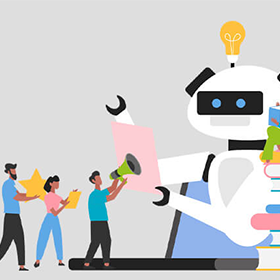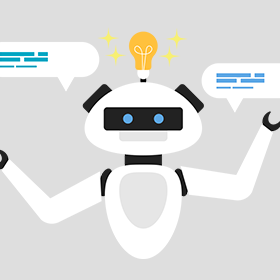仕事のAI
スペシャルサイト
クラスタリングとは?手法や活用事例から、メリット・デメリットまでをご紹介
近年、データの増加とともに、情報を効果的に活用する能力が企業の競争力を左右するようになっています。特に、膨大なデータの中から有用な情報を抽出することが求められる中、多くの企業が直面する課題は、どのようにしてデータを適切に分類し、業務やサービスに活かすかという点です。そこで、クラスタリングは、データを自然なグループに分けることで、パターンやトレンドを見つけ出す効果的な解決策となります。
本コラムでは、クラスタリングの基本概念から具体的な手法、そして実際の活用事例までをわかりやすく解説します。

1.クラスタリングとは?
クラスタリングは機械学習の一つであり、「データ間の類似度に基づいてグループ分けしていく手法」を指します。具体的には、膨大なデータセットを分析し、類似した特徴を持つデータポイントをグループ化することで、データの潜在的な構造を明らかにします。この手法は、マーケティング、医療、金融など、さまざまな業界で活用されています。
クラスタリングと分類の違い
クラスタリングと分類は、データ分析において混同されがちな概念ですが、異なる目的と方法を持っています。分類は、あらかじめ学習されたカテゴリーにデータを割り当てる手法であり、ラベル付きデータを用いてモデルを訓練します。一方、クラスタリングはラベルのないデータを扱い、データの特徴を見つけることでグループを分けていきます。
つまり、分類は学習したデータを使用するのに対し、クラスタリングはデータから特徴を学習していく手法になります。
クラスタリングの種類
クラスタリングにはいくつかの手法があり、目的やデータの特性に応じて適切な手法を選択することが重要です。主なクラスタリング手法には、階層的クラスタリングと非階層的クラスタリングがあります。
・階層的クラスタリング
階層的クラスタリングは、似ているデータをグループ化する手法です。クラスタ数を自由にすることができ、データの傾向が把握できない場合でも分析することができます。
また、分析結果が、デンドログラム(樹形図)で表現されるため、視覚的にも理解がしやすいのが特徴です。ただ、大量データを分析するには適しておりません。
・非階層的クラスタリング
非階層的クラスタリングの代表的な手法として、K-meansクラスタリングがあります。これは、データをあらかじめ決めた数のクラスタに分割する手法です。K-meansは、各クラスタの中心を反復的に調整しながら、データポイントを最も近いクラスタに割り当てます。この手法は、大量のデータを迅速に処理するのに適していますが、階層的クラスタリングとは違ってクラスタ数を事前に設定する必要があります。

2.クラスタリングのメリット
クラスタリングの概要や分類・種類についてはお分かりいただけたかと思いますが、実際にクラスタリングを導入するメリットとしては、どのような点が挙げられるのでしょうか。
ここではクラスタリングのメリットについて詳しくご紹介していきます。
ラベル付けコストが不要
クラスタリングは教師なし学習であるため、大量のデータに正解ラベルを付与する工程が不要です。ラベル作成にかかる時間や人件費を大幅に削減でき、ラベル化が難しいログデータやバイオデータでも迅速に分析を始められる点が大きな魅力です。
隠れたパターン・自然なグループ構造の発見
データ間の類似性にもとづいてグルーピングを行うため、従来のカテゴリ分けでは見落とされがちな潜在クラスや未知のパターンを発見できます。こうして得られたクラスタは、新たな仮説を生み出しドメイン理解を深める起点となります。
データの要約・可視化
大規模データを少数の代表点で表現し、t-SNE や UMAP と組み合わせて 2D/3D で可視化すると、複雑な構造を直感的に把握できます。これにより意思決定者は全体像を短時間で理解でき、ストレージや通信コストの削減にもつながります。
パーソナライゼーション/セグメンテーションへの直結
クラスタリングで抽出した顧客・ユーザグループをターゲットに設定するだけで、広告配信やレコメンドの精度が向上します。医療、金融、製造などでも、類似プロファイル別に処置や商品を最適化でき、高度なパーソナライズを少ない労力で実現できます。
異常検知・ノイズ除去
主要クラスタから大きく外れるデータ点を異常として扱うことで、不正利用検知や設備故障予兆検出を簡潔に行えます。また、ノイズを除去してから教師あり学習モデルを構築すると、学習データの質が向上し、モデルの安定性と精度が高まります。
以上のように、クラスタリングはラベルコストの削減から未知パターンの発見、可視化、パーソナライゼーション、異常検知まで多方面で大きな価値を提供します。探索的分析の第一歩として導入するだけでもクラスタリングのメリットは大きく、得られた知見を他の機械学習手法やビジネス施策と組み合わせることで、データ活用の幅と深さを飛躍的に広げることができます。

3.クラスタリングのデメリット
クラスタリングのメリットもある一方で、デメリットも存在します。
続いて、クラスタリングのデメリットについて説明をしたいと思います。
評価指標とクラスタ数の決定が難しい
教師なし学習で正解ラベルがないため、クラスタリングの「良し悪し」を客観的に測ることが容易ではありません。シルエット係数やエルボー法といった統計指標はあくまで参考値であり、指標間で推奨されるクラスタ数が食い違うことも多々あります。最終的にはドメイン知識や可視化結果をもとに人手で判断する必要があるため、手戻りや主観の混入を避けにくい点が大きな課題です。
距離関数・前処理・高次元性への強い依存
多くのアルゴリズムはユークリッド距離などあらかじめ定義した距離尺度に依存し、特徴量のスケールが合わないだけで結果が大きく変わります。カテゴリ変数の数値化手法や外れ値の扱いも成果を左右し、前処理の手間が増大します。さらに次元が増えると距離が一様化する「高次元の呪い」によりクラスタリングが機能しづらくなり、大規模データでは計算コストも急増します。
クラスタの意味づけとビジネス活用のギャップ
数値的に近いデータ点をまとめただけでは、そのクラスタが人間にとって直感的に理解しやすいとは限りません。各クラスタに対して「どの特徴が顕著か」「どう施策に落とし込むか」を追加で分析しなければ、実務的に活用できない“きれいな絵”で終わってしまいます。結局は専門家がクラスタごとにラベルや説明を付与する必要があり、この作業が“ラベル付け不要”というメリットを部分的に打ち消すケースもあります。
以上のように、クラスタリングはラベルなしで柔軟にパターン抽出ができる一方で、評価・前処理・解釈の各工程で専門知識と追加コストが発生します。導入時には「評価基準をどう設計するか」「前処理と距離尺度をどう選ぶか」「得られたクラスタをどう意思決定につなげるか」をあらかじめ明確にし、必要に応じて半教師あり学習や説明モデルを組み合わせて弱点を補完することが重要です。

4.クラスタリングの注意点
評価指標とクラスタ数の決定
- シルエット係数・Calinski-Harabasz・Davies–Bouldin など、複数の指標を併用し、ひとつの数値だけに依存しないようにします。
- クラスタ数を変化させたときの “安定性” を、サブサンプリングやブートストラップで検証します。
- 事前に「施策に落とし込める粒度」についてビジネス側と合意し、その範囲で最適なクラスタ数を探ります。
距離関数・前処理・高次元性への依存
- 特徴量は標準化、ロバストスケーリング、カテゴリ変数の適切なエンコーディングを徹底します。
- データの特性に合わせて、ユークリッド距離以外にもコサイン類似度、マハラノビス距離、学習済み埋め込み空間などの距離尺度を検討します。
- PCA・UMAP・t-SNE などで次元を縮約し、高次元の呪いと計算コストを同時に緩和します。
クラスタの意味づけとビジネス活用
- 各クラスタの平均値・頻度や決定木によるルール抽出を用いて “特徴変数トップ5” を明示し、解釈性を確保します。
- 施策担当者とのワークショップでクラスタをレビューし、具体的なアクション(ターゲティング、アラート閾値など)を早期に合意します。
- 必要に応じて半教師あり学習や追加ラベリングを行い、クラスタを継続的に改善します。
これらの注意点を事前に計画し実行することで、クラスタリングのデメリットを最小化し、得られたグループを実務に活かしやすくなります。

5.クラスタリングの手法一覧
続いて、クラスタリングの手法について解説します。
階層的クラスタリング
以下にて、代表的な階層的クラスタリング手法を紹介します。
1.群平均法
群平均法は、クラスタ間の距離を求める際に、2つのクラスタを構成するすべてのデータ点の組み合わせの距離を計算し、その平均をクラスタ間の距離とする手法です。この手法は、クラスタの形状に対する柔軟性が高く、ノイズに対しても比較的頑健です。
2.ウォード法
ウォード法は、クラスタ内のデータ点間の平方和を最小化することを目的とした手法です。具体的には、各データ点とクラスタの平均値との差の二乗和を求め、平方和が最も小さくなるようにクラスタを結合していきます。この手法は、均一なサイズのクラスタを生成する傾向があり、クラスタの分散を最小化するため、統計的に安定した結果を得ることができます。
3.最短距離法
最短距離法は、2つのクラスタ間で最も近いデータ点同士の距離をクラスタ間の距離として採用する手法です。この手法は、クラスタがデータの密集した部分を形成するように設計されています。しかし、ノイズや外れ値に敏感であるため、データの前処理が重要です。
4.最長距離法
最長距離法は、クラスタを構成する要素同士のすべての距離の中で最長のものをクラスタ間の距離として採用する手法です。この手法は、クラスタが互いに離れていることを保証するため、クラスタ間の分離を強調します。結果として、クラスタは比較的均一なサイズで生成されることが多いです。
非階層クラスタリング
続いて、代表的な非階層クラスタリング手法を紹介します。
1.k-means法(k平均法)
k-means法は、データをk個のクラスタに分割する手法で、各クラスタの中心を反復的に計算して更新することで、適切なクラスタリングをします。この手法は、計算が高速であり、特に大規模なデータセットに対して有効です。しかし、初期値の選択やクラスタ数の設定に依存するため、結果が不安定になることがあります。
2.混合正規分布
混合正規分布は、データを複数の正規分布の組み合わせとしてモデル化する手法です。この方法は、ソフトクラスタリングと呼ばれ、データポイントが複数のクラスタに属する確率を計算します。混合正規分布の代表的な推定アルゴリズムであるEMアルゴリズムは、データが持つ潜在的な構造を効果的に捉えることができます。
k-means法と混合正規分布の関係
k-means法は、各データ点を一意のクラスタに割り当てる「ハード」なクラスタリング手法であるのに対し、混合正規分布はデータ点が複数のクラスタに属する可能性を考慮する「ソフト」なクラスタリング手法です。しかし、混合正規分布の代表的な推定アルゴリズムであるEMアルゴリズムとk-meansのアルゴリズムは、ある理論的な設定の下では一致することが知られており、本質的には近しい手法とされています。

6.クラスタリングの活用事例
最後に、クラスタリングの活用事例について解説いたします。
食品業界 購買ビッグデータを基にクラスタリングAIを活用
食品業界では、電子レシートから得られる購買データを用いて、食品の市場分析を実施しています。
購買ビッグデータを基にクラスタリングAIを活用することで、消費者の購買特性や似た食品が集まったクラスタを自動で抽出することに成功しています。
クラスタリング活用した小売企業向け分析サービス
クラスタリング技術は、小売企業において顧客の購買パターンを分析し、ターゲットマーケティングを強化するために活用されています。例えば、特定の購買傾向を持つ顧客群を識別し、個別のプロモーションを展開することで、売上向上を図ることが可能です。このような分析サービスは、顧客理解を深め、競争力を高める手段として注目されています。
医療業界 クラスタリングとAI予測分析ツールを用いて天候と頭痛の関係を調査
クラスタリングとAI予測分析ツールを用いて、天候と頭痛の関係が調べられています。膨大な気象データと患者の気圧の変化による体調不良が危惧される時間帯の確認、及び頭痛を記録したデータをクラスタリングすることで、頭痛の発生には気圧の変化と降雨、湿度が関与することが示唆されています。

7.まとめ
本コラムでは、クラスタリングについて詳しく解説してきました。
機械学習を活用したいと考える皆様にとって、クラスタリングはその第一歩として非常に有効な技術です。ぜひクラスタリングを業務やサービス開発に取り入れ、データドリブンなアプローチを実現してください。
また、AIの導入の際には、ぜひ長期的な戦略と持続可能な運用を見据えたデータ作成基盤の構築など、万全な体制を整えた上で実施することをおすすめします。
リコーはAI関連サービスのご提供を通じて、貴社のお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。