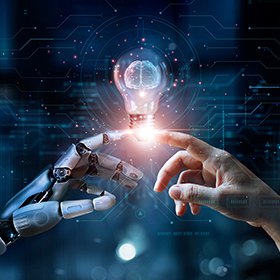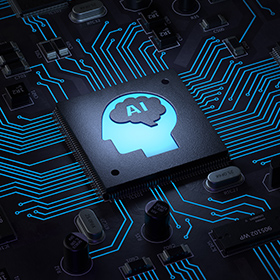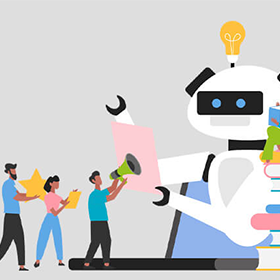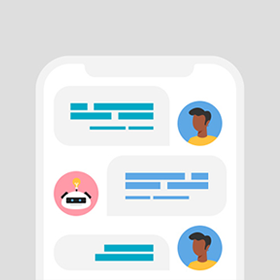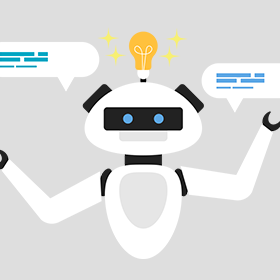AIチャットボットの自治体での活用方法とは?
近年、自治体では、AIチャットボットの活用が進んでいます。多くの自治体は、現在、業務効率化やDX、地方創生、外国人対応などのさまざまな課題に取り組んでいます。そうした中、AIチャットボットは一つの有意義な活用の可能性があることから、注目されています。今回は、AIチャットボットの自治体での活用方法やメリット、導入事例をご紹介します。
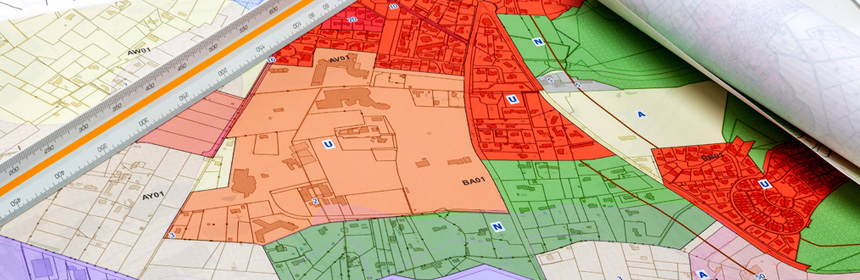
AIチャットボットとは
AIチャットボットとは、人工知能(AI)を利用して人間との対話を行うプログラムやシステムのことを指します。これらのチャットボットは、自然言語処理(NLP)を用いてユーザーの入力を理解し、適切な応答を生成することができます。データやログが不十分な場合、返答の精度が低くなることには注意が必要です。
しかし、データやログが蓄積されるにつれて、人間と話しているかのような自然な対話に近くなっていきます。例えば、形式ばった受け答えだけでなく、簡単な雑談も可能になります。
AIチャットボットは、カスタマーサポート、オンラインショッピングのアシスタント、予約システム、情報提供など、さまざまな分野で利用されており、今後も技術の進化に伴い、さらに高度で便利なツールとしての活躍が期待されています。

AIチャットボットの自治体での活用方法
自治体では、AIチャットボットは、どのように活用されているのでしょうか。その活用方法の例をご紹介します。
住民からの問い合わせへの対応
日々、寄せられる住民からの問い合わせ対応は、時期によって、もしくは緊急時などには特に増えることがあります。そのようなときに、住民からの問い合わせ対応をAIチャットボットで受け付ける方法です。簡単で、定型文で回答が返せるようなよくある質問においては、問い合わせ対応そのものを自動化できます。
外国人対応
住民の中でも、外国人からの対応では、多国語対応が求められます。問い合わせがあったときに、該当する言語を選択してもらい、その言語でFAQを提供することも行われています。
自治体内のヘルプデスク
自治体職員からの問い合わせを受け付けるヘルプデスクにも活用されています。多くの自治体には人手不足や働き方改革の課題がある中、問い合わせ対応はできるだけ効率化したいものです。住民からの問い合わせ対応と同様に、すべての問い合わせをAIチャットボットが担えるわけではありませんが、一部の対応は可能です。
観光・文化情報等の総合窓口コンシェルジュ
観光や文化情報については、その地域を訪れる観光客などからの問い合わせ対応を行う必要があります。問い合わせ対応だけでなく、AIチャットボットのほうから地域の観光資源や伝統文化などの情報を提供するといった総合窓口のコンシェルジュ的な役割を担わせている自治体もあります。
自治体でのAIチャットボットの導入状況
近年、自治体のデジタル化推進の一環として、AIチャットボットの導入が注目されています。総務省が令和5年12月31日に公表したデータによれば、全国1,788団体のうち369団体がチャットボットを導入しており、その割合はまだ高いとはいえないものの、年々増加傾向にあることがわかります。
導入の背景には、住民からの問い合わせに対する迅速な対応が求められていることや、職員の人手不足と業務負荷軽減の必要性があります。問い合わせ内容の一次対応をチャットボットが担うことで、窓口の混雑を緩和し、限られた職員数で多様な行政サービスを提供しやすくなる点が大きなメリットです。
一方で、自治体においては高齢者の利用が多い現状を踏まえ、操作性の高いインターフェースや有人サポートとの連携など、ITリテラシー格差への配慮が不可欠です。
今後は、導入後の運用・改善体制を整え、住民の声を積極的に取り入れることで、チャットボットの機能をより洗練させ、サービスの質をさらに向上させる取り組みが進むと期待されます。また、複数の自治体が連携してノウハウを共有する事例も増え、導入コストの削減や機能強化につながる可能性が指摘されています。

自治体がAI型を導入するメリット
自治体がAI型を導入するメリットとして、主な4つをご紹介します。
24時間365日問い合わせ対応が可能になる
従来は、問い合わせに対応できるのは自治体の業務時間内に限られていましたが、AIチャットボットを導入すれば、簡易的な質問なら24時間365日対応することが可能になります。結果として、住民の利便性や満足度向上につながります。
職員の業務効率が上がる
問い合わせ対応の自動化に成功すれば、職員の業務効率が向上します。もちろん、AIチャットボットが対応しきれない部分は、職員が対応しますが、それでもよくある質問については対応が自動化されるので、職員はよりコアな業務に専念できます。
自動化により人手不足対策・人件費軽減が期待できる
どの自治体も人手不足が深刻になる中、課題解決のためのツールとしてAIチャットボットは有効です。人件費削減にもつながるでしょう。
AI技術のなかでも導入しやすい
自治体をはじめ、国内では今、AIやIoT(Inernet of Things)を活用したDXが推進されています。そのような中、AI技術を活用する観点からすれば、AIチャットボットは導入ハードルが低くなってきています。現在は、AIチャットボットが普及浸透しているため、コスト的にも導入しやすくなっています。
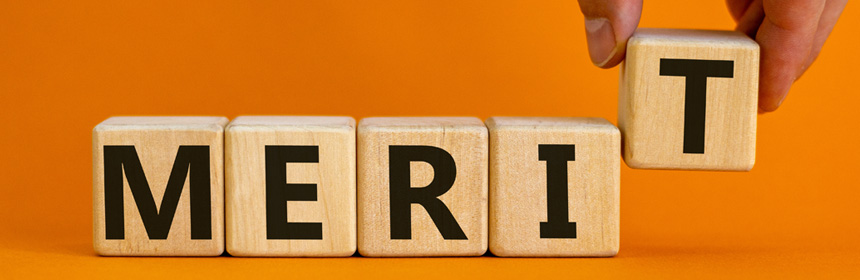
自治体のAIチャットボットの導入事例
自治体のAIチャットボットの導入事例を3つご紹介します。
緊急時の問い合わせ対応
ある自治体では、消費者からの消費生活に関する問い合わせに、一件一件、丁寧に回答する必要がある窓口があります。一時期、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、問い合わせ数が莫大に増え、対応しきれなくなってしまいました。そこでAIチャットボットを導入し、緊急時の問い合わせ対応のフォローを行いました。定形的な問い合わせはAIチャットボットが、前さばきの役割を担うことに成功しています。また消費者側も、24時間365日問い合わせができるようになり、必要な情報に素早くにたどりつきやすくなったため、利便性が向上しました。
防災情報の提供
ある自治体では、公式LINEアカウント上にAIチャットボットを導入し、住民に対して防災情報の提供を行っています。大型の台風が到来する予報を受け、住民からの問い合わせが増えることが予想されていたため、あらかじめ問い合わせ対応の幅を持たせる意味でAIチャットボットを導入しました。気象庁・国土交通省による気象警報注意報や、同自治体の避難場所の情報、ライフラインの情報へ簡単にアクセスできます。また、り災証明書や災害見舞金・補助金といった台風の被害にあった人に対しても、必要な情報をAIチャットボットで提供する仕組みも作りました。これにより、住民の不安を軽減し、問い合わせ対応の効率化を実現しました。
観光案内・PR
ある自治体は、公式LINE上に、地域にゆかりのある戦国武将に見立てたキャラクターをAIチャットボットとして設置しました。これにより、この地域に訪れようとしている観光目的の人が、観光情報を参照できるようにしました。戦国武将のキャラクターを用いることで、この地域の歴史にあわせた観光情報を発信したところに特性があります。
まとめ
ご紹介したように、自治体では、多様な用途でのAIチャットボットの導入が進んでいます。自治体が抱える課題解決に役立てられており、今後もさらに活用の可能性が広がっていくでしょう。
AIチャットボット選定の際には、ぜひリコーの「RICOH Chatbot Service」をご検討ください。
AI活用型チャットボットであり、リコー独自技術で磨き上げられた高性能AIが、類義語や同義語、表記のゆれを自動で理解します。そのため、精度の高いチャットボットの応答を実現します。
自治体への導入事例も多くありますので、ぜひ詳細をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。