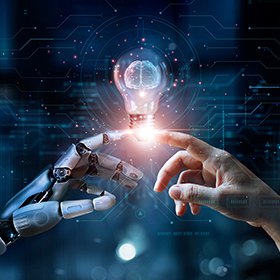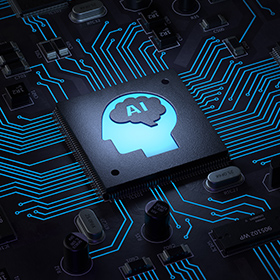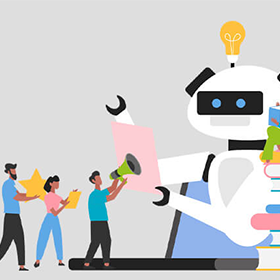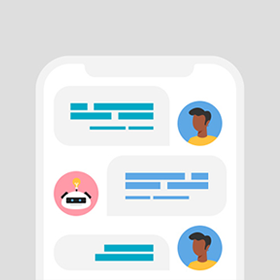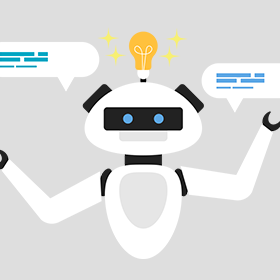エッジAIとは?メリットやデメリット、クラウドAIとの違いについて徹底解説!
近年はクラウドを通じて利便性高くサービス利用ができるようになりましたが、通信速度や通信コストの観点からは課題もあります。そうした課題を解決し、通信速度やコスト、セキュリティ面で優位なエッジコンピューティングが注目を集めています。
そしてAI(人工知能)を搭載することでさらに利便性高く利用ができるようになりました。今回は、エッジAIの定義やクラウドAIとの違い、メリットとデメリット、活用事例と採用時の注意点を解説します。

エッジAIとは?
エッジAIの定義と共に、クラウドAIとの違いを確認していきましょう。
エッジAIとは?
エッジAIとは、エッジコンピューティングとAI(人工知能)を組み合わせた技術です。エッジコンピューティングのエッジとは「端」を意味しており、端末(デバイス)の付近にサーバーを設置し、データ処理を行うことからそう呼ばれています。
一般的には、サーバーが別の場所にあり、デバイスで取得したデータがネットワークを通じてサーバーに送られ、データ処理が行われます。この一般的な方法と比べて「端」で処理するという意味から、エッジコンピューティングと呼ばれています。
AIは人工知能とも呼ばれる、人の知能を人工的に再現する技術であり、エッジコンピューティングのデータ処理に組み込むことでより精度を高めたのがエッジAIです。
クラウドAIとの違い
エッジAIとよく対比されるのが「クラウドAI」です。これはクラウドコンピューティングとAIを組み合わせた技術です。クラウドコンピューティングとは、物理的なサーバーではなく、インターネット上にあるサーバー上でさまざまなコンピューター機能を実現するものです。データ処理、ストレージ、データベース、アプリケーション配信などのほか、AIの利用も可能です。
このクラウドコンピューティングのデータ処理にAIを組み合わせて精度を高めた仕組みがクラウドAIです。
エッジAIと異なる点として大きいのは、データ処理の「場所」と「タイミング」の2点です。
エッジAIは端末付近のサーバーでデータ処理が行われる一方、クラウドAIは端末にインターネットを通じて接続されたクラウドサーバーでデータ処理が行われます。
また、エッジAIは端末付近のサーバーで処理が行われるため、端末におけるデータ収集とサーバーにおけるデータ処理がほぼ同時に実行できます。一方、クラウドAIはネットワーク通信を介するため、エッジAIと比較して、データ収集からデータ処理の間にタイムラグが発生します。

エッジAIのメリット・デメリット
エッジAIには、メリットもあれば、デメリットもあります。それぞれ確認していきましょう。
メリット
リアルタイム処理が可能
先述の通り、エッジAIはデータ収集とデータ処理をほぼ同時に行えるため、リアルタイムに近い処理を実現します。
そのため、例えば自動運転や産業分野など遅延が事故につながるような分野でのAI活用の際に採用されています。
また、データ処理の段階ではネットワークを介さないため、ネットワークの途切れる恐れもなく、安定的な稼働が期待できます。
通信量・通信料金の削減
エッジAIはデータ処理にネットワーク通信を必要としないことから、通信量や通信料金の削減につながります。
セキュリティ性向上
ネットワーク通信を介するコンピューティングと比べて、エッジAIは、端末付近で処理されることから、データセキュリティのリスクは低減されます。ネットワークを通じた情報漏洩や不正アクセスの恐れが少なくなります。その点からセキュリティを重視したい入退室管理などの分野では理想的なセキュリティを保てます。
またエッジAIはデータ加工後にネットワーク送信できるため、個人を特定できないよう加工したデータを共有することも可能です。
ネットワークがつながらない場所でもシステム構築が容易
エッジAIは小規模であり、ネットワークがつながらない場所でも実現できることから、システム構築が容易といえます。
デメリット
処理能力が限定的
エッジAIは、現場に設置する端末の付近におけるサーバーで処理することから、クラウドAIと比較して、CPUなどのサーバー性能が下がります。そのため、処理能力が劣ることから、大容量の処理は不向きといわれています。エッジAI技術は日進月歩で高まっていますが、現状は限定的な利用となります。
アップデート・管理コストの圧迫
エッジAIはシステム構築などの物理的な構築面では容易ですが、導入コストや、アップデートやメンテナンスなどの管理の手間やコストに負荷が大きいといわれています。クラウドAIと比較すれば、メンテナンスはクラウドサーバー提供側に任せられる一方で、エッジAIは自社が現場にある設備を自らメンテナンスする必要があります。エッジAI導入の際には、メンテナンスやコストに関する想定も十分に行っておくことが重要です。

エッジAIを支える技術要素
エッジAIの性能を理解するには、その実現を支えるハードウェア、特に「推論処理」に特化したプロセッサの存在が不可欠です。
処理能力の限界を打破するNPUの役割
エッジAIの大きな課題の一つは、クラウドAIと比較して「処理能力が限定的である」という点です。これは、従来のCPUやGPUといった汎用的なプロセッサでは、AIモデルが要求する大量の並列演算を、低消費電力かつリアルタイムに行うことが難しいためです。
この課題を克服するために開発されたのが、NPUやAIアクセラレーターと呼ばれる専用の半導体チップです。NPUは、AIの推論に必要な計算処理に特化して設計されています。この専用設計により、汎用プロセッサを用いる場合に比べて、劇的な低消費電力と高速な処理を実現します。
特に、AI処理に不可欠な並列演算において効率的であり、バッテリー駆動の小型デバイスでも、高度な画像認識や音声処理をクラウドに頼らずに行うことが可能になっています。
さまざまなエッジデバイスに最適化されたAIチップ
現在、NPUなどのAIアクセラレーターは、スマートフォン、監視カメラ、自動車のECU(電子制御ユニット)、産業用ロボットなど、さまざまなエッジデバイスに組み込まれています。
これらのAIチップの進化により、エッジAIは「データ収集と単純な推論」から、「複雑なAIモデルの実行と、現場でのリアルタイムな意思決定」へと、その適用範囲を広げています。これにより、エッジAIのデメリットとされていた「処理能力の限界」は、日進月歩で解消されつつあるといえます。技術的な進化が、エッジAIのさらなる普及を後押ししているのです。

エッジAIの活用事例
エッジAIの活用事例をご紹介します。
製造業 外観検査自動化
ある製造業では、製造後の製品の外観検査をエッジAIにより自動化しています。工場内では大量のデータが生成されるため、エッジで処理できるエッジAIに適しています。
外観検査においては、あらかじめ良品をカメラで撮影し、そのデータをAIに学習させることで、異常検知に役立てています。高い精度での異常検知を実現しています。
また導入時のネットワーク整備などのコスト削減にもメリットを感じています。
食品工場 入退室管理システム
ある食品製造業では、工場の入り口においてエッジAIを活用した入退室管理を採用しています。食品工場では衛生管理の徹底が求められ、誰がいつどの部屋に入ったかを正確に記録しなければなりません。しかし従来の顔認証やカメラでは、帽子やマスクなどをつけたままの状態では判別がむずかしい状況でした。
そこでエッジAI搭載のカメラを利用した入退室管理システムを採用しました。ユニフォームに色付きのタグをつけ、そのタグをエッジAIカメラが読み込み、自動で検出・処理することで、精度の高い入退室管理を実現しています。
介護施設 見守りカメラ
ある介護施設では、エッジAI技術を用いた入居者の見守りカメラを導入しています。従来からモニタリング用カメラは導入していましたが、解像度が低かったため、介護の業務には役立っていませんでした。
エッジAI搭載見守りカメラは、解像度が高く動体検知機能を備えており、何かアクシデントがあった際に即座に異常を知らせてくれるため、即時対応も可能になりました。入居者の身の安全と共に、介護業務の効率化も実現しています。

エッジAI活用時の注意点
エッジAI活用時には、次の注意点を押さえることで、より有意義な活用につながるでしょう。
強固なセキュリティ対策が必要
エッジAIはもともとセキュリティ性に評価がある一方で、セキュリティホールを対策したり、定期的なアップデート対応を継続的に実施したりと常時セキュリティ対策が求められます。特に設置している端末数が多い場合はセキュリティリスクが高まるため注意が必要です。
運用コスト増・管理の煩雑化への対応体制
管理やメンテナンスなどの運用コストが増す点、管理が複雑化しがちな点などのデメリットに対応する体制作りが欠かせません。
ベンダーのサポートを受けるほか、クラウドAIとの併用などエッジAIのメリットを最大限活かしながら管理体制を整えましょう。
処理可能な量の限界を見極めた開発が必要
大量データ処理に不向きなエッジAIは、処理可能な量の限界を見極めること、そしてクラウドAIのすみわけをしっかりと行い、適材適所で採用するのが良いでしょう。前述のような自動運転、外観検査、入退室管理、監視カメラなどの最適な活用シーンの見極めも求められます。
ハードウェアとの適合性への留意が必要
開発に際して、AI技術を組み込む場合、実装するハードウェアがAIモデルに適していない場合があります。エッジコンピューティングとAIとの組み合わせについては、専門的な知識が求められるため、経験豊富な開発ベンダーに依頼することをおすすめします。

エッジAIの今後
エッジAIの進化は留まることを知らず、今後はさらに最先端の技術領域と融合することで、その真価を発揮し始めます。特に「生成AI」と「デジタルツイン」との連携は、今後のビジネスのあり方を大きく変える可能性を秘めています。
エッジにおける生成AI
近年、大規模言語モデル(LLM)などに代表される生成AIが注目を集めていますが、これをエッジデバイス上で動作させる技術開発が進んでいます。
通常、大規模なAIモデルは膨大な計算資源を必要とするためクラウド上での処理が基本ですが、モデルを軽量化しエッジデバイスに組み込むことで、ネットワーク接続の有無にかかわらず、現場で即座に、情報の要約、応答の生成、ドキュメント作成支援などが可能になります。
例えば、製造現場では、作業マニュアルをカメラで読み込み、現場の状況に合わせて即座に要点を要約・指示することができます。また、医療・介護の分野では、患者のバイタルデータや行動データに基づき、即座に異常の可能性を生成AIが分析・通知することも期待されます。
これは、エッジAIが持つ「リアルタイム性」と「セキュリティ性の高さ」というメリットを最大限に活かす、未来の活用方法といえるでしょう。
デジタルツインとのシナジー
デジタルツイン(現実空間のデータを収集し、コンピュータ上に「双子」のような仮想空間を構築する技術)の精度は、リアルタイムなデータ収集と処理にかかっています。
ここでエッジAIが重要な役割を担います。現場のエッジデバイスがセンサーやカメラから大量のデータを収集し、その場で前処理(ノイズ除去や重要な特徴抽出)を行うことで、クラウド側のデジタルツインモデルに送るデータ量を大幅に削減します。
これにより、データ転送量が減ることで仮想空間への反映がよりリアルタイムになり、同時にクラウドサーバー側の処理負担も軽減されます。結果として、大規模なデジタルツインの運用コストを抑えつつ、より正確でリアルタイムなシミュレーションを可能にします。
以上の様にエッジAIは、単なる監視・制御技術から、現実世界とデジタル世界のシームレスな統合を可能にする、基盤技術へと進化を遂げているのです。

まとめ
エッジAIは、クラウドAIと比較して、リアルタイム処理やネットワーク通信がむずかしい現場での処理も可能である画期的な技術です。一方で管理コストや処理性能などのデメリットもあることから、適材適所で選択していくことがポイントといえます。
リコーは多岐にわたるAI関連サービスのご提供が可能です。AI導入をご検討の際は、ぜひ、お気軽にご相談ください。