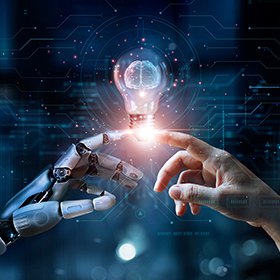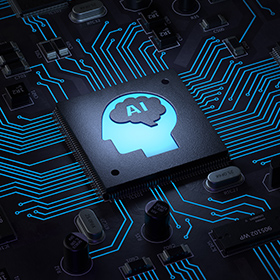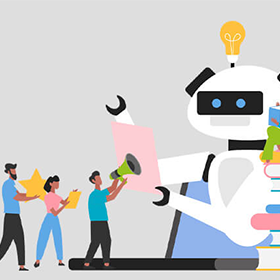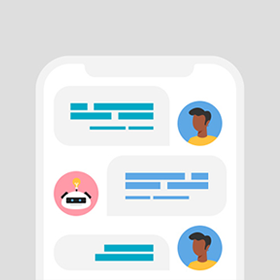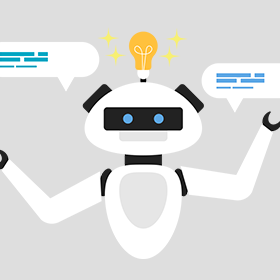AI導入でビジネスモデルを革新
~メリットと導入ステップをご紹介!
近年は日本企業においてAIの導入が進んでおり、従来のビジネスモデルが革新されつつあります。果たしてどのようなメリットが見込めるのでしょうか。また実際の導入メリットも気になるところです。
今回は、AIの日本企業への導入状況から活用用途、導入メリット、導入ステップ、AI導入時の課題と解決策までご紹介します。

AI導入状況と活用用途
日本企業においては、AIの導入はどの程度進んでいるのでしょうか。近年のトレンドから企業の活用用途まで解説します。
AI導入状況
近年、AIのうち、特に生成AIの導入が世界的に加速しています。生成AIとは、学習したデータをもとに新たにテキストや画像、動画などのコンテンツを生成する人工知能の一種です。
総務省の「情報通信白書 令和6年版(※)」で紹介されているデータによれば、世界各国の企業に向けて生成AIの活用方針が定まっているかどうかを尋ねた結果、日本で「活用する方針を定めている」と回答した企業の割合は42.7%でした。一見、割合が多いように見えますが、米国、ドイツ、中国では約8割以上であるため、それらと比較するとかなり低い数値です。今後の導入が期待されます。
※出典:総務省「情報通信白書 令和6年版」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151120.html
AIの主な活用用途
AIは、業務においてさまざまな用途で用いられています。主な活用用途をご紹介します。
【生成AI】
・メールや文書作成
・アイデア出し、シミュレーション
・広報コンテンツ生成
・プログラミングコード生成、バグ修正
・顧客対応の自動化
・社内向けヘルプデスク
・製品やサービスへの組み込み
生成AIについては、文章作成やアイデア出し、画像や動画作成、プログラミングコード作成といった生成分野のあらゆる用途で活用されています。
また生成AIはチャットボットの形態で利用することが多いため、チャットボットで顧客や従業員からの問い合わせに対応する活用も進んでいます。
自社製品やサービスに組み込み、付加価値として提供するケースも少なくありません。
【AI】
・情報収集、将来予測
・高度なディープラーニングによる分析・判断
・異常検知
従来のAIも活用が進んでおり、インターネット上の膨大な情報を収集したり、データをもとに分析して商品の売れ行きなどの将来予測を行ったりすることが可能です。
またAIの機械学習を発展させた高度なディープラーニングによる分析と判断は、顔認証や文字起こし、不正検知などに利用されています。また製造業の不良品検知などの異常検知の分野でも活用が進んでいます。

AI導入のメリット
AIを社内業務に導入するメリットをご紹介します。
業務効率化、生産性向上
AIは従来、人の手で行っていた業務の自動化を実現することから、業務の効率化につながります。コア業務へ専念できれば、全体の業務効率も向上するでしょう。
人手不足への対応、負荷軽減
AIによって人の作業を効率化することで、近年、多くの業界で深刻化する人手不足の課題を解決します。
また少ない人員によって業務負荷が高まっている場合の解決策となります。
顧客体験価値、満足度向上
生成AIチャットボットを顧客向けに提供することで、問い合わせ対応の効率化につながります。同時に、営業時間外の24時間の問い合わせが可能になるため、顧客の自己解決につながり顧客体験価値と満足度向上にもつながるでしょう。
膨大なデータ分析の実現
従来、人が長時間かけて行っていたデータ分析業務も、AIが代わりに担えば大幅な効率化につながります。またこれまで取得できなかった分析結果を得られるため、データに基づく意思決定を実現するデータドリブン経営も可能です。
新規ビジネス創出
ユーザーニーズを分析して商品開発に活かしたり、顧客に最適な提案を行い、付加価値を提供したりすることで、新規ビジネスの創出にもつながります。

AI導入ステップ
AIを社内に導入する際には、主に次のステップを踏むことで成功につながるでしょう。
1.現状課題分析と目的の明確化
AIを導入する際に注意が必要なのが、目的を定めずに導入してしまうことです。効果測定ができないため、成果が出たかどうか、費用対効果はどうなのかがわかりません。
まずは現状を洗い出し、解決策となるAIの導入を検討しましょう。AI導入の一般的な目的として「人手不足に対応するための業務効率化」「顧客満足度向上」「新規ビジネス創出」などが挙げられます。
2.AIが対応する業務のリストアップ、対応範囲の指定
AIをどの業務に導入するのか、まずは業務のリストアップを行いましょう。そしてAIがどこまで対応するのか、人との対応範囲の棲み分けを十分に検討することが大切です。
3.AIツール開発・選定
目的を達成し、課題解決につながるAIツールの開発もしくは選定を行いましょう。選定基準としては自社の環境に合っており、セキュリティ性も担保できるかどうかが最低限の基準となります。
4.学習データの準備
AIモデルに新たに機械学習をさせる場合には、学習データを用意しましょう。
5.AI活用ルールの策定
AIは特に生成AIの場合は、コンテンツを生成するため、そのコンテンツの利用ルールを定めることで、適正利用を促進します。正確でない回答や情報漏洩、著作権侵害などのリスクを回避する体制を整えましょう。
6.テスト導入
まずはPoC(概念実証)を行うなど、テスト的に小規模から導入します。
7.効果検証・改善
効果検証を行い、狙った効果が出ているか、また問題があれば改善します。これによりリスクを最小限にとどめながら最適化していくことができます。
8.本格導入
特定の部署などに本格導入し、効果検証を行います。改善を重ね、他部署にも転用できそうな段階で全社展開していきましょう。

AI導入時の課題と解決策
AI導入時には、次のような課題に直面することが多くあります。そこで解決策をご紹介します。
導入・運用コスト増加
AIは導入・構築、運用に専門人材が必要になったり、AI環境構築自体に多額のコストがかかることがあります。それゆえに中小企業は特に導入ハードルが高いでしょう。
解決策:
解決策としては、まずは小規模から始めて徐々に拡大していく、段階的導入を進めることがおすすめです。また効果検証を行い、改善を重ねながら、人的リソースや負荷削減などの効果を算出し、費用対効果を高めていくことで、コストを回収する考え方もあります。
データセキュリティ
特に生成AIは学習したデータをコンテンツとして生成するため、学習内容によっては機密情報や個人情報を含む恐れがあります。またユーザーが入力した内容を学習してしまう仕組みの場合は、よりリスクが高まります。
解決策:
解決策としては学習データに機密情報を含めないほか、入力データを学習しない仕組みを構築することが一つに考えられます。またネットワークにおけるデータ通信の暗号化も有効な対策です。
著作権などの法的リスク
生成AIは著作物を学習して生成するリスクがあるため、コンテンツをそのまま使うと著作権侵害につながるリスクがあります。
解決策:
解決策としては、著作権侵害につながるコンテンツでないか、人的チェック体制を整えることが先決です。また社内でAIガバナンス体制を構築し、リスクに備えることも一案です。
ハルシネーション
ハルシネーションとは、生成AIが正しくない情報をあたかも正しいかのように表現する現象です。改善の取り組みは進められていますが、起こり得るリスクとして真摯に対応しなければなりません。
解決策:
解決策としては、コンテンツ生成後の人的チェック体制を整えるほか、RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)の採用も一案です。RAGはAI技術の一種で、大規模言語モデル(LLM)と検索システムを組み合わせたものです。RAGは学習済みデータだけでなく外部データベースを検索して参照し、正しいかどうかを調べた上で回答を返すため、情報の信頼性が向上します。そのため、ハルシネーション対策の一つとして活用されています。
AI人材確保と育成
AI開発はもちろんのこと、導入や運用に際してもAIの専門人材が求められます。社内で採用や育成を行う必要があり、コストやリソースの懸念が生じることがあります。
解決策:
解決策として、専門家やパートナーによる支援を受けることが考えられます。開発、導入、運用と一連の流れを通じて伴走型の支援を行う事業者を選ぶことで、成果につながりやすくなります。

まとめ
日本企業におけるAI導入は、まさに今進行中のフェーズといえます。数ある課題をクリアしながら、AI導入を最適化しましょう。
リコーは多岐にわたるAI関連サービスのご提供が可能です。AI導入をご検討の際は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
開発、導入、運用において伴走型支援を行います。セキュリティに関するサポートも可能ですので、お気軽にご相談ください。