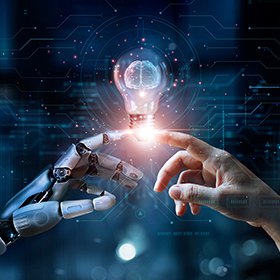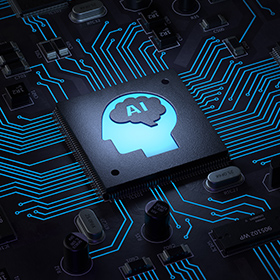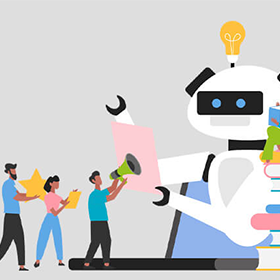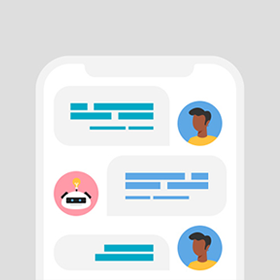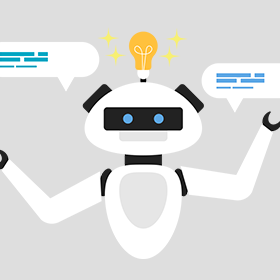AIを活用して効率化できる業務とは?活用例やAIとRPAの活用方法など詳しく解説
AIを活用して、業務効率化を試みる企業が増加しています。AIを活用すれば、人手不足を解消してくれるだけでなく、今までのデジタル化では難しかった高度な作業も可能です。ここでは、AIで効率化を図れる業務内容を、業界別に詳しく紹介します。AIとRPAの違いや、AIとRPAを組みあわせた事例も解説するため参考にしてください。
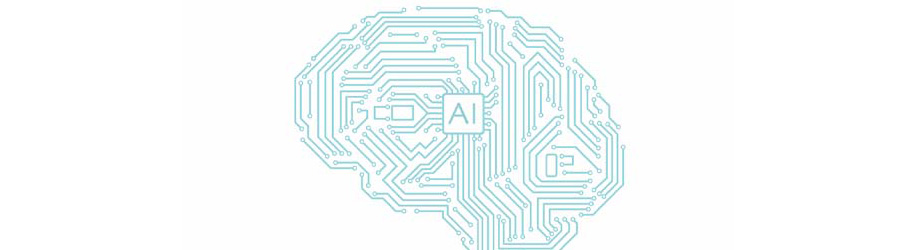
そもそもAIとは何か?
AIは「人工知能」と和訳されます。AIの強みは機械学習と深層学習の双方が可能なことです。
機械学習では、決められた条件に従ってモノを識別します。人間が識別の手掛かりになる特徴を教えることで、AIは機械学習に対応します。これらは、主に顔認証や異常検知などに活用されています。
一方、深層学習では、学習データをもとにAI自身が特徴を見出します。深層学習は、AI活用型チャットボットやAIスピーカーなどで使われています。
AIが業務効率化で必要とされる背景
業務におけるAIの必要性は、現代社会が直面する課題を背景に急速に高まっています。
労働人口の減少と生産性向上
日本を含む多くの国では、少子高齢化による労働人口の減少が深刻な問題となっています。従来の働き方では、将来の労働力不足を補うことが困難です。AIは、定型業務やデータ入力、問い合わせ対応といったタスクを自動化し、従業員がより創造的で価値の高い業務に集中できる環境を作ります。これにより、限られた人材で最大の成果を出す、生産性向上が実現します。
膨大なデータの活用
スマートフォンやIoTデバイスの普及により、企業は日々膨大な量のデータ(ビッグデータ)を蓄積しています。しかし、人間が手作業でこのすべてを分析し、活用することは現実的ではありません。AIは、これらのデータを高速かつ正確に分析し、市場トレンドの予測、顧客行動の理解、新たなビジネスチャンスの発見を可能にします。AIを活用することで、データドリブンな意思決定が加速し、競争優位性を確立することができます。
働き方の多様化とリモートワークの普及
パンデミックを経て、リモートワークや柔軟な働き方が定着しました。これにより、コミュニケーションや業務遂行の効率化が新たな課題となっています。AIチャットボットや自動化ツールは、従業員の問い合わせに24時間対応したり、業務プロセスを自動化したりすることで、場所や時間にとらわれないスムーズな働き方をサポートします。
これらの背景から、AIは単なる便利なツールではなく、企業が持続的に成長し、変化に対応するための不可欠なパートナーとなりつつあります。

AIとbotの違い
botとは、決められたタスクや処理を自動化するプログラムの総称です。ここでは、テキストや音声などでユーザーとコミュニケーションを取る「チャットボット(chatbot)」の略称として比較します。
botは自身で考えて応答しているように一見見えますが、自動化プログラムのため、AI特有の学習機能はありません。設定されたプログラムにしたがって行動するため、AIのように臨機応変な対応には不向きです。
AIとRPAについて
RPAも業務効率化に役立ちますが、AIと混同されがちです。RPAについて、AIとRPAを掛けあわせた事例も含めて紹介します。
RPAとは何か
RPA(Robotic Process Automation)とは、業務を効率化させるロボットシステムを意味します。総務省の定義によると、RPAは性能に応じて3つのクラスに分類できます。
クラス1は、定型業務を自動化する一般的なRPAです。クラス2はEPA(Enhanced Process Automation)と呼ばれ、AIの活用により一部の非定型業務も遂行可能なものです。クラス3はCA(Cognitive Automation)と呼ばれ、AIの深層学習を取り入れた高度な活動を実施します。ただし、クラス3のRPAは、2021年の時点であまり見られません。
※参考:総務省|情報通信統計データベース|RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)
AIとRPAの違い
AIは「機能」であり、RPAは「システム」です。AIは機能学習や深層学習を発動し、大量のデータを分析できます。人間よりもデータ処理能力に長け、高精度な分析が可能なAIですが、作業自体は人間やRPAが実行する必要があります。
AI搭載のRPAに期待が寄せられている
AIを搭載すると、RPAの作業スピードや精度は大いに向上します。RPAの機能が向上すると、より大きな業務の効率化が期待できます。
たとえば、AIを搭載したRPAのソフトウェアロボットを導入すると、リモートワークによる業務対応が可能です。オフィスにロボットを設置すると、従業員は自宅から作業状況を監督できます。AIでは判断できない点がある場合にも、ネットワークを使って自宅からロボットに指示を出せます。
AI×RPAの活用事例
地方自治体での導入事例
地方自治体には紙の書類が多く、業務効率化を阻んでいました。書類のデジタル化を目的に導入されたシステムが「AI-OCR」です。AI-OCRは、AIが文字を読み取り、デジタル化をRPAが実施する仕組みです。AI-OCRの活用により、申請書や調査票、アンケートなどをデジタル化でき、入力業務を削減できました。
ほかにも、地方自治体では、AIの音声認識による議事録作成や、AI活用型チャットボットによる問い合わせ対応などが実施されています。
金融機関での導入事例
銀行では、書類をもとに数多くのサービスを提供しています。しかし、公共料金の口座振替依頼用紙のような書類は非定型であり、情報の読み取りに時間がかかる点が問題視されていました。
地方自治体のように、多くの金融機関でもAI-OCRを活用しています。AIが定型・非定型を問わず書類から情報を読み取り、各システムへの入力や照会などの処理はRPAが担当します。AI-OCRの導入後には、窓口業務や事務作業が大幅に短縮され、残業時間を削減できるケースが増えています。
IT専門商社での導入事例
あるIT専門商社では、企業のデータを統括するERPの使い勝手が悪く、Excelを併用して業務をこなしていました。ほかのERPに変更しようにも、コストが懸念されます。
ERPの使用感を向上させるため、複数の部門で行う業務をAIによって自動化し、アプリケーションをRPAで操作させました。結果、部門間の連携がスムーズになり、業務効率化を達成できています。
人材サービス業での導入事例
人材サービスにかかわる企業では、社内の情報共有とコミュニケーションの円滑化が課題でした。人材サービスが取り扱う、応募者や企業の情報は膨大です。さらに、常に最新の情報を共有しなければ業務が滞ります。
社内システムへのログインをAIによって自動化したところ、簡単な問い合わせメールへの対応や、データ入力、レポート作成などをRPAに任せられるようになりました。社内の連携が強化され、コストの削減、業務効率化につながっています。

AIとbot/RPAの違いまとめ
AI・bot・RPAの違いを、以下にまとめました。
| 特徴 | |
|---|---|
| AI | ・機械学習や深層学習が可能 ・企業が保有する膨大なデータをスピーディーに分析して、botやRPAをサポートする |
| bot | ・人間の会話や行動を予想し、対話するようにプログラムされたツール ・botのみでは、プログラム以外の働きはできない |
| RPA | ・プログラムした内容に従い作業するツール ・単純なオフィス業務の自動化に向く |
AIを活用した業務効率化のメリット
AIを活用したシステムは、高度な業務をスピーディーにこなして、業務の属人化を防ぎます。また、体力や精神力に限界のある人間とは異なり、AIを活用したシステムは24時間365日安定して稼働します。人的ミスの心配もありません。
たとえば、コールセンターのシステムにAIを組みあわせると、AIがオペレーターに速やかに回答を提案します。このような仕組みを利用して問い合わせ一件あたりの接客時間が短縮されると、応答率の向上にもつながります。
業務効率化でAIを導入する時の課題と対策
業務効率化のためにAIを導入する際、企業はいくつかの課題に直面します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。
高額な導入費用と投資対効果の不確実性
多くの企業にとって、AI導入は初期費用と運用コストの面で大きな負担となることがあります。また、具体的な効果が見えにくく、投資に見合うリターンが得られるか不透明な場合もあります。
対策: 導入前に、どの業務にAIを適用するかを明確にし、具体的な目標(例:問い合わせ件数を20%削減する)を設定します。まずは無料のトライアルや安価なSaaS型AIツールから始め、スモールスタートで効果を検証することが重要です。
AI人材の不足
AIを開発・運用できる専門的な知識を持つ人材が社内に不足していることも大きな課題です。
対策: 外部のベンダーやコンサルタントと連携し、専門的なサポートを受けるのが一般的です。また、既存の従業員向けにAIリテラシー向上研修を実施することで、社内の運用体制を強化できます。
従業員のAIに対する抵抗感
新しい技術への不安や、「AIに仕事を奪われる」といった懸念から、従業員がAI導入に抵抗を示すことがあります。
対策: AIは仕事を奪うものではなく、業務をサポートし、より価値の高い仕事に集中するためのツールであることを丁寧に説明します。導入初期には、AIが担当する業務範囲を限定し、従業員がその利便性を実感できるようにすることが効果的です。
これらの課題を乗り越えることで、AIは企業の生産性を飛躍的に向上させる強力な武器となります。
AIで効率化を図れる業務例
AIの学習能力は、業務効率化に強い威力を発揮します。部門別に、AIで効率化を図れる業務例を紹介します。
問い合わせ対応
AIは言語や音声を認識して、社外や従業員からの問い合わせに自動的に回答することができます。商品や企業のサイト上にAI活用型チャットボットを設置して、オペレーターの業務負担や人件費を削減しましょう。
オペレーターの手が空いた場合には、より複雑な問い合わせへの対応に注力してもらえます。丁寧な接客ができると、顧客満足度や従業員満足度の向上が見込めます。
営業活動
CRMやSFAにAIを活用すると、顧客属性や購買履歴をもとに分析を行い、見込み客を抽出できます。顧客一人ひとりにあわせたレコメンドも可能です。
AIの分析能力は、売上予測にも活用できます。大きな利益が見込める顧客に集中して営業をかけていれば 、効率よく売上を増やすことができるでしょう。また、AIを搭載したツールに高度な分析や単純な作業を任せると、営業担当者はクロージングのような人間らしさが要求される業務に集中できます。
人事業務
人事業務では、エントリーシートの審査や勤怠状況の管理にAIを活用できます。事前に採用に値する経験や学歴、職歴の内容などを学習させましょう。AIが大量のエントリーシートを識別し、採用担当者の負担を軽減します。人事異動の際も、従業員の経験やスキル、勤怠状況や勤務態度などのデータをもとに、適切な人材をピックアップすることが可能です。
採用業務が効率化すると面接に時間をかけられるため、より企業にマッチする人材を見極められます。
物流
物流にAIを活用すると、出入庫管理から検品、仕分け業務が効率化できます。たとえば、出入庫管理は、AIによる画像認識システムで自動化できます。それにより、これまで手入力で行っていた業務を大幅に効率化することができます。
また、倉庫外の業務も効率化できます。AIは渋滞情報や配車計画、ドライバーのスキルや運転の傾向などを加味し、最適な配送ルートを提案します。
生産工場
生産工場にはロボットが活用されていますが、経験やスキルに左右されがちな業務は機械化が困難でした。
AIの学習機能を駆使すると、微妙な匙加減が必要な業務も機械化できます。機械化が進行すれば、生産性も向上し、業務効率化やコスト削減が叶うでしょう。危険な作業を機械に委ねられれば、安全性も確保されます。
設備や機械の保守・保全
設備や機械は、使用を続けるうちに老朽化や故障によるトラブルが発生します。トラブルを防ぐためには、日常的・定期的な点検が欠かせません。しかし、目視のような経験に頼った点検だけでは、異常を見逃すケースがあります。
AIを保守・保全に活用すると、点検業務の自動化が可能です。点検の精度が上がり、高所や狭所のような危険な箇所にも対応できます。
【関連コラム】
AI活用で変わる業務プロセス~業務効率化の実例とヒント
AI活用で実現する業務効率化 - 導入事例と成功のポイント

AIを活用したチャットボットとは?
AIを活用することのメリットや業務例を紹介しましたが、その中でも業務効率化に役立つAI搭載型のチャットボットの導入を検討する企業が増えています。本章ではAI型のチャットボットについて、簡単に紹介いたします。
チャットボットとは
チャットボットとは、Webサイトやアプリなどに組み込むことで、Web上でユーザーからの質問に24時間365日自動回答を行うツールです。
チャットボット(Chatbot)とは?│初心者にもわかりやすく解説
AI搭載型のチャットボットとは
AI搭載型のチャットボットは、人工知能を搭載し、決められた回答以外にも、過去の履歴や会話などの蓄積されたデータをもとに、AIが学習し、チャットボットを利用するユーザーに対して、都度回答を作成し返信をする機能を持ったチャットボットのことです。
AIが過去の履歴や会話などの蓄積されたデータを活用するため、人的リソースの削減や業務効率化に役立つといったメリットがあります。
またチャットボットにはAI型の他、ルールベース型と呼ばれるチャットボットもあります。それぞれの特徴は異なるため、自社の目的にあったチャットボットを導入することをおすすめします。
【関連コラム】AIチャットボットとは?仕組みや価格相場、導入事例を紹介!
AI活用による業務効率化を進める際の注意点
AIを導入する目的や優先度、効率化したい工程などを明確にしましょう。企業の課題ごとに、AIに任せるべき内容は変わります。もしかすると、AIを導入せずとも課題を解決できる方法があるかもしれません。加えて、AIの導入にはコストがかかります。コストを無駄にしないためにも計画的な導入が求められます。
課題にかかわるデータの種類や量、AIの取扱いに長けた人材についても確保しましょう。データが少ない、適切な人材が見当たらないなどの場合は、環境を整えてからAIの導入を再検討すべきです。
まとめ
AIを活用することで、さまざまな業務の効率化が叶います。さらにRPAにAIを組み込むと、業務の効率化が可能です。自社の目的や問題を洗い出して、適切に導入しましょう。
たとえば、社内外の問い合わせをAIで効率化したい場合は、AI活用型チャットボットなどのツールを検討すると効率化につながります。
「RICOH Chatbot Service」は学習済みのAIを活用し、表記ゆれを自動で吸収します。部署別/業務別テンプレートを使うと、問い合わせに対応する原稿の作成も簡単です。導入前はもちろん、導入後も手厚くサポートしてくれるので安心です。チャットボットスペシャルサイトでは、無料デモや無料トライアル(30日間)も利用できますので、ぜひお問い合わせください。