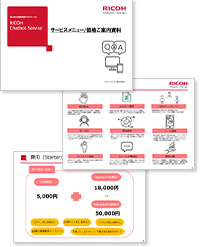FAQとは|何の略で、どう読む?
Q&Aとの違いや必要性について解説します

FAQとは、「よくある質問とその回答」をまとめた情報ページのことです。ユーザーが疑問を自己解決できるようにすることで、社内問い合わせ対応の効率化や顧客満足度の向上につながります。Webサイトやサービスのサポートページで広く活用されており、チャットボットとの併用でさらに効果が高まります。
本コラムではFAQの意味や似ている言葉としてある「Q&A」との違いに触れながら、FAQについて説明します。FAQの必要性についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
\RICOH Chatbot Serviceに関する
\資料ダウンロードはこちらから/
企業のホームページなどに掲載されているFAQとは、どういったものなのでしょうか。まずは、FAQの概略について説明します。ここでは、意味や読み方などを把握しましょう。
FAQとは英語のFrequently Asked Questions(フリークエントリー・アスクド・クエスチョンズ)を略した言葉です。
ウェブサイトやサービスで「よくあるご質問(FAQ)」と表記されている場合が多いです。
簡単に言うと顧客が頻繁に質問する内容と、それに対する回答をまとめたものです。FAQページでは、質問と回答がセットで掲載されており、顧客が自分で問題を解決できるよう、自己解決を促す目的で活用されます。
FAQ、どう読む?
FAQの読み方は、複数あります。たとえば、「エフ・エー・キュー」や「フェイク」などと呼ばれています。「ファキュー」などと読むことはありません。

FAQの意味を日本語に直訳すれば、「頻繁に尋ねられる質問」という意味になります。一般的には「よくあるご質問(FAQ)」と表記されている場合が多いです。
FAQを作成する際のポイントは、ユーザーが迷わないで一瞬でわかるようにすることです。主に4つ重要な点があるのでそれぞれ説明します。
1. ユーザーの視点に立つ
「よくある質問」は、企業が伝えたい情報ではなく、ユーザーが本当に知りたいことを反映する必要があります。顧客サポートに寄せられる問い合わせ内容を分析し、頻度の高い質問や、特に重要度の高い質問から作成しましょう。
2. 質問の意図を明確にする
質問文は、具体的な言葉で簡潔に表現します。「〜の方法は?」や「〜できますか?」など、疑問点が明確になるよう工夫することで、AIは質問の意図を正確に読み取り、適切な回答を選びやすくなります。
3. 回答は簡潔に、分かりやすく
一つの質問に対して、一つの回答を基本とします。専門用語は避け、専門的な内容を扱う場合は、簡潔な言葉で解説を加えましょう。関連するページへのリンクも、ユーザーとAIの両方にとって利便性が高いです。
4. 情報を分類・整理する
FAQの量が増えたら、カテゴリやタグで情報を分類しましょう。「製品仕様」「料金」「トラブルシューティング」などのカテゴリに分けることで、ユーザーもAIも効率的に情報を見つけられるようになります。
以上の点を踏まえ、FAQを作成しましょう。

一般的なFAQの構成は以下の要素を意識することで、より利便性が高まります。
カテゴリ分けを明確にする
製品、サービス、料金、利用方法、トラブルシューティングなど、カテゴリごとに質問を分類することで、ユーザーは自分の知りたい情報がどこにあるかを直感的に理解できます。これにより、FAQ全体の見通しが良くなり、使いやすさが向上します。
複数の質問から単一の回答へ誘導する
例えば、「パスワードを忘れた」「ログインできない」「PWの再設定方法」といった複数の質問に対し、一つの共通した回答(パスワード再設定の手順)に誘導できるよう設定しておくことが重要です。これにより、ユーザーは異なる表現で質問しても、同じ解決策にたどり着くことができます。
以上の構成を意識してFAQを作成することで、ユーザーの利便性が高まり、自己解決率の向上に繋がります。

FAQとQ&Aの違いは大きくはなく、どちらも「質問と回答」を基本とする情報形式です。しかし、本質的な目的と役割に明確な違いがあるため、説明します。
Q&Aとは
Q&Aは「Question and Answer」の略で、文字通り「質問と回答」を意味します。特定の質問に対して、その答えを簡潔に提供することを目的としています。Q&Aは想定されるあらゆる疑問に網羅的に答える傾向があり、特定の製品マニュアルや技術文書など、詳細な情報が必要な場面でよく利用されます。
FAQとは
FAQは「Frequently Asked Questions」の略で、「よくある質問」を意味します。これは、顧客やユーザーから頻繁に寄せられる、共通性の高い質問とその回答をまとめたものです。FAQの目的は、個別の問い合わせを減らし、ユーザーが自力で問題を解決できるようにすることにあります。そのため、多くのユーザーが抱えるであろう疑問に焦点を絞って情報を提示します。
両者の違いと使い分け
両者の最も大きな違いは、「質問の頻度」です。
FAQは頻繁に寄せられる質問に絞って構成されており、特定の製品やサービスに関する共通の疑問解決に特化しています。
Q&Aは頻度に関わらず、想定される幅広い質問を網羅的にカバーする傾向があります。
したがって、FAQはQ&Aの集合体の中から、特に重要な部分を厳選したものであると考えることができます。
FAQは、顧客対応の効率化と満足度向上を同時に実現できる仕組みです。電話やメールでの問い合わせが減ることで、業務負担やコストを削減でき、人的ミスの防止にもつながります。
さらに、顧客は自分のタイミングで情報を得られるため、利便性が向上し、結果としてサービス満足度の向上も期待できます。
FAQを活用することの利点を具体的に見ていきましょう。
電話やメールでの問い合わせ件数の削減が出来る
FAQがあれば、顧客が自ら調べることができ、問い合わせ件数の削減につながります。コールセンターで対応する件数も減るため、回線数や対応する人員を減らすことも可能です。そうなれば、コストも大幅にカットできるでしょう。
さらに、過去の膨大な対応履歴を素早く利用できるFAQシステムを導入すれば、より的確な対応も可能です。そうなれば、問い合わせに対して誤った回答をしてしまう可能性が低くなります。そのような人為的なミスも減らすことで、業務の効率化を図ることもできます。
顧客対応、サービスの向上が見込まれる
FAQは、顧客対応やサービスの向上にも役立ちます。企業のホームページにFAQがない場合、問い合わせ専用の電話番号やメールアドレスが掲載されていることが多いです。しかし、実際にはわざわざ電話やメールで問い合わせをするようなことはしない顧客もいます。
たとえ問い合わせたとしても、電話がつながりにくかったり、メールの返信がなかなかこなかったりするケースもあるでしょう。そういった場合、自社の商品やサービスに満足してもらえず、顧客離れが進んでしまうことも考えられます。
FAQがあれば、顧客が自分にとって都合の良いタイミングで自由に情報を確認することが可能です。FAQから情報を得るのに手間はかからないうえに、待たされるストレスもありません。FAQを導入すれば、結果として顧客の満足度向上につながります。
FAQシステム(チャットボット)を利用して
問い合わせ削減に成功した企業事例
導入後わずか3ヶ月で
ヘルプデスク業務を約30%効率化

西武鉄道 情報システム部様は、社内問い合わせ対応負荷の軽減を目的に「RICOH Chatbot Service」を導入。ヘルプデスク業務、システムメンテナンス時間の短縮に成功しました。

前述のとおり、FAQを掲載すれば、問い合わせ件数をある程度限定させることも可能です。さらには、それまで想定していなかった問い合わせの情報を得られるようになります。
新たに発生する問い合わせの内容を分析したうえで有効に活用できれば、さまざまなメリットが生じます。たとえば、クレームやリコールにつながるようなリスクを早期に発見し、損害を最小限に抑えることが可能です。また、問い合わせの内容によっては、新製品の開発におけるヒントとして活かせる可能性もあります。
SEO対策にも役立つ
FAQは、ホームページのSEO対策としても機能します。SEOとは、インターネット上の検索エンジンで検索されたときに、自社のホームページが上位に表示されるようにするための手法のことです。
検索エンジンは、よくある質問も検索の対象としています。そのため、SEOを意識してFAQの回答内容を作成すれば、検索から自社のホームページを訪れる人の数を増やすことにもつながるのです。そこから、自社の商品やサービスに興味を持ってもらうきっかけにもなるでしょう。
FAQを社内に導入した企業事例についていくつか紹介します。
大阪ガス株式会社様
大阪ガス株式会社様では電力自由化後の顧客ニーズ変化に対応するため、TMJと連携し電話中心のサポートをFAQ・チャットへシフトしました。初年度に運用ガイドラインとKPIを整え、導線改善でFAQ閲覧数を約2倍にし解決率も向上。翌年度は新システム導入で更新工数を削減し<0件ヒット>を大幅に低減。取り組みは社長賞を受賞し、今後はAIチャットで24時間対応を実現する方針です。東レ建設株式会社様
東レ建設株式会社様では、年間500件以上寄せられるマイクロソフト365関連の問い合わせを効率化するため、リコーの「RICOH Chatbot Service」を導入しました。このチャットボットは特にマイクロソフト365の問い合わせに特化して構築されています。その結果、問い合わせ対応時間を50%削減し、社内ヘルプデスクの担当者がより専門的な業務に集中できる環境を整えました。さらに、問い合わせが多かったシステムメンテナンス時間は1/8に短縮されました。
サントリーフーズ株式会社様
サントリーフーズ株式会社様では、応対品質の平準化とFAQ改廃の迅速化を狙い、低コストで検索性に優れる「ナレッジリング」を採用しました。Excel・紙管理を脱却し、キーワード検索で即時回答、資料削減と部署横断の情報共有を実現。応答時間を短縮して顧客待ち時間を削減し、オペレーターの自己学習にも活用され、全社で同一見解を共有できる基盤となっています。株式会社横森製作所様
不具合多発で利用離れした旧文書管理を刷新。シンプルで高速・低コストなNotePMを全社員に導入し、ISO資料や製品仕様、社内FAQを一元化しました。応答速度向上でクレームが消え、掲示板や外部共有で情報発信も活性化。海外拠点や委託先とも安全に共有できる点も高評価で、今後は管理者一括招待機能に期待しています。FAQにはさまざまな利点があるため、自社サイトにFAQがない場合は作成を検討したほうがいいでしょう。
自社サイトにFAQを設置するには、どのようにしたらいいのでしょうか。ここでは、FAQを設置する方法について、内容の決め方やサイトへの反映のしかたなどを具体的に解説します。
FAQに載せる内容を決める
FAQを作るためには、まず載せる内容を決めることが必要です。必要な情報はそれぞれの企業やサービスによっても異なります。決め方には以下のような方法があります。
お客様の立場になって想像する
FAQに載せる内容は、お客様の立場を意識して決めなければなりません。たとえば、過去に多く寄せられた問い合わせから、掲載する内容を考える方法があります。また、お客様にとって本当に必要な情報はどのようなものか考え、定期的に見直しをすることも必要です。
問い合わせ内容を収集する
FAQを作るためには、さまざまなところから問い合わせ内容を収集する必要があります。お客様と直接関わることが多い担当者であれば、日々の具体的な問い合わせについて熟知している可能性が高いです。そういったところからも問い合わせ内容を集めていきましょう。
アンケート調査を行う
FAQに掲載する質問を決めるときは、お客様の声を直接聞くことも大切です。たとえば、アンケート調査を行って、具体的な疑問点について確認してみるという方法もあります。アンケート調査から、お客様が持っている疑問点が浮かび上がってくるでしょう。
サイトへの反映方法を決める
お客様にFAQを活用してもらうためには、サイトへの反映方法も重要です。自社サイトに合った方法を選び、FAQを掲載するようにしましょう。
専用ページを作る
FAQを自社サイトに反映する方法としては、専用ページを作るのが一般的です。質問の数が多い場合は、カテゴリで分けて掲載すると目当ての質問にたどり着きやすくなります。お客様が必要としている回答が得やすいように工夫が必要です。
検索ページを作る
FAQを導入する方法としては、検索ページを作るのも有効です。お客様の中には、「自分の質問がどのカテゴリに該当するのか分からない」という人もいます。その場合、検索ページがあれば、キーワードを入力するだけで的確な答えが分かります。
チャットボットを設置する
FAQを元にしたチャットボットを設置すれば、お客様はより簡単に疑問を解決できるようになります。チャットボットなら、お客様が入力した内容に合う質問をすぐにピックアップして返答することが可能です。お客様の疑問が曖昧な場合は、詳細の聞き取りも自動的に行うことができます。
【参考】チャットボットの活用シーン
チャットボットとは、本サイトの画面右下に設置されているような、テキストや音声を通じて自動的に会話を行うプログラムのことです。チャットボットをWebサイトに設置することで、FAQページと同様、電話やメールでの問い合わせ件数の削減が実現でき、顧客の欲しい情報をすぐに返すことで顧客満足の向上を図ることが可能です。
FAQページとチャットボットの違いは主に以下の2つが挙げられます。
①質問に対する回答スピード
FAQページの場合、ユーザーは自分が知りたい情報に対して、掲載されている質問を自分の手で探さなくてはなりませんが、チャットボットは、あらかじめ用意した選択肢を選んでいくだけで、即座に回答まで辿り着くことができます。
②曖昧な質問への回答
ユーザーが質問内容をうまく言語化できない場合、FAQページでは自力で回答を探さなくてはならないですが、チャットボットでは、AIが入力内容から質問の意図を理解し、ユーザーにとって最適な回答を導き出すことができます。
【参考】チャットボットを実際に利用している事例を読む
【関連コラム】
チャットボットとFAQシステムの違いとは?
弊社ではチャットボットに関するお役立ち資料を無料でご提供しております。
興味がありましたら、以下のリンクよりお気軽にダウンロードください。
【資料ダウンロード】今こそチャットボット導入のチャンス!─社内外の問い合わせ対応を劇的に効率化
【資料ダウンロード】チャットボットの種類と特徴を押さえて自社にあったサービスを選ぶ
【資料ダウンロード】業種・業務別に見るチャットボット活用法
-
FAQを導入するとどんな業務改善が期待できますか?
誰が対応しても同じ情報を提示できるため、誤案内や説明不足を防止できます。
-
FAQの導入を検討中ですが、まず何から始めればよいですか?
「問い合わせを○%削減」「対応時間を○分短縮」など定量目標を決めてください。
-
FAQは多言語対応はしていますか?
対応しています。
-
FAQを設置するだけで、本当に問い合わせ件数は減りますか?
はい。よくある質問を網羅しておくことで、ユーザーが「自己解決」しやすくなるため、メールや電話での問い合わせの減少が期待できます。
-
FAQとチャットボットの併用にはどんな効果がありますか?
チャットボットはFAQを自動で案内できるため、24時間体制での問い合わせ対応が可能となり、さらに削減効果が高まります。
-
FAQを充実させるには、どのような内容を優先的に掲載すべきですか?
過去の問い合わせ履歴から多かった質問や、初めての利用者がつまずきやすい内容を優先すると効果的です。
FAQは、その企業に対して顧客からよく寄せられる質問をまとめたものです。FAQがあれば、顧客対応にかかる労力やコストを減らすことができます。また、顧客もスムーズに自分自身の疑問や悩みを解決できるため、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
自社サイトにFAQを設置する方法をいくつかご紹介してまいりましたが、中でもチャットボットの導入は近年、数多くの企業様のWebサイトで見られるようになってきました。
弊社が提供する「RICOH Chatbot Service」はこれまで様々な業種・業界のお客様に選ばれ、数多くの成功事例を収めています。
チャットボットの導入に興味がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!