ナレッジベースとは?
重要視される背景やメリットから活用できるツール、導入後のポイントまで解説

企業の知的資産であるノウハウや知識、技術を上手に活用すれば、業務の効率化を図れます。この記事では、自社でナレッジベースを構築して業務の効率化を図りたいと考えている人に向けて、ナレッジベースとは何か、重要視される背景やメリット、構築するために活用できるツールなどを解説します。ぜひ参考にしてください。
ナレッジ(knowledge)とは、直訳すると「知識」という意味をもつ用語です。ナレッジベースとは、業務に関するノウハウや知識、スキルなどを統合したデータベースのことです。社内ネットワークを介して利用することができ、必要な時に必要な情報にアクセスできます。ナレッジベースを構築すれば、個々の社員がもつノウハウや知識、スキルなどを企業の知的資産として蓄積できます。
ナレッジマネジメントとは、社内専用のナレッジベースを構築し、企業が成長するための経営手法のことです。業務で得たナレッジを社内で共有できれば、企業としての競争力や優位性を高めることにつなげられます。ナレッジベースの構築は、ナレッジマネジメントを円滑に行うための手段のひとつです。
ナレッジベースは実際にどのようにして活用されているのか、具体的な活用例を紹介します。
FAQ
FAQにも、ナレッジベースが活用されています。FAQとは、一般的に「よくある質問」として企業のホームページなどに設置されている質問と回答を載せたページです。ページには、ユーザーからの問い合わせが多い質問を集め、回答が記載されています。ナレッジベースは、問い合わせなどによってユーザーから受けた質問をまとめる際にも便利です。FAQがあれば、カスタマーサポート業務の効率化にもつながります。
また、ナレッジベースをチャットボットに連携する活用方法もあります。ユーザーからの問い合わせには、AIが自動で対応します。チャットボットは表記ゆれにも対応できるうえ、ユーザーも24時間いつでも気軽に質問できるのが特徴です。
FAQとは|何の略で、どう読む?Q&Aとの違いや必要性について解説します
自動応答音声
ナレッジベースの情報の活用により、電話での問い合わせの目的を分析する際にも役立てられます。問い合わせの目的がいくつかに絞り込めれば、目的別の案内ができます。自動応答音声とは、問い合わせをしてきたユーザーに対し、複数の選択肢を自動音声で提示できるシステムのことです。自動応答音声を使用すれば、オペレーターの負担も減らせます。
企業において、ナレッジベースの構築が必要な理由とは何なのか、背景について解説します。
終身雇用制度の崩壊・人材の流動化
戦後から採用されていた終身雇用制度が崩れ、人材の流動化は一層増しています。熟練社員の定年や早期退職、人員の入れ替わりなどによって、個々の社員がもつナレッジやノウハウを残せない現状があります。企業がナレッジやノウハウを蓄積するためには、ナレッジベースを構築し、社内で共有するための仕組み作りが重要です。働き方の多様化
企業は、働き方改革の促進や感染症などの影響により、多様なワークスタイルを受け入れる、環境の整備や体制の見直しなどの必要性に迫られています。リモートワークや在宅勤務、フレックス制などを導入する場合、従来よりもナレッジの蓄積や共有がしづらくなります。ナレッジベースを構築すれば、スムーズな共有が可能です。IT技術の発達
IT技術の発達により、クラウドサービスやデータベースが普及し、ナレッジの共有がしやすくなったことも、ナレッジベースが重要視される背景のひとつです。クラウドサービスやデータベースの利用により、ナレッジベースの構築が容易になったうえに、社内でのナレッジ共有も迅速に行えるようになりました。ここでは、企業がナレッジベースを活用すると得られる効果やメリットについて解説します。
素早い情報共有・更新が可能になる
ナレッジベースを構築してナレッジを蓄積すれば、社員が業務に必要な情報へ迅速にアクセスできるうえに、伝達漏れなどの対策としても有効です。ナレッジベースに蓄積したナレッジは容易に更新できるため、常に最新の状態を維持できるメリットもあります。業務の効率化・コスト削減につながる
これまでに蓄積したノウハウや業務フローを活用できるようになるため、業務の効率化につなげられます。また、FAQなどからユーザーへ必要な情報を迅速に提供できるため、企業への問い合わせ件数を減らせます。オペレーターの人員を減らすことで人件費削減も可能です。個人・企業で取り組める業務効率化のアイデア【16選】役立つツールも紹介
業務を均質化できる
同じ業務内容であっても、社員によって能力や業務をこなすまでにかかる時間は異なります。ナレッジベースを活用すれば、業務を効率よくこなしている社員のナレッジを他の社員に共有できるうえに業務の属人化も未然に防げるため、業務の均質化を図りやすくなります。顧客対応の質が向上する
ナレッジベースは、過去の事例などを検索する際に便利です。過去の事例をもとに迅速な顧客対応ができるようになるため、顧客満足度の向上が期待できます。また、業務を熟知した社員のナレッジを社内で共有できることから、会社全体のスキルアップにつなげられます。ナレッジベースは業務効率化に大きく貢献する一方で、導入にあたり注意が必要なポイントもあります。メリットだけに目を向けるのではなく、デメリットを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。
情報の形骸化・陳腐化のリスク
ナレッジベースの最も大きな課題は、登録された内容が更新されず、情報が古くなってしまうことです。一度「使えない」という経験をすると、従業員は利用しなくなってしまいます。せっかくのコンテンツも、適切な管理がなされなければ意味がありません。そのため、常にコンテンツの鮮度を保つ仕組みが不可欠です。
導入と定着のコスト
ツールの導入費用だけでなく、情報を蓄積・整理するための人的コストも考慮しなければなりません。特に運用に慣れるまでの時間が必要となったり、個人の負担が増えることで、形骸化を招くケースも少なくありません。費用対効果を最大化するためには、導入後の定着までを見据えた計画的な投資が求められます。
文化の醸成が困難
知識やノウハウの共有に積極的でない文化の組織では、ナレッジベースの定着がしづらいことがあります。優れたツールを導入しても、「自分の経験は教えたくない」「情報を入力するのが面倒」といった意識が障壁となり、有益なコンテンツが集まらないこともあります。ツール導入と並行して、知識共有を推奨する文化を醸成していく取り組みが重要となります。

ナレッジベースを構築する際に活用できるツールがあります。以下では、主なツールの種類について解説します。
データベース型
データベース型は、蓄積した情報を迅速に検索するためのツールで、社内でナレッジを共有する目的で利用する際に便利です。膨大な情報の中から必要な情報を検索にかかる時間を短縮できます。また、社外の人へ必要な情報だけを共有するといった活用法もあります。グループウェア型
グループウェア型は、タスクやプロジェクトなどの進捗状況などを共有するためのツールです。チャットやメールなどの機能があり、業務上で得たナレッジをリアルタイムで共有できるうえに、社内コミュニケーションの向上につなげられます。また、スケジュール管理も可能です。ヘルプデスク型
ヘルプデスク型は、社員やユーザーから得た意見やクレームなどの情報をナレッジベースに統合し、社内外向けのヘルプデスクでの対応に活かすためのツールです。社内向けヘルプデスクの場合、FAQの活用によって、マニュアルよりも迅速に必要な回答を探せます。データマイニングツール型
データマイニングツール型は、AIや統計を用いて蓄積したデータを分析し、ナレッジベースの構築に活かせるツールです。経営や営業戦略などの分析にも適しています。代表的なものとして、膨大な情報やデータの収集、分析などが可能なビッグデータが挙げられます。社内Wiki型
社内Wiki型は、インターネット上でナレッジの作成や編集が可能なWikipediaを社内向けとして利用できるツールで、社内でのナレッジの蓄積や共有が可能です。たとえば、ナレッジの解説、業務への活かし方などを共有できるほか、社内掲示板として活用する方法もあります。社内でナレッジベースを構築する方法とポイントについて、以下で詳しく解説します。
ナレッジベースを作る方法
ナレッジベースの構築は、自社で一から作る方法とツールを活用する方法の2種類があります。それぞれの方法について確認しておきましょう。自社で一から作る場合は、必要なナレッジを収集し、整理したうえでテキスト、グラフなどを作成します。ナレッジが多いほど、構築に時間や費用がかかります。ツールを活用する場合は、蓄積してきたデータやナレッジなどを保管するシステムやデータベースとツールを連携させ、ナレッジベースを構築します。
目的・課題を明確にしたうえで始める
ナレッジベースの活用やツールを導入する前に、何のためにナレッジベースを構築するのか、目的や社内の課題を明確にしておくことが大切です。たとえば、社内で保有するナレッジや情報が分散しているケースなどです。既存システムと連携できるツールを活用すれば、効率よくナレッジを統合できます。また、経営層と社員との間でナレッジの共有意識に差が生じている場合は、トップダウンで指示するだけでなく、社員にナレッジベースを活用する目的や必要性を理解させ、自発的に情報を共有できる環境を作りましょう。
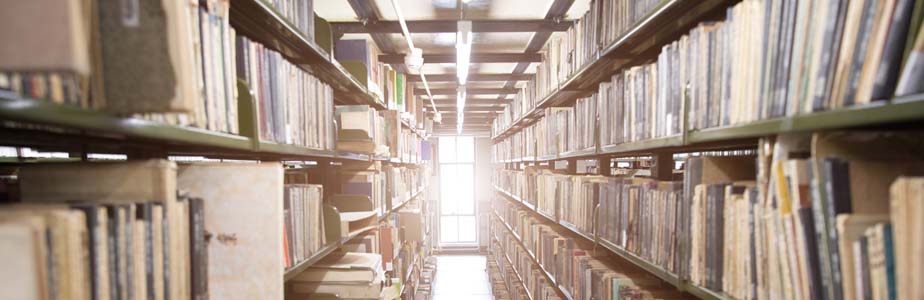
ナレッジベースを構築する際にツールを活用する場合は、以下で解説するポイントを参考にしてツールの選定を行いましょう。
どんな機能が備わっているか
ツールを選定する際は、どのような機能が搭載されており、自社に必要な機能が揃っているのかを確認しておくことが大切です。多機能なツールであっても、自社で活用できる機能が搭載されていなければ、導入コストを無駄にしてしまいます。利用者が使いやすいか
導入するツールが高機能であっても設定が複雑で操作しづらいものだと、社員に利用してもらえなくなります。ツールを選定する際は、誰でも操作しやすいか、最新の状態に更新できるかなど、業務で利用する社員が使いやすいかどうかを重視しましょう。検索性に優れているか
ナレッジベースを検索する方法には、キーワード、カテゴリ、タグなどが挙げられます。迅速にナレッジを検索するためには、ツールの検索性の高さを考慮する必要があります。また、ナレッジの検索性を高めるには、ナレッジの階層化が容易に行えることも重要です。さまざまなデバイスに対応しているか
ナレッジベースを社外から利用できると、業務に有効活用しやすくなります。パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどの社員が業務で利用しているデバイスに対応しているツールを選定しましょう。ナレッジベースは導入してからが本当のスタートです。組織の資産として価値を高め続けるためには、戦略的な運用を行い、システムを「育てていく」意識が欠かせません。
明確な運用ルールの策定
ナレッジベースを効果的に機能させるには、誰が、いつ、どのような内容を追加・更新するのか、明確なルールが必要です。例えば、部署ごとに管理責任者を置いたり、情報のテンプレートを統一したりすることで、コンテンツの質を担保し、検索性を高めることができます。このルールを組織全体で共有し、徹底することが運用の第一歩です。
利用促進と改善のサイクル
ナレッジベースは、チームのメンバーが積極的に利用して初めて価値が生まれます。そのため、管理者は定期的に利用状況を分析し、あまり見られていないコンテンツの改善や、検索頻度の高いキーワードに関連する情報の追加を検討しましょう。従業員からのフィードバックを収集する仕組みを作り、改善のサイクルを回し続けることで、真に役立つデータベースへと成長することができ、企業の課題解決に貢献します。
専任の管理者の設置
ナレッジベースの継続的な運用には、全体を把握し、活性化を促す管理者の存在が効果的です。管理者は、ルールの周知徹底、利用の促進、内容の棚卸しなどを主導します。個人の努力だけに頼るのではなく、チームとして運用体制を構築することで、最終的なゴールである業務効率化の実現へと繋がります。

近年ではAI(人工知能)を活用した新しい形のナレッジベースが注目されています。AIの活用で、より高度な情報の蓄積と活用を行うことができ、更なる業務効率化を実現するでしょう。
高度な検索機能による課題解決
AIナレッジベースの最大の特徴は、その高度な検索能力にあります。AIが質問の意図や文脈を理解し、膨大なコンテンツの中から最適な回答を自動で探し出して提示します。これにより、従業員はキーワード検索に悩むことなく、必要な情報へ瞬時にアクセスでき、迅速な問題解決が可能になります。個人の検索スキルに依存せず、誰もが平等に情報を活用できる環境が整います。
情報登録・管理の自動化
AIは、社内のドキュメントや過去のやり取りから、ナレッジベースに追加すべき情報を自動で抽出・提案してくれます。これにより、情報登録にかかるチームの手間が大幅に削減されます。また、重複する内容の指摘や、関連性の高いコンテンツの紐づけも自動で行うため、管理コストを抑えながら、データベース全体の質を高めることができます。
組織全体の知的生産性を最大化
AIナレッジベースは、単なる情報の保管庫ではありません。社員一人ひとりの経験や知識をAIが学習・解析し、組織全体の共通資産として再構築します。これにより、属人化していたノウハウが共有され、組織全体の知的生産性が飛躍的に向上します。
AIという強力な頭脳を得ることで、企業はかつてないレベルの業務効率化とイノベーションの実現が期待できると考えられています。

ナレッジベースを構築すれば、社内での情報共有や業務の効率化などの効果が得られます。ただし、一から構築すると膨大な時間やコストがかかるため、データベース型やデータマイニングツール型などの既存のツールを有効活用しましょう。
業務の効率化を考えるなら、問い合わせ窓口などのリソース削減や効率化も効果的です。
リコージャパン株式会社の「チャットボットスペシャルサイト」は、学習済みのAIを使用した表記ゆれを自動で吸収できるチャットボットサービスを案内しています。導入や運用が簡単に行え、手厚いサポートもついていて簡単に利用できます。30日間の無料トライアルも実施しているため、ぜひお試しください。
資料ダウンロードはこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!











