FAQの作成に役立つツールとは|FAQ導入のメリットやツールの選び方、最新トレンドなど解説します!

社内やお客様からの問い合わせへの対応は、負担がかかることも多くあります。業務を効率化できないかと検討している担当者もいるのではないでしょうか。
解決策のひとつがFAQの導入です。この記事ではFAQ作成に役立つツールとはどのようなものか、FAQを導入するメリットや注意点も合わせて解説します。ぜひ参考にしてください。
「FAQ」とは、「よくある質問」とその回答をまとめ、記事化してサイトなどで公開することです。種類は大きく分けて社内向けと、ユーザー(顧客)向けの2種類にわけられます。FAQを導入すれば、エンドユーザーの自己解決を促せるとともに、サービス担当者が的確に回答するためのサポートにもなります。的確かつ迅速な顧客対応が可能になることで、ユーザーの満足度向上にもつながるでしょう。
導入するためには、まず「よくある質問」を整理したうえで分析し、ユーザーが知りたい内容に対する的確な回答を用意しなければなりません。なお、FAQ作成ツールには応答記録をもとに自動でFAQが作成できるものなど複数の種類があります。以下の段落でさらに詳しく解説します。
FAQの種類は大きく分けて「社内向けFAQ」と「ユーザー(顧客)向けFAQ」の2種類です。以下でそれぞれの特徴や目的について解説します。
社内向けFAQ
社内向けFAQは、主に社内マニュアルの共有が目的です。具体的な例として、従業員が日々行う仕事に関する社内のルールやワークフローをまとめた業務マニュアルや顧客対応マニュアルなどが挙げられます。また、カスタマーサポート(お客様からの問い合わせ対応)を支援し、業務の効率化を図ることが目的のFAQも社内向けFAQに含まれます。ユーザー(顧客)向けFAQ
ユーザー向けFAQは、ユーザーの疑問解決が目的です。あらかじめ「よくある質問」と回答を用意しておくことで疑問が解決できたり、サポートセンターへ問い合わせる必要がなくなったりします。なかにはユーザーが直接書き込んだ疑問に、他のユーザーが回答してくれる掲示板タイプのFAQや、操作マニュアルとして利用できるタイプもあります。社内向けFAQでは工数の削減や属人化の防止、ノウハウの蓄積などの多くのメリットがあります。以下でそれぞれ詳しく説明します。
問い合わせ対応にかかる工数の削減
FAQがない状態では、カスタマーサポートなどの担当者がユーザーの疑問に直接対応することになります。FAQを作成し、内容を充実させればユーザー自身で疑問を解決できるケースも増え、問い合わせ数を減らすことができます。その分、対応に時間を取られていた担当者の負担を減らし、コア業務に集中させることもできます。属人化の防止
決まった担当者だけに業務を任せていると、その人が居なくなれば誰にも詳細が分からなくなることがあります。ベテランに頼っていたところ、その人が退職したら同じレベルで業務を引き継げる人が育っていないということも起こりえるでしょう。FAQを導入することで、特定の人にしか担当できないという状況を防ぐことができるのです。ノウハウが蓄積される
そもそもFAQは、よくある問い合わせの質問と回答を集めて整理したものです。自社の業務にかかわる内容やユーザーが疑問に思うポイントを網羅しているため、FAQの作成がノウハウの蓄積にもなります。社内に系統だったノウハウが蓄積されていることで、従業員がFAQを参照しながらキャッチアップもできるようになります。
ユーザー向けFAQでは、顧客ニーズの把握や顧客満足度の向上が見込めるほか、時間外でも対応できるメリットがあります。
顧客ニーズの把握ができる
FAQは、どのような疑問にアクセスが集中しているのかなど、情報を蓄積できるシステムでもあります。つまり、閲覧記録を分析すれば、顧客ニーズの把握が可能です。質問に対する回答が的確であるかどうかを検討すれば、さらに充実した回答を用意することもできるでしょう。ニーズを踏まえたうえで、新製品や新サービスの開発に活かすこともできます。顧客満足度向上につながる
FAQがない状況で疑問が生じたとき、ユーザーは電話やメールなどで問い合わせをするしかありません。しかし、なかには電話やメールでの問い合わせに抵抗やデメリットを感じる人もあり、商品の注文やサービスの利用まで至らずに離脱してしまうこともあり得ます。FAQの閲覧で問題解決できることは大きなメリットとして働き、顧客満足度の向上につながります。時間外でも対応できる
昼夜にかかわらずサポートセンターを稼働させていても、手薄な時間が発生する可能性があります。そもそも夜間や土日・祝日は問い合わせに対応していないところもあるでしょう。FAQを整備しておくことで、時間にかかわらずユーザーが疑問に対して自己解決できる機会が増え、夜間や休日にコールセンターを設置しなくてもユーザーサポートができます。FAQ導入を成功させるためには、システム選定と導入計画における注意点を押さえることが重要です。特にコストパフォーマンスと利用促進の課題は、導入失敗の一般的な原因です。
システム選定と費用のバランス
多機能なFAQシステムは魅力的ですが、自社の規模や目的に合わない機能を搭載していると、無駄なコストが発生します。初期の構築費用だけでなく、月額の料金や保守費用も含めた総額で判断することが重要です。機能が多ければ高い成果が出るとは限りません。必要な機能(例えば、強力な検索機能や分析機能)を見極め、費用対効果をシミュレーションすることが求められます。安価でも検索精度が低いシステムは、結局使われず失敗に終わるリスクがあります。
コンテンツの品質と量のバランス
導入初期に完璧な網羅性を目指すと、コンテンツ作成に膨大な時間がかかり、公開が遅れてしまいます。かといって、回答の精度が低い、または情報が不足している状態では、利用者のためにならず、問い合わせが減りません。スモールスタートを意識し、最も頻度の高い問い合わせから優先的にコンテンツ化することが効率的です。初期段階で適切なタグ付けや、利用者が入力するであろうキーワードを想定しておくことも、検索性向上につながります。
利用者への周知計画の不足
導入と同時に、FAQの利用を促す周知活動を計画することが不可欠です。社内向けであればポータルサイトでの目立つ表示や研修での案内、顧客向けであればWebサイトの目立つ場所への導線設置や、サポートデスクが問い合わせを受けた際にFAQへ誘導する手順を徹底するなど、具体的な施策が求められます。この周知を怠ると、利用率が上がらず、導入効果の実現が遠のきます。
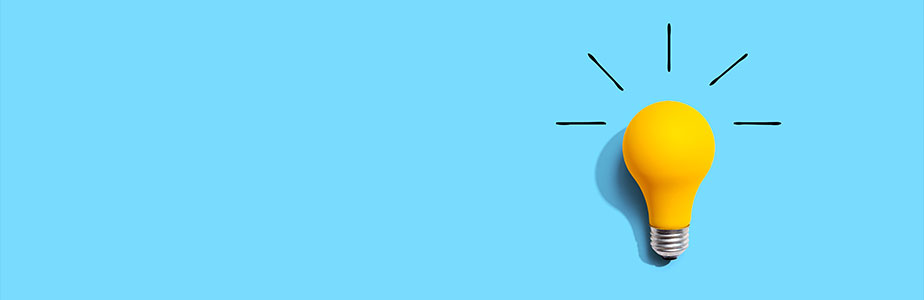
自社でFAQの作成や追加・修正を行うためには、それだけ人手を割かなければなりません。ツールのなかには、実際にコールセンターで対応した記録から自動的に問題集を生成してくれるタイプもあるなど、適切なものを活用すれば担当者の負担を減らせます。問い合わせ内容を自動分析したうえで、オペレーターに模範解答を示してくれるツールもあります。
直感的にFAQ作成やコンテンツ追加の操作ができるタイプなら、専門的なHtmlやCSSなどの知識がない担当者でも運用や管理が行いやすいでしょう。ほかにも検索機能に特化したタイプやAIを活用したもの、チャットボットで自動応答できるものまで実に多彩なツールがあるため、自社の状況に合わせて選ぶことが大事です。
では適したFAQ作成ツールを選ぶためには、どこに気をつけばいいのでしょうか。ポイントは以下の2点です。
担当者が操作しやすいもの、ユーザーにとっても使い勝手のよいものを選ぶ
実際に作業をする担当者にとって、使いやすいツールを選ぶ必要があります。具体的にはFAQの作成や修正、更新作業の操作がしやすい、画面が見やすいなどです。決まったテンプレートがあるものや、Excelから内容をインポートできる機能を備えたツールも使い勝手がいいでしょう。また、社内の担当者だけではなく、ユーザーにとって使いやすいシステムであることも求められます。無料のお試し期間があるなら、導入前に使い勝手を確認してみることもおすすめです。
導入目的や自社の業務に合った機能を備えているものを選ぶ
先述したようにFAQツールにはいくつかの種類があり、機能はさまざまです。合わないツールでは効果を発揮しないどころか、かえって使いづらい場合もあります。導入を検討する時点でまずは目的を明確にし、自社の業務に合ったツールを選ぶことがポイントです。例えば、気軽に問い合わせをしてもらいたい意図があるなら、チャットボットタイプが向いています。また、自社に合ったツールを選ぶポイントについては、以下の「FAQ運用の注意点」の段落も参照してください。
ここからは実際にFAQを運用していく段階において注意すべきポイントを3つにわけて解説します。
導入前に目的や業務フローを整備しておく
導入したツールが適切ではなかった場合、運用を開始してから使い勝手が悪いことに気づいたり、作業工数の削減につながらないなどの問題が起こる可能性があります。あとになって不都合が生じないように、あらかじめ情報を共有したいのか、サポートセンターの業務を削減したいのかなど、自社の目的を明確にしておくことが大事です。また、ツールを導入することで逆に業務の工数が増えることがないよう、適切なワークフローを設定しておく必要もあります。
FAQは導入して終わりではない
FAQは状況に合わせて常に修正を加え、最新の状態を保っておく必要があります。例えば、FAQを参照してくれても知りたい内容が含まれていなければ、ユーザーのニーズを満たせません。問い合わせ傾向を踏まえたうえで、適宜コンテンツの修正や追加などを行い、充実させていくことが重要です。また、FAQを導入していることをしっかり周知しておく必要もあります。問い合わせ傾向のデータだけでなく、営業担当者などからも情報を得る
FAQを充実させるためには、サイトへの問い合わせ内容だけを吸い上げるのではなく、営業担当者など社内の情報も取り入れるべきでしょう。例えば、ユーザーの声を直接聞く機会を持つ営業担当者は、よりリアルなユーザーの疑問を日々感じていることも多くあります。FAQに取り上げる内容を決める際は、社内でヒアリングを行い、生の声を聞くことも大事です。FAQを「使われる」状態にするには、導入後の継続的な運用が不可欠です。以下では、利用者に使ってもらうための運用ポイントを解説します。
利用者の目に触れる導線設計
優れたFAQも、利用者の目につかなければ存在しないのと同じです。Webサイトのフッターに小さく「FAQ」と表示するだけでは不十分です。トップページや関連製品ページ、エラー表示画面など、顧客が疑問を感じる瞬間にFAQへのリンクを目立たせて配置することが重要です。サポートデスクのオペレーターが問い合わせを受けた際にも、口頭でFAQを案内する手順を徹底し、FAQ利用の習慣化を促すことも効率的な手法です。
検索性と可読性の継続的な改善
利用者は疑問を素早く解決したいと考えています。検索窓の入力サジェスト機能の改善や、同義語・表記ゆれ(例:「料金」「費用」)の登録を定期的に行い、検索精度を維持する必要があります。また、専門用語を多用した回答は、利用者のためになりません。図解や動画を適切に搭載し、テキストは簡潔に保つことで、可読性を高いレベルで維持します。適切なタグ付けによるカテゴリ分類の見直しも、利用者が回答にたどり着くのを助けます。
チャットボットとは、Webサイトやアプリなどに組み込むことで、Web上でユーザーからの質問に24時間365日自動回答を行うツールです。どちらも問い合わせ対応時に使用されるツールではありますが、以下のような違いあります。
①疑問や悩みを解決する方法が異なる
FAQの場合は掲載元の内容からユーザー自身で探すのに対し、チャットボットの場合は会話を通じて自動で問い合わせの回答を掲示してもらえます。
②質問に対する回答スピードが異なる
前述の通り自身で探すFAQに対して、チャットボットは即座に回答までたどり着くことが可能となります。
③伝えられる情報量が異なる
FAQの場合、複雑な内容や長い文章であっても、それらを画像などを活用し丁寧に伝えることができます。一方でチャットボットの場合、Webサイトの端に設置されるケースが多く、短文で分かりやすい内容のみとなるため、掲示できる情報は異なります。
以上にようにFAQとチャットボットにはそれぞれ違いがあるので、どちらかのツールを検討する際は、導入目的を整理したうえで、自社に合ったツールを選定することが重要となります。
FAQシステムは、テクノロジーの進化と共に新たなトレンドを迎えています。顧客サポートの効率化と満足度向上を実現するため、最新の動向を紹介します。
AIによる検索精度の飛躍的向上
従来のキーワード検索では、利用者の入力とFAQのタグが一致しないと回答にたどり着けない課題がありました。しかし、AIを搭載したセマンティック検索が主流となり、入力された文章の「意図」をAIが理解。より精度の高い検索が可能です。これにより、利用者が自己解決できる割合が大幅に向上し、問い合わせデスクへの入電を削減します。
生成AIによる運用効率の最大化
最新のトレンドとして、生成AIの活用が急速に進んでいます。オペレーターが入力した対応履歴やマニュアルから、AIがFAQの回答案を自動で生成・要約する機能です。これにより、FAQコンテンツを構築するコストと時間が大幅に削減されます。また、回答の表示方法を最適化したり、パーソナライズされた回答を実現したりするなど、顧客体験の向上にも寄与しています。
よくある質問と回答を集めたFAQは、企業の担当者にとってもユーザーにとってもメリットがあります。しかし、FAQを作成するためのツールにはさまざまなものがあり、自社に適したものを選ぶことが重要になります。
「RICOH Chatbot Service」は導入や運用が簡単なうえ、無料デモや無料トライアル(30日間)にも対応しています。サポートも充実しているため、はじめて導入する際も安心です。FAQツールとしてチャットボットの導入を検討しているのなら、まずは資料ダウンロードをお試しください。
資料ダウンロードはこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!












