生成AI導入時に社内ルールを策定すべき理由とは?
具体的なルールや作り方まで解説

生成AIの「ChatGPT」が2022年にOpenAI社より公開されて以来、日本国内において生成AI活用の大きな波が起きています。社内専用の生成AIツールを構築する企業も増えており、今後もますます多くの企業で導入が進んでいくものと考えられます。
しかし、生成AIはまだ取り扱い方に注意が必要な面があり、導入時には社内ルールを策定して全社的に統一された活用を進めています。
今回は、生成AI導入時に社内ルールが求められる理由からその具体的な内容、作り方、社内ルール策定のポイントをご紹介します。
まずは生成AIの概要と共に、導入時に社内ルールが求められる理由、策定のメリットを見ていきましょう。
●生成AIとは?
生成AI(Generative AI)は人工知能(AI)の一種であり、特に「生成」に特化した能力を持つ技術です。テキストや画像、音声、動画などの多様な形式のコンテンツを自動生成可能です。
従来のAIは与えられたデータをもとに最適な解を見つけ出すことを目的としていましたが、生成AIはディープラーニング(深層学習)と呼ばれる技術によって学習した膨大なデータのパターンや関係性を活かし、新しいデータを生成することを目的とします。
●生成AIの社内ルール策定が求められる理由
生成AIを企業が社内に導入する際には、多くの場合、合わせて社内ルールを策定するのが一般的になっています。なぜ策定する必要があるのでしょうか。
その大きな理由は、生成AIには著作権侵害や情報漏洩、誤情報による意思決定のリスクなどがあることから、使用方法や生成結果の取り扱い方を誤ってしまうと、企業として大きな損害につながることが挙げられます。
生成AIの社内ルールを策定することは、次のメリットが期待できます。
【関連コラム】
生成AIで作成した文章や画像の著作権はどうなる?トラブル防止のためのポイントを解説
●生成AI社内ルール策定のメリット
・法令違反、情報漏洩の予防 生成物に著作権を含むコンテンツが含まれていることを知らずに活用してしまうと著作権法違反になります。また生成AIは一般的にユーザーが入力した内容を学習のために保存するため、個人情報などの機密情報を含んでいた場合、学習に使われてしまう恐れがあります。もし社外のユーザーの生成結果に自社の機密情報が漏洩してしまえば、大きな損害につながります。
さらに、生成AIにはハルシネーションと呼ばれる、「虚偽や誤った情報をあたかも事実であるかのように生成する現象」が起こることがあり、誤情報を取り扱うリスクがあります。
社内ルールを策定し、これらのリスクを周知し、生成物の人によるチェックを欠かさないことや機密情報を入力しないなどの予防策を義務付けることで、生成AIの安全な利用が可能になります。また、万が一トラブルに発展した際の対応策も規定しておけば、より安心して生成AIの活用ができるでしょう。
【関連リンク】
生成AIのセキュリティリスクとは?具体例から対策までわかりやすく解説!ChatGPTを社内で利用する際に注意すべきこととは?
・従業員のリテラシー向上 社内ルールを通じて従業員が生成AIを安全に使いこなせるようになれば、従業員のITリテラシーや生成AIに関する活用スキルが向上するものと考えられます。DX推進やリスキリング(学び直し)にも貢献するでしょう。
・生成AI活用による生産性向上 社内ルールを策定することで、従業員が安心して生成AIを使えるようになる環境が整い利活用が促進されるため、生産性向上につながると考えられます。人手不足などの課題に直面する場合は、省人化やコスト削減にもつながります。
・社内利用の均一化 生成AIをルールなくただ導入すると、一部の層だけの利用にとどまってしまったり、従業員や部署・部門ごとに活用ルールがバラバラになってしまうことがあります。特に先述の複数のリスクを確実に回避するためにも、社内ルールの策定は重要であり、利用の均一化につながります。
生成AIの社内ルールに盛り込むべき具体的な内容を見ていきましょう。
●利用可能な業務範囲
●機密情報入力の禁止
●著作権侵害に注意する
●ハルシネーションや倫理的な問題への配慮
●トラブルが起きたときの対処法
●ユースケースごとの注意点
生成AIを使用して良い業務の範囲をあらかじめ定めることで、各種リスクを最低限にとどめることができます。具体的なリスク回避につながるルールも必要です。例えば機密情報の入力を禁止したり、著作権侵害に注意したり、ハルシネーションや倫理的な配慮のされていない生成物への配慮を徹底したりすることが重要です。
また、トラブルが起きたときの具体的な対処法を、ステップごとに記載することも求められます。ユースケースごとにどのようなリスクが発生し得るか、また生成後のチェックの仕方などを記載することで、より利活用が進むでしょう。
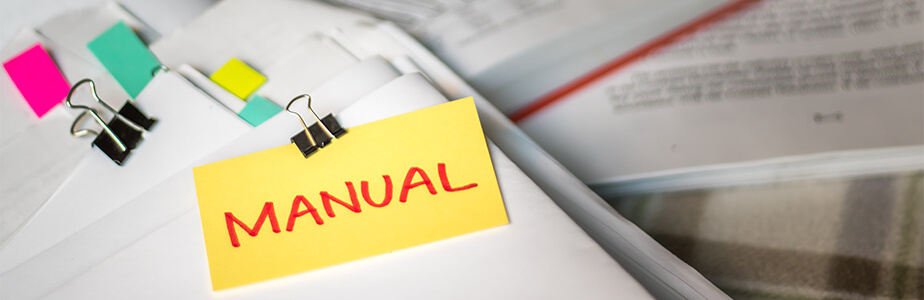
では、生成AIの社内ルールはどのように作れば良いのでしょうか。ステップをご紹介します。
1.社内ルール策定の目的の明確化
社内ルールは、どのような目的で策定するのか、明確にしておくことが重要です。例えば、「情報漏洩や権利侵害など、企業の損害を未然に予防するため」「生成AIの適切な利用を推進し、生産性向上につなげるため」などの目的が挙げられます。
2.自社の生成AI活用の用途や範囲の決定
生成AIの導入目的に応じて、生成AIを活用する用途や範囲を定めます。
3.生成AI利用のリスク分析
生成AIを利用する用途や範囲それぞれについて、どのようなリスクがあるのかを洗い出し、分析を行います。
4.生成AI利用のリスク分析結果に基づき必要なルール策定
リスク分析結果に基づき、禁止事項などのリスク回避に必要なルールを策定します。
生成AIの社内ルールを策定しても、運用の方法を誤ると形骸化したり、かえってリスクを高めたりすることがあります。ここでは、多くの企業が生成AIの社内ルールを活用する際に陥りがちな「落とし穴」を3つ紹介します。
●厳しすぎる制限によるシャドーAIの発生
リスクを恐れるあまり「原則利用禁止」や「過度な申請手続き」を設けると、業務効率を求める従業員が会社の管理外で個人アカウントのAIを利用するシャドーAIを誘発します。これは最も管理が届かない危険な状態です。ルールは縛るものではなく「安全に使うためのガイド」として、利便性とのバランスを考慮しましょう。
●技術進化に追いつかずルールが陳腐化する
生成AIの技術は日進月歩です。策定時には想定していなかった「画像生成」「音声認識」「ファイルのアップロード」などの新機能が次々と登場します。1年前に作ったルールを固定したままにすると、現場の実態と乖離し、ルールが守られなくなる形骸化の要因となります。
●人の善意とリテラシーに頼りすぎる
「機密情報は入力しないこと」と周知するだけでは、ヒューマンエラーを完全には防げません。悪意がなくても、どれが機密情報にあたるかの判断基準が個人で異なれば、情報漏洩のリスクは残ります。ルールというソフト面だけでなく、システム側で制御する「ハード面」の対策も併せて検討することが重要です。

続いて、社内ルール策定のポイントをご紹介します。
●各種ガイドラインを参考にする
社内ルールはゼロから作ることもできますが、既存のガイドラインを参考にすることで、より生成AIによるリスク回避や利活用を推進できると考えられます。
日本ディープラーニング協会(JDLA)の「生成AIの利用ガイドライン」をはじめ、各自治体や企業、団体、大学が策定したガイドラインを参考にすることができます。
【参考】
一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)「生成AIの利用ガイドライン」
●利便性と安全性のバランスを考慮する
ルールを厳しく制限しすぎると、かえって無断利用を招く原因となります。禁止事項を定めるだけでなく、「どのようなケースなら積極的に使ってよいか」という推奨活用例をセットで明示することが、従業員の安心感と利活用促進につながります。
●ツールによる「仕組み」での対策を並行する
「機密情報を入力しない」というルールを徹底するだけでは、ヒューマンエラーを完全には防げません。ルールというソフト面だけでなく、入力データが学習されないようなハード面の対策をセットで行うことで、より強固なセキュリティ環境が構築できます。
●専門家に相談しながら作成する
生成AIをはじめとしたAI全般の専門知識を持った専門家や弁護士などに相談しながら、社内ルールを策定することもリスク回避のために有効です。
●社内ルール策定後に周知・研修を行う
社内ルールを策定した後は、ただ従業員向けに配布するだけでなく、同時に周知のアナウンスや研修を行うことで、よりルールが浸透すると考えられます。
●定期的に見直す
社内ルールを策定し、生成AIの社内利用が進んでいけば、利用の範囲を広げたくなったり、新たなリスクが生じたりすることもあります。社内ルールは定期的に見直し、随時アップデートしていくことで、安心安全かつ効率的な利用を進められるでしょう。

-
生成AIの社内ルールを策定する最大のメリットは何ですか?
情報漏洩や著作権侵害のリスクを抑えつつ、従業員が安心してAIを活用できる環境を整えられる点です。ルールが明確になることで、安全性と業務効率化を両立できます。
-
生成AIの社内ルールに最低限盛り込むべき項目は何ですか?
「利用範囲」「機密情報の入力禁止」「生成物の事実確認」「著作権への注意」「トラブル時の報告フロー」の5点は、リスク管理上、必須項目として盛り込むべきです。
-
生成AIの社内ルールを厳しくしすぎることによる弊害はありますか?
はい。過度な制限は、従業員が管理外でAIを使う「シャドーAI」を招きます。禁止事項だけでなく、推奨される活用例も示し、利便性とのバランスを取ることが重要です。
-
策定した生成AIの社内ルールは、どのくらいの頻度で見直すべきですか?
技術進化や法整備が非常に速いため、半年から1年単位の見直しを推奨します。新機能や最新のリスクに合わせて随時更新することが、ルールの形骸化を防ぐ鍵となります。
生成AIを導入する際には、利用促進やリスク回避のために社内ルールの策定も同時に行うことが重要です。策定から周知、研修、見直しなど一連の流れに手間取ることもあるかもしれませんが、生成AIの適切な利用のためには投資すべき取り組みといえます。
また、あらかじめリスクの少ない生成AIを導入することも、検討しましょう。
リコーの「RICOH Chatbot Service」なら生成AIを活用した企業向けChatGPT連携サービスもあり、特にセキュリティリスクを回避しながら生成AI導入をご検討中の方におすすめです。
ぜひRICOH Chatbot Service 生成AIチャットのラインナップをご検討ください。
・RICOH Chatbot Service 生成AIチャット from 一般ナレッジ
リコーがご提供するチャットボット上でChatGPTを手軽に利用できます。Azure OpenAI Serviceでセキュアな環境を実現しており、通常のChatGPTとは異なり、社内データなどを入力しても学習されず、情報漏洩の心配がありません。
・RICOH Chatbot Service 生成AIチャット from 社内ナレッジ
社内データをアップロードすることで、社内データに基づき生成AIが回答する自社専用のAIを活用できるようになるサービスです。入力した内容も社内に留まるため、漏洩リスクはありません。
生成AIをセキュアな環境で活用されたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
RICOH Chatbot Service紹介資料はこちら RICOH Chatbot Serviceスペシャルサイト RICOH Chatbot Serviceの問い合わせフォーム
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!










