チャットボット導入の注意点 - チャットボットを育てる教育とは
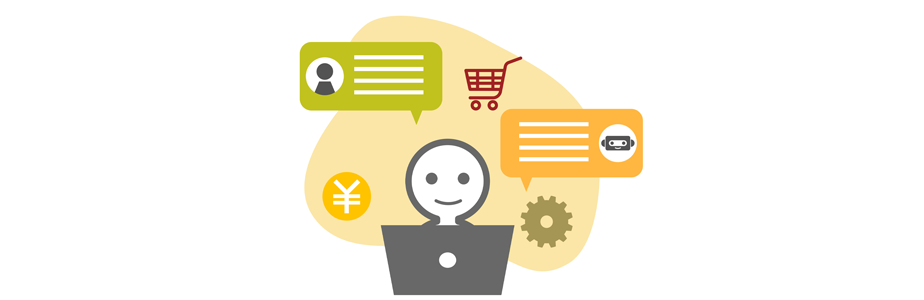
人件費削減、対応品質向上、お客様満足度アップ、顧客接点機会増、業務効率化などのメリットが注目され、最近急激に導入企業数が増えているチャットボットですが、導入する際には、思ったような効果が出ないなどの失敗をしないよう、いくつか注意をすべき点があります。
最も気を付けるべきは、「回答精度の低いチャットボットにはお客様と会話をさせてはいけない」という点です。Webサイトにおけるチャットボットの役割は、店頭でお客様に声をかける接客担当のようなものです。
店頭でこんにちは!と気持ちの良い声がけが出来たとしても、その後お客様からの「〇〇を探しているんだけど、あるかな?」という質問に対して「今日はすごく暑いですよね。コーヒーはいかがですか?」などのトンチンカンな返答をしてしまったら、お客様は怒って帰ってしまいますよね?
チャットボットも同様です。お客様が知りたいことや質問に対して的を射た回答をしていく能力が求められるのです。
チャットボットは、「チャット(会話)」と「ボット(ロボット)」を組み合わせた言葉で、テキストや音声を通じて自動で会話を行うプログラムを指します。Webサイトやビジネスチャット、SNSなど、様々なプラットフォームでの利用が可能です。このツールを導入する際の注意点として、まず自社のニーズに合った種類を選択することが挙げられます。
チャットボットの主な種類
チャットボットは、大きく「シナリオ型(ルールベース型)」と「AI型」の2つに分けられます。シナリオ型は、あらかじめ設定したルールやシナリオに沿って応答するタイプです。単純な質疑応答や決まった業務の効率化に適しており、比較的容易に構築できます。一方、AI型は、蓄積されたデータからAIが学習し、より複雑で幅広い問い合わせに対応可能です。自然な会話に近い形でユーザーの意図を汲み取ることができますが、構築には専門的な知識や準備が必要になる場合があります。どちらのタイプを選ぶか、あるいは両者をどう組み合わせるかが重要になります。チャットボット(Chatbot)とは?初心者にもわかりやすく解説
チャットボットを導入する場合、お問い合わせ業務の負荷を減らしたり、お客様の利便性を上げ、満足度を向上させたりといった何らかの導入目的を持っていることでしょう。導入すると、確かにはじめのうちはチャットボットに問い合わせが行くため、人の対応が減るというメリットが得られます。しかし、その導入目的を達成し、導入効果を最大化するためには「教育」が必要不可欠です。なぜなら、教育が不完全だとユーザーにストレスを与えてしまい、「はじめからチャットボットを使わず、電話すればよかった」「結局、チャットボットのほうが解決までに時間がかかってしまった」などと思わせてしまうことがあるためです。実際、チャットボットの回答精度が低いことで、クレームにつながった事例もあるといわれます。
そのため、チャットボットは教育が最も重要であることをはじめから押さえておくことが、チャットボット導入のポイントであり、注意点でもあります。
チャットボットサービスを選ぶ場合には、教育はどのように行うことができるのか、また、その教育方法はどのくらい負荷がかかるのかをよく事前に確認しておくのをおすすめします。できるだけ簡単に誰でも行えるサービスを選ぶのが、運用の負荷を減らすと同時に、チャットボットの導入効果を最大化するコツです。
チャットボットの導入を成功させるためには、計画的な手順を踏むことが不可欠です。導入の各段階での注意点を押さえた上でチャットボットを構築することが重要です。
1.目的と範囲の明確化
まず、「なぜチャットボットを導入するのか」という目的を明確にします。例えば、「顧客満足度の向上」「オペレーターの業務効率化」「24時間365日の問い合わせ対応」など、具体的なゴールを設定します。次に、その目的を達成するために、どの範囲の業務をチャットボットに任せるかを定めます。すべての問い合わせを自動化しようとせず、まずは特定の領域(例:よくある質問への回答)から始めるのが現実的です。顧客のニーズを分析し、対応範囲を適切に定めることが、導入失敗のリスクを減らす最初の注意点です。2.ツールの選定とシナリオ構築
目的と範囲が決まったら、それに合ったチャットボットツールを選定します。提供される機能、サポート体制、費用、構築の難易度などを比較検討しましょう。無料トライアルが可能なツールも多いので、実際に利用して操作性を確認することをおすすめします。ツール選定と並行して、チャットボットの会話の流れとなるシナリオを構築します。ユーザーがどのような質問をするかを想定し、分かりやすく、解決に導く回答を用意することが重要です。チャットボットをかしこくし、顧客対応の品質を向上させるためには「教育」が必要であることをお伝えしました。チャットボットには「人工無能」と言われるルールベース型と、「人工知能」と言われる機械学習型の2種類があるため、それぞれ教育方法が異なります。
1つ目のルールベース型とは、利用者からのあらかじめ想定される問い合わせや質問とその答えをデータベースに登録しておけば、その通りにロボットがチャット(回答)してくれるものです。こちらは「考える脳」がない人工無能型のチャットボットなので、どれだけ想定問答集を登録しておけるかが、チャットボットの「かしこさ」に直結し、育てることができます。
2つ目の機械学習型はAIがお客様とのチャット内容を基に、情報を蓄積し、どんどんかしこくなっていく人工知能を搭載したタイプのものです。こちらも初期は「教師データ」という想定問答を勉強させますが、大切なのはお客様とのチャットを通じて、AIに色々な会話の経験をさせることです。AIは経験を積めば積むほど、情報を蓄積し、かしこくなっていきます。逆にチャットを使う人が少なければデータが集まらず、データが無ければ学習ができず、結果としてAIは頭が悪いままになってしまい、お客様からの評判を落としてしまう、というデフレスパイラルが生まれます。

チャットボットの導入を検討している方は、管理画面の見やすさ、使いやすさなどと共に、以下のような教育機能がついているかをしっかりと確認しましょう。
1.質問とその回答内容の管理がしやすいか
初期に作成した質問と回答をCSVファイルで一括登録したり、運営途中で追加・修正したい内容が発生した際に管理画面から直感的(感覚的)に登録できるかどうかが重要です。2.ユーザー辞書が使いやすいか
固有名詞の登録をしたり、業界独特の言い回しや略称、表現のゆれなどを登録することができれば、回答精度の向上につながります。1つの質問につき、違う表現でも質問を登録できるように、類義語辞書が使えるかどうかも確認しましょう。3.チャット内容の確認ができるかどうか
チャット完了時に取得する満足度/不満足度などの定量データだけでなく、定性データであるチャット内容を定量データに紐づけて確認できることが重要です。例えば不満足の方だけを抽出してそのチャット内容を分析すれば、課題や改善点が見つけやすくなります。4.会話のシナリオ設計がしやすいかどうか
チャットボットの導入初期に最もつまずきやすいのが、会話のシナリオ設計です。Aという質問が出たらBという回答を表示して、次にCとDについての情報は必要ですか?などと、利用者と会話を続けていくためのシナリオ設計と登録がしやすいかどうかも「チャットボットのかしこさ」と「顧客満足度」に大きく影響してきます。
ある程度導入してみたいチャットボットの目星がついたら、そのチャットボットのトライアルやデモ画面を活用し色々な角度で話しかけてみるとよいでしょう。あえて曖昧な表現をつかったり、口語調で話しかけるように入力してみたりすることで、そのチャットボットのかしこさやチューニングのしやすさを体感してみることが重要です。
導入が確定したら、自分がお客様だったらどんな質問をするだろうか、ということを徹底的に考え、質問集に書き込んでみてください。
チャットボット導入による成果創出事例は続々と出ていますが、人材採用にチャットボットを使うことで成功しているケースも増えてきています。この場合も、就職説明会や採用面接では面と向かって聞きづらい内容をあえて企業側からチャットボットに登録することで、応募者から共感と信頼を得ることに成功しているそうです。
ある企業は採用サイトのチャットボットに、「月間の平均残業時間は?」「残業代未払いはある?」「有給消化率は?」「社員年齢構成比は?」「会社の雰囲気は明るい?」「飲み会は強制参加?」「お茶出しは女性社員の仕事?」など、なかなか聞きづらい質問とその答えを登録しておいたところ、学生に本音で語ってくれる会社として合同説明会で大人気だったそうです。
これからチャットボットを導入しようとしている企業様は、「回答精度の低いチャットボットにお客様と会話をさせて信頼を落としてしまう」ことの無いように、しっかりと研究と準備を行うことをおすすめ致します。かしこいチャットボット君を教育し育てるのは、管理者の役割でもあります。
チャットボット製品サイトはこちら
AIを搭載したチャットボットの利用シーンは飛躍的に拡大しています。以下ではAIがどのようにチャットボットで活用されているか具体的な例をご紹介します。
高度な問い合わせへの自動対応
AIチャットボット最大の強みは、ユーザーの曖昧な表現や文脈を理解し、自然な対話を通じて最適な回答を自動で導き出せる点です。これにより、これまでは有人オペレーターの介入が必須だった複雑なニーズにも対応可能になっています。例えば、社内ヘルプデスクにおいて、従業員それぞれの状況に応じたIT関連のトラブルシューティングを自動で行ったり、ECサイトで顧客の好みを学習し、パーソナライズされた商品を提案したりといったことが可能となります。一方で、このような高度なツールを構築する場合、AIの学習に多くのデータを用いるという点には注意が必要です。業務プロセスとの連携
AIチャットボットをRPA(Robotic Process Automation)やCRM(顧客関係管理)といった他のシステムと連携させることで、単なる問い合わせ対応ツールを超えた活用ができます。例えば、顧客からの予約受付をチャットボットで完結させ、その情報を自動で予約管理システムに登録するといった一連の業務を自動化できます。このような連携の設定は、オペレーターの作業を大幅に削減し、コア業務への集中が可能となります。このように、AIチャットボットをうまく活用することで業務プロセス全体の再構築と効率化へとつながるのです。

チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!











