社内コミュニケーションを活性化させるには?
最新のトレンドや課題の原因、活性化する10の施策も紹介

社内コミュニケーションとは、社内において情報やノウハウなどの共有を円滑に行うことです。継続的な企業活動には、良好な社内コミュニケーションが欠かせません。この記事では、企業の担当者に向けて、社内コミュニケーションを活性化するための具体的な方法を解説しています。自社での社内コミュニケーションの改善に役立ててください。
社内コミュニケーションとは、社員同士が情報やノウハウなどを共有し、お互いに円滑なやり取りができることです。以下で詳しく解説します。
業務効率化やビジネスの成功に重要
社内コミュニケーションとは、社員同士のやり取りや情報共有を円滑に行うことです。業務の遂行には、他部署や他の社員との連携を図るうえで、円滑なコミュニケーションが欠かせません。また、社内コミュニケーションは、業務効率アップやビジネスの成功の一端を担う重要な要素とされています。とくに、新型コロナウイルスの拡大に伴い、リモートワークの導入や社内コミュニケーションの改善に取り組む企業が増えています。

従来のオフィスワークから、リモートワークやサテライトオフィスなどに移行したことで、社員がオフィスで業務を行うなどの価値観が変わってきました。社員同士に物理的な距離がある中で業務を進めていくには、積極的な社内コミュニケーションが必要です。たとえば、チャットツールやタスク管理ツールなどの導入により、自社にあった環境をつくり出せます。
社内コミュニケーションが活性化すると、企業はどのようなメリットを得られるのか、以下で解説します。
情報共有
社内コミュニケーションが活性化すると、リアルタイムでの情報共有が可能です。タイムリーな情報共有ができれば、業務を円滑に進められます。一方で、業務の遂行に必要な情報にアクセスできる仕組みがなければ、業務に支障をきたしてしまいます。情報共有には、業務効率化ツールやチャットツールの導入がおすすめです。業務効率化・生産性向上
社内コミュニケーションが円滑になると、業務分担がしやすくなったり、積極的に業務に携わろうとする社員が増えたりするなどのメリットが得られます。結果的に、業務効率化や生産性向上などの成果が期待できます。業務効率アップには、業務効率化ツールやチャットツールの導入がおすすめです。社員満足度の向上
社員同士や上司・部下間でのやり取りが円滑になれば、お互いに意見を伝えやすい職場環境を作れるようになります。会社は、社員の意見を吸い上げやすくなり、福利厚生の充実などに反映させることで、社員のモチベーションや満足度を高めることも可能です。離職率・定着率の改善
社員の満足度や自社への愛着心の向上により、離職率の低下につなげられます。社員の定着率が改善されれば、他社への優秀な人材の流出を防げるため、企業は安定した経営を行えるようになります。顧客満足度の向上
社内コミュニケーションが不足するとミスを誘発しやすくなり、顧客満足度の低下を招くことがあります。一方、社内コミュニケーションが円滑になれば、顧客対応が迅速にできるため、企業の信頼度が高まり、結果的に利益を生み出せます。企業ブランドイメージの向上
社員が働きやすい職場環境を整備している企業は、メディアなどで紹介されるケースが多いです。そのため、企業のブランドイメージの向上が期待できるうえに、社員の帰属意識を生むきっかけになります。近年、働き方の変化に伴い、課題はより複雑化しています。ここでは、多くの企業、従業員が直面している代表的な課題を3つご紹介します。
リモートワークと出社社員間の情報格差
ハイブリッドワークの普及は、オフィス勤務者とリモートワーカーとの間に情報格差や心理的な距離を生んでいます。オフィスでは、何気ない雑談から新しいアイデアや仕事のヒントが生まれる機会がありますが、リモートで働くメンバーは、こうした会話の輪に入ることができません。重要な方針転換といった情報も、オフィスでの口頭共有が中心になると、リモートワーカーに伝わりにくくなります。この状況が、「出社しないと情報が得られない」という不公平感やチームの一体感の喪失に繋がっています。世代間のコミュニケーション手法の違い
スムーズな意思疎通を妨げる要因に、世代間の「当たり前」とする手法の違いが挙げられます。例えば、対面や電話での会話を重視する管理職・ベテラン世代と、チャットでのテキストコミュニケーションを好む若手世代とでは、認識のズレが生じがちです。若手は「チャットで済むのに」と感じ、管理職は「テキストだけでは本心がわからない」と不安を覚えるなど、互いにストレスを感じる場面が増えています。このすれ違いが、報告・連絡・相談の遅れやためらいを生み、仕事に支障をきたす可能性があります。ハラスメントを恐れて会話が減っている
コンプライアンス意識の高まりは健全な職場に不可欠ですが、一方で「ハラスメントと捉えられる可能性がある」という過度な懸念が、コミュニケーションの萎縮を招いています。特に管理職が部下との関わり方に悩み、業務外の雑談を避け、業務連絡のみに留めてしまうケースは少なくありません。このような過度な配慮は、従業員間の信頼関係の構築を妨げます。結果として、チームメンバーの孤立感を招くだけでなく、本来生まれるはずだった新しいアイデアの芽を摘んでしまうことにもなりかねません。
社内コミュニケーションが不足する原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。
以下ではコミュニケーションが不足する主な原因を解説します。
働き方の多様化による接点の減少
リモートワークの普及をはじめとする働き方の多様化は、物理的に顔を合わせる機会を大きく減らしました。特に、廊下や休憩室で生まれていた偶発的な雑談が激減した影響は深刻です。この雑談は、新しいアイデアの源泉となることも多く、その喪失は組織の活力を削ぐ一因となります。離れた場所で働くメンバー間では、心理的な距離も生まれがちです。心理的な壁と組織風土
組織の風土や文化も、コミュニケーションを妨げる大きな要因です。経営層が掲げる方針が一方的に伝達されるだけで、現場の従業員が意見を言える雰囲気がなければ、双方向の対話は生まれません。「発言しても否定される可能性がある」と感じる心理的な壁は、活発な意見交換を阻害します。結果として、気軽に相談できなくなり、業務をスムーズに進める上での障害となるのです。業務の多忙化と時間的余裕の欠如
個々の仕事の多忙化も、コミュニケーション不足の直接的な原因です。多くの従業員が自身の業務に追われ、他者と関わる時間的・精神的な余裕を失っています。特に、業務が専門化・属人化すると、「自分の仕事とは関係ない」という意識が強まり、部門間の連携はさらに希薄になる可能性があります。
社内コミュニケーションを活性化させる具体的な方法について解説します。自社で取り組む際の参考にしてください。
業務効率化ツール・チャットツール
社内コミュニケーションの活性化には、業務効率化ツールやチャットツールが有効です。なかでも業務効率化に主眼を置くなら、チャットボットがおすすめです。チャットボットは、社内外からのチャットによる質問や問い合わせに対してロボットが自動で応答してくれます。また、チャットツールでは、リアルタイムでの情報共有によってコミュニケーションを活性化できます。Web会議・テレビ会議
Web会議システムでは、インターネット回線を利用してリアルタイムでのやり取りが可能です。テレビ会議システムは、オフィスの会議室と遠隔地を結び、円滑なコミュニケーションがとれます。どちらも、ミーティングだけでなく、社内外の勉強会や座談会などに活用できます。1on1
1on1とは、上司と部下が1対1で面談を個室空間で行うことです。一般的に、目標管理や業務上の進捗確認などの目的で実施されています。1on1の実施により、上司・部下の関係性の改善が期待できます。社内SNS
社内SNSとは、社内でのみ利用できるSNSのことです。社内SNSでは、情報やノウハウの一斉配信や閲覧、タスク共有などが可能です。社内SNSの利用によってコミュニケーションが活発にできるため、上司・部下、部署、社員同士などのつながりを強化できます。社員研修・ワークショップ
社員研修は、社内の社員を対象にした研修のことです。一方、ワークショップは体験型の講習のことで、講師が一方的に話すのではなく、グループワークなどを取り入れ、参加者が課題に取り組む特徴があります。経営層、管理層、社員など、各層でコミュニケーション力アップを目的とした社内研修やワークショップを実施すれば、組織全体のコミュニケーションスキルを向上できます。社内報
社内報は、経営者や社員へのインタビュー、社内のニュース、業績の報告などを社員に向けて発信するための広報誌です。冊子などを社員に配布するのではなく、社内SNSやメルマガなどによる配信を行う企業が増えています。社内報の活用により、社内での出来事や社員のプロフィールなどの情報共有が行えるため、会社への愛着心を育むことにつながります。社員食堂・カフェ
社員食堂やカフェがあれば、経営層と社員、他部署の社員同士が交流しやすくなります。たとえば、昼食時に食事をとりながら、普段関わりのない部署の社員と気軽に会話を楽しむ、情報交換し合うことも可能です。福利厚生の充実により、社員満足度の向上や企業ブランドのイメージ向上も期待できます。レクリエーション・イベント
社内でのレクリエーションやイベントの開催も、社内コミュニケーションを活性化するうえで有効な手段です。たとえば、部活動や運動会、社員旅行、バーベキューなどが挙げられます。レクリエーションを通して、業務以外での社員同士のつながりを作れます。また、上司や同僚の普段は見られない一面を知り、親近感をもたせるきっかけとしても効果的です。社内ポイント制度など
社内ポイント制度は、感謝・称賛を伝えたい社員に対して、社員同士がポイントを送り合うための制度です。社内通貨とも呼ばれています。社内通貨の導入により、社員のモチベーションの向上や行動指針の浸透などを通じて、組織文化の形成につなげられます。フリーアドレス制度
フリーアドレス制度とは、固定席ではなく、社員が好きな場所で業務を行える仕組みのことです。フリーアドレス制度の導入により、働き方改革の促進や役職や部署を超えた、気軽なやり取りを促せます。近年の社内コミュニケーションには、注目すべきいくつかのトレンドがあります。これらは、働き方の変化や、組織と個人の関係性の進化を反映したものであり、これからの企業経営において非常に重要です。
ハイブリッドワークにおける意図的な機会創出
ハイブリッドワークの定着により、意図的なコミュニケーションの機会を創出することが不可欠になっています。オフィスでの偶発的な雑談が減った今、ビジネスチャットに雑談専用チャンネルを設けたり、オンライン懇親会を定期的に開催したりするなど、意識的な工夫が求められます。こうした取り組みは、離れた場所で働くメンバー間の連携を深め、新しいアイデアが生まれる土壌を育むために欠かせません。コミュニケーションの「質」を高める心理的安全性
コミュニケーションの「質」がこれまで以上に重視されるようになりました。特に、従業員一人ひとりが安心して発言できる「心理的安全性」の確保は、イノベーションの鍵とされています。心理的安全性が高い職場では、失敗を恐れずに挑戦したり、気軽に相談し合ったりできるため、創造的なアイデアが生まれる可能性が飛躍的に高まります。これは従業員の幸福度(ウェルビーイング)にも直結する重要な要素です。エンゲージメントを高める戦略的コミュニケーション
コミュニケーションは従業員エンゲージメント(企業への貢献意欲)を高めるための戦略的な手段と位置づけられています。単なる情報共有に留まらず、会社の方針やビジョンを丁寧に伝え、個々の仕事が組織全体にどう貢献しているかを示すことが重要です。これにより、従業員は自らの仕事に誇りを持ち、組織目標の達成に向けてスムーズに連携できるようになります。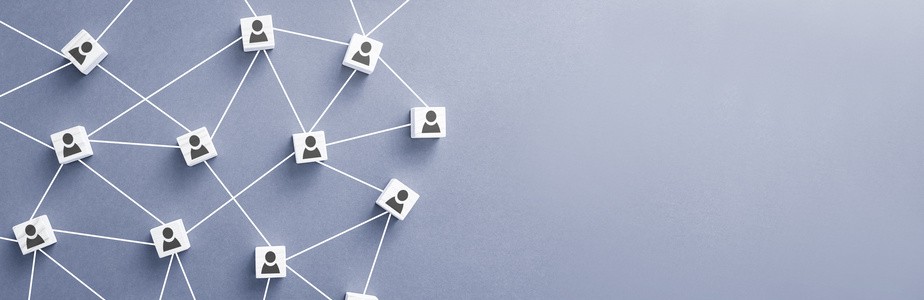
ここでは、社内コミュニケーションの改善に効果的な企業の事例について紹介します。
佐川グローバルロジスティクス株式会社
佐川グローバルロジスティクス株式会社では、人事、経理、基幹システムなどへの問い合わせが集中する、本社部門の業務効率を上げたいという課題を抱えていました。業務効率化に効果的なチャットボットの導入により、問い合わせ対応の効率化を実現しています。西武鉄道株式会社
西武鉄道株式会社の情報システム部では、社内向けのヘルプデスク業務の効率化が課題でした。チャットボットの導入により、業務の3割をチャットボットに誘導し、業務効率の向上につながっています。また、メンテナンス工数が減り、属人化リスクも低減しました。ヤマハ発動機
ヤマハ発動機では、2016年1月に社内報のコンテンツ内容の刷新を図りました。リニューアル前は、20代の若手社員の閲読率が低かったものの、若手社員向けに文字数を減らし、フルカラーにするなどの工夫をしたところ、社内報の閲読率が84.8%に向上しました。日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ビジネスシステムズ株式会社では、2014年に社員食堂を開設しました。開設前は、社員同士の交流が少なく、会社への帰属意識が薄いことが課題でした。開設後は、昼はランチ、夜はバーとなり、上司と部下、社員同士の交流の場として広く活用されています。Yahoo!
Yahoo! JAPANでは、東京本社の移転に伴い、フリーアドレス制度の導入を決めました。本社勤務の全社員の約5,700名が、20フロアに渡る執務エリアの好きな場所で働ける環境を整備しました。移転後は、社内外の勉強会やライトニングトーク(LT)などが頻繁に開催されています。コニカミノルタ
コニカミノルタ株式会社では、2020年度の入社式をオンラインで実施しました。新型コロナウイルスの感染防止に加え、社長が新入社員に直接メッセージを共有したいという思いから、東京本社と国内の5拠点にライブ映像をリアルタイムで配信しました。
前述にて社内コミュニケーションの改善に効果的な企業事例の中で、業務効率化を目的として、チャットボットを導入した企業をご紹介しました。
そもそもチャットボットとは、Webサイトやアプリなどに組み込むことで、Web上でユーザーからの質問に24時間365日自動回答を行うツールです。
チャットボットを導入することで、問い合わせ対応などを自動化することができ、問い合わせ業務以外に対応できる時間が増えるといったメリットもあります。
その他にも社内コミュニケーションの活性化で得られるメリットしてもあげられた、顧客満足度の向上にもチャットボットは役立つため、昨今チャットボットを導入する企業が増えています。
社内コミュニケーションの活性化は、業務効率化や企業ブランドイメージの向上につなげられます。上述した施策を参考にして、自社にあった方法を実施し、社内コミュニケーションを高めましょう。
「RICOH Chatbot Service」は、たくさんの大手企業の社内問合せ対応にも採用されており、問合せ対応時間半減、満足度70%を実現するなどの成果をあげています。手厚いサポートもついているため、興味のある方は資料のダウンロードをお試しください。
Enterpriseプランの詳細はこちら
Enterpriseプラン紹介資料のダウンロードはこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!











