業務効率化する8つの手法|進める手順や役立つツール、フレームワーク、注意点について解説

業務効率化とは、自社の非効率な業務を改善することです。業務効率化にはさまざまな手法があるため、自社の状況にあわせて手法を選択する必要があります。この記事では、社内の業務効率化について検討している担当者に向けて、業務効率化の手法について解説します。手順や役立つツールについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
業務効率化とは、どのようなことを表しているのでしょうか。ここでは、業務効率化の概要やメリットについて解説します。
概要
業務効率化とは、業務の「ムリ」「ムダ」「ムラ」を解消して非効率な部分を改善することです。業務効率化には、さまざまな手法があります。たとえば、業務にかかる時間を短縮したり、不要な作業をなくしたりするなども一つの方法です。そのような視点で見れば、パソコンのショートカットキーにより操作の工数を減らすのも、業務効率化の一例です。業務効率化するメリット
業務効率化を実現できれば、コスト削減が期待できます。余計な手間や時間も減らせるため、社員の仕事に対するモチベーションもアップさせられます。業務の生産性も向上し、同じ労力でも高い成果を生み出せるようになるでしょう。業務効率化を目指すと、企業側と社員側の両方にメリットがあります。業務効率化と生産性向上は、しばしば同じ意味で使われがちですが、厳密には「手段」と「目的」という関係性にあります。この違いを理解することが、効果的な施策を推進する第一歩となります。
手段としての業務効率化
業務効率化とは、業務のプロセスにおける「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、より少ないリソース(時間、コスト、労力)で作業を完了できるようにすることを目指す取り組みです。
例えば、「資料作成にかかる時間を半分にする」「複数の部門にまたがる承認プロセスを簡略化する」といった活動がこれにあたります。あくまで焦点は、既存業務のプロセスをいかにスムーズにし、コストや時間を削減するかに置かれます。これは後述する生産性向上を達成するための重要な手段の一つです。
目的としての生産性向上
一方、生産性向上とは、投入したリソースに対して、得られた成果を最大化することを目指す概念です。計算式で「生産性 = 成果 ÷ 投入リソース」と表されます。
業務効率化が「投入リソース」を減らすアプローチであるのに対し、生産性向上は「成果」を増やすアプローチも含む、より広範な概念です。例えば、業務効率化によって従業員の作業時間が短縮されても、その空いた時間で新たな価値を生み出さなければ、企業全体の「生産性」が向上したとは言えません。業務効率化は、生産性向上という最終目的を達成するためのステップと言えるでしょう。

業務効率化を進めるにはどうすればいいのでしょうか。ここでは、業務効率化の進め方について解説します。
1.現状を把握する
自社の現状を把握するため、業務の棚卸しを実施しましょう。具体的には、業務の担当者の割り振り、作業時間、使用しているツール、必要なスキルなどについて部署ごとにそれぞれ確認します。2.効率化する業務を選ぶ
自社の業務のうち、どの業務を効率化すべきか検討します。効率化しやすい業務を選ぶと、成果も出しやすくなります。また、自社が抱えている課題にあわせ、その解決に役立つ業務を選んで効率化することも大切です。3.手法の検討と実施
効率化しようと考えている業務にあわせ、最適な手法を選びましょう。さらに、業務効率化のスケジュールを立て、具体的にどのように進めるか考えます。スケジュールに沿ってプロジェクトを実行しましょう。4.効果検証と改善
業務効率化のためのプロジェクトを実行したら、効果検証を行います。想定していたような効果を得られなかった場合は、原因を特定して改善しましょう。PDCAサイクルを回し、より高い効果を得られるようにすることが大切です。業務効率化の手法としてはさまざまなものがあります。ここでは、具体的な8つの手法について解説します。
業務を自動化する
社員がそれまで手作業で行っていた業務を機械に任せることができれば、業務の自動化を実現できます。たとえば、エクセルのプログラムを使えば入力作業を自動化できます。ヘルプデスクやカスタマーサポートにチャットボットを導入すると、対応の自動化が可能です。このような単純な作業を自動化すれば、複雑な作業により多くの労力を割きやすくなります。不要な業務を削除する
日常的に行っている業務のなかには、不要なものが存在する可能性があります。たとえば、オンライン会議を導入すれば、無駄な会議を減らすきっかけになります。さらに、社員にリモートワークを認めると、通勤時間の削減が可能になり効率化につながるかもしれません。本当に必要なものだけを残し、無駄なく業務を進められるようにしましょう。分業化する
業務によっては分業すると効率化につながる場合もあります。1人が担当している業務をわけ、作業ごとに各担当者が集中的に取り組めるようにしましょう。分業すると単独で作業するよりも、それぞれの役割を徹底しやすくなります。1人で幅広い業務に対応するよりも、効率的に進められる可能性が高いです。担当者を変える
分業化したら、業務にあわせて担当者を変えるのもひとつの方法です。人材によってスキルや得意分野はそれぞれ異なるため、業務との相性を考慮して担当者を割り振ればより効率的に業務を進めやすくなります。それぞれの能力に適した業務を担当させ、スムーズに業務を進められるようにしましょう。業務の優先順位を明確化する
ワークフロー全体を見直し、業務の優先順位を明確にすることも大切です。企業の運営をスムーズに進めるためには、優先順位の高い業務ほど力を入れて取り組む必要があります。利益率を高めるための業務を優先し、時間や労力を割けるようにしましょう。それにより、最小限のリソースで効率的に利益を出せるようになります。データベースを活用する
社内全体の業務を効率化するためには、情報共有を徹底しましょう。すべての社員が同じ条件で情報を閲覧できるよう、データベースを作って一元管理するのがおすすめです。データベースで情報をまとめておけば、社内共有や後任への引き継ぎの際もスムーズに必要な情報を伝えられます。データベースの活用方法や運用のルールも定めて共有してください。業務マニュアルを作成する
業務に関するマニュアルを作成すれば、業務のやり方やルールを客観的にまとめられます。社員はわからないことがあってもマニュアルですぐに確認できるため、人によって業務のやり方に差が出るおそれもなくなります。混乱を少なくし、属人化しやすい業務の成果を平均化することが可能です。外注する
単純な作業は社内で対応するのではなく、外注すると大幅な効率化につながります。外注すれば自社の社員が対応する必要がなくなるため、利益につながるより重要な業務に労力をかけやすくなります。外注するにはその分のコストもかかりますが、費用対効果を考慮したうえで問題なければ外注することも検討しましょう。
業務効率化を推進する際、どこから手をつければよいか迷うケースも少なくありません。ここでは、具体的な改善施策を見つけ、優先順位をつけるために役立つ代表的なフレームワークを2つ紹介します。
ECRS(イクルス)
ECRS(イクルス)は、業務プロセスを改善するための視点を示すフレームワークです。以下の4つの頭文字をとったもので、この順番で検討することが推奨されます。
・Eliminate(排除):その業務は本当に必要か? なくせないか?(例:形骸化した日報や、不要な会議を廃止する)
・Combine(結合):複数の業務をまとめられないか?(例:部門ごとに行っていたデータ集計作業を一本化する)
・Rearrange(交換):順序や場所、担当者を変更できないか?(例:営業担当が行っていた事務作業を、アシスタントがまとめて処理する)
・Simplify(簡素化):より単純な方法で実行できないか?(例:複雑なExcel管理を廃止し、専用のITツールを導入する)
4象限マトリクス
ECRSで改善のアイデアが出たら、次に「どの業務から手をつけるか」を決定する必要があります。そこで役立つのが、「重要度」と「緊急度」の2軸で業務を分類する4象限マトリクスです。
1.重要かつ緊急:すぐに対応すべき業務
2.重要だが緊急でない:計画的に取り組むべき業務
3.重要でないが緊急:簡素化・自動化・IT化の対象となる業務
4.重要でも緊急でもない:排除(Eliminate)の対象となる業務
多くの従業員は1と3の業務に追われがちです。業務効率化とは、特に3と4の業務を削減し、最も価値のある2の業務に取り組む時間を創出する活動とも言えます。業務の優先度を設定する際に活用できます。

業務効率化を進めるうえではツールを使用すると便利です。ここでは、業務効率化のために役立つツールについて解説します。
チャットボット
チャットボットとは、コンピューターが自動で応答して会話できるプログラムのことです。問い合わせの窓口にチャットボットを導入すれば、社内外からの問い合わせを自動化できます。担当者が個別に対応する必要がなくなり、担当者の負担を軽減できるだけでなく、対応の質も向上させられるでしょう。
チャットボット(Chatbot)とは?│初心者にもわかりやすく解説
グループウェア
グループウェアとは、オンライン上で情報を共有したりコミュニケーションをとったりできるツールです。具体的には、会議室の予約、ワークフローの電子化、タイムカード、レポートの共有などさまざまな機能がついています。グループウェアがあればさまざまな業務をまとめて管理できるため、業務効率化につながります。
ビジネスチャット
ビジネスチャットとは、ビジネスでの利用を想定して設計されているチャットツールです。電話やメールを使用するよりも、スピーディかつ効率的に情報をやりとりできます。チャットができるだけでなく、ビデオ通話、ファイル管理、タスク管理などさまざまな役立つ機能が搭載されている場合もあります。
RPA
RPAとは「Robotic Process Automation」の略であり、業務をロボットに代行させる方法です。RPAを活用すると、たとえば、営業活動において得られる顧客情報の整理も自動化できます。情報を簡単に整理できれば、購買意欲が高い顧客の分類もしやすくなります。業務を効率化でき、よりスムーズに成果を出せるようになるでしょう。
業務管理システム
業務効率化に役立つシステムとしては、勤怠管理システム、生産管理システム、営業管理システムなどさまざまなものがあります。それぞれ特定の業務に特化したシステムになっており、日々の業務において生まれる情報を一括で管理可能です。分類や整理もスムーズに行えるため、情報の有効活用がしやすくなります。
さまざまな企業が業務効率化に力を入れています。ここでは、業務効率化に成功した企業の事例を紹介します。
西武鉄道株式会社
社内向けのヘルプデスクにチャットボットを導入していたものの、使い勝手に問題がありました。自社の状況に即したチャットボットに切り替えたところ、自動で回答できる割合が増加しました。適切な回答を示せない場合も、類似する回答を表示でき、大幅に負担が減っています。※参考:チャットボット導入によりヘルプデスク業務の全体の効率化を実現|RICOH Chatbot Service
佐川グローバルロジスティクス株式会社
幅広いだけでなく問い合わせ数も多く、回答に手間がかかっていました。また、担当者による回答の差も課題となっていました。そこで精度の高いチャットボットを導入した結果、70%以上の高い満足度を実現することができました。担当者が対応すべき問い合わせ数は半減しました。※参考:チャットボット導入で社内問い合わせ時間の課題を半減した事例|RICOH Chatbot Service
リコージャパン コーポレートセンター 経理部
経理部に対して電話による問い合わせが多く寄せられており、主業務を圧迫していました。チャットボットを導入したところ、電話による問い合わせは3カ月で1,000件も減少しています。また、電話の着信の減少により、リモートワークにもより取り組みやすくなっています。※参考:チャットボット導入で働き方改革 - 問い合わせ1,000件削減|RICOH Chatbot Service 個人・企業で取り組める業務効率化のアイデア【16選】|役立つツールも紹介
業務効率化を目指すうえでは注意点もあります。ここでは、失敗のリスクを減らして業務効率化を成功させるためのポイントを解説します。
スピード重視は質の低下につながる
スピードを重視しすぎ、作業時間の短縮だけにこだわる企業も少なくありません。しかし、単に作業時間を短縮しようとすると、社員にとっての負担が重くなる可能性があります。そうなると、業務の質の低下につながるため注意が必要です。社員にビジョンを共有しないと成果が出ない
業務効率化を進めるうえでは、社員に対して目的や目標を共有する必要があります。それぞれを理解できていないと、成果につながりにくくなるためです。組織全体で体制を整え、業務効率化を目指しましょう。自社に合うツールの選定を行う
業務効率化を目指すうえでは、ツールやシステムを活用すると効果的です。しかし、導入したツールやシステムが使いづらければなかなか定着しません。社員にとって使いやすく、現場に適しているツールやシステムを選びましょう。
前述にて業務効率化に役立つツールとして、チャットボットをご紹介させていただきました。本章では実際にチャットボットの導入を検討する際に、どういったポイントを抑えるべきなのかを簡単に紹介します
・チャットボットの導入目的を明確にする。
・導入検討しているチャットボットが導入目的に適しているのか。
・導入が簡単にできるのか。
・デモ画面や無料トライアルを活用し、事前に使用感を試せるのか。
・導入前後のサポート体制が整っているのか。
上記の他にも、外部ツールとの連携やセキュリティの内容など、様々なポイントを鑑みて、自社にあったチャットボットを選定することをおすすめします。
チャットボットの導入事例19選!業界別の事例や導入手順・費用も解説
AIチャットボットの登場は、業務効率化の新たな手段を提供しています。従来のシナリオ型チャットボットと異なり、AIチャットボットは対話の意図を理解し、より複雑なケースにも柔軟に対応できます。
社内バックオフィス業務の自動化
企業のバックオフィス部門(人事、総務、経理、情報システム)には、従業員からの定型的な問い合わせが日常的に発生します。これらの対応は、各部門の担当者にとって大きな負担となります。AIチャットボットを社内ポータルやビジネスチャット環境に導入することで、これらの問い合わせ対応を自動化できます。これにより、従業員は検索の手間なく自己解決でき、バックオフィス担当者は本来のコア業務に集中できる環境が整います。
営業・マーケティング活動の支援
AIチャットボットの活用は社内だけに留まりません。営業やマーケティング領域でも、データを活用した業務効率化を推進できます。例えば、Webサイトに来訪した顧客からの「製品Aと製品Bの違い」といった質問に対し、AIチャットボットが製品データやFAQを基に即時回答することで、顧客満足度の向上と営業機会の損失防止につながります。さらに、チャットの対話履歴(どのような質問が発生したか)をデータとして蓄積・分析することで、顧客のニーズや製品改善のヒントを得ることも可能です。複数の顧客対応をAIが一次窓口として担うことで、営業担当者はより成約確度の高い見込み客への対応にリソースを集中させることができます。
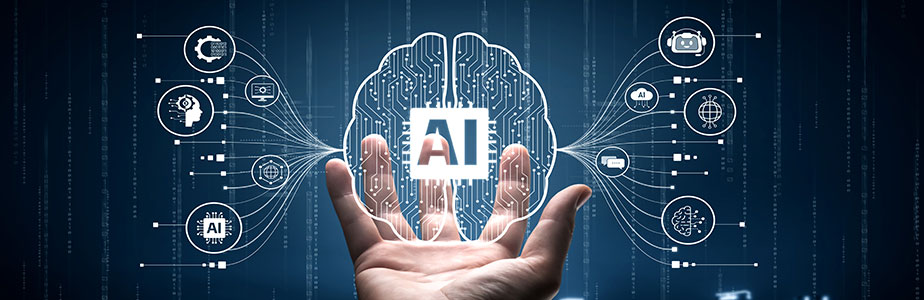
業務効率化を実現するには、さまざまな手法があります。自社の状況を確認し、最適な手法を選んで実践しましょう。そのためには、業務効率化に役立つツールやシステムを上手に活用することも重要です。
「RICOH Chatbot Service」は、簡単に導入でき、運用も非常に楽なチャットボットです。学習済みのAIを使用しており、表記ゆれも自動で吸収できます。サポートも手厚く安心です。ぜひ導入をご検討ください。
資料ダウンロードはこちら
チャットボットお役立ち資料
RICOH Chatbot Serviceのサービス資料はもちろん、
導入事例集、チャットボットの基礎知識が学べる資料など
チャットボットに関する様々な資料をご用意!
是非、ダウンロードして御覧ください。

以下のような資料をご用意しています。
- チャットボットの種類とそれぞれのメリットデメリット
- チャットボットサービスを正しく賢く選ぶコツ
- RICOH Chatbot Service 導入事例集
- RICOH Chatbot Service サービス資料
など様々な資料をご提供中!











